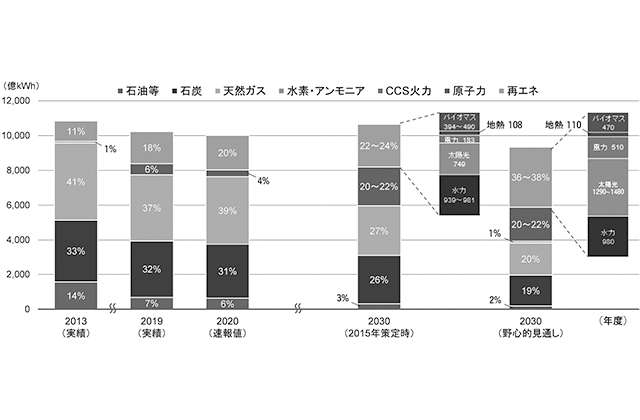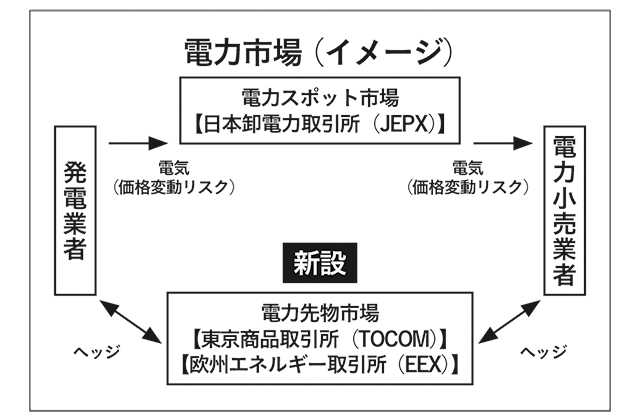【多事争論】話題:容量市場
2025年度を実需給年度とする容量市場の約定価格が、前回よりも大幅に下落した。
果たして現行のまま、供給力の安定的な確保という目的を達成する市場となり得るのか。
〈 市場への過度な行政介入 排除を意識した改善が必要〉
視点A:穴山悌三 長野県立大学グローバルマネジメント学部教授
わが国の容量市場について、2025年度分の第2回オークションの経過措置考慮後の約定総平均単価がkW時当たり3109円と、第1回の9533円から大幅に低下したことが耳目を集め、審議会などでもその評価が行われている。「市場なので価格が変動するのは当然である」とか、「過度なルール変更を都度行うのは適切ではない」といった審議会委員の意見はもっともであるものの、「この価格シグナルが4年後を的確に表しているかよく検討してもらいたい」との声にも矢面に立つプレーヤーの実感が込められている。
価格低下の背景には、電力・ガス取引監視等委員会が報告するように「事前監視の導入がNetCONE以上の応札に対するけん制を一定程度もたらしたことで、全体として、昨年度応札価格が高かった電源が低い価格で応札した」ことや、ゼロ円入札を含めて「NetCONE×50%(4686円)以下の供給量が約2700万kWも増加し、供給曲線が大きく右にスライドした」ことがある。
なお、CONE(Cost of New Entry)は、容量市場に新たに参入するプラントの長期的な限界供給費用を、Netはほかの市場(kW時を販売するエネルギー市場やΔkWを評価するアンシラリーサービス市場など)で得られる期待収益を差し引いたもの。新設電源は、kW時やΔkWの取引で得られる報酬の不足分を容量市場でカバーする必要があり、NetCONEはその見積評価額から導出される。
容量市場は「市場」とはいえ、人為的に設計されたメカニズムを通じて最適な電源容量確保へと導くことを期待するものであり、わが国に限らず容量市場を採用する当局はその設計に工夫を重ねる必要がある。米国PJMも、価格の不安定の解消などに細やかに修正を重ねて今日の制度を築いているが、なお人為的な設計に起因する各種の問題が存在し、さまざまな批判も続いている。
米国でも当局の恣意的な判断に懸念 数十億ドルの超過費用発生との分析も
トッド・アーガード、アンドリュー・クレイト両教授は共同執筆の論文「Why capacity market prices are too high」(22年)で、容量市場は「政策市場」であり、米国FERC(連邦エネルギー規制委員会)とRTO(地域送電機関)が価格が低すぎるという懸念にとらわれていると指摘。将来需要の想定やCONE計算の過大化傾向を検証して、これらが所要の容量を膨らませたために消費者に数十億ドルの超過費用が発生したと分析している。
「政策市場」は、従来の規制上の義務の下での遂行よりも効率的に、すなわちより低コストで政策目的(安定供給に十分な発電容量の確保)を達成するためのものである。そしてわが国の容量市場の設計・運営・規制には、ISO/RTOとしての広域系統運用の実績を重ねてきた米国以上に留意すべき点があるが、ここでは規制当局介入の増大に伴う諸課題について指摘したい。
わが国の公益事業の多くは規制産業として発展を遂げ、その後、いわゆる規制緩和を進めてきた。この過程で、許認可などの事前規制の緩和や事後的なチェックへの移行などの合理化を進めてきた。電気事業について見れば、旧一般電気事業者のアンバンドリングなどの構造変化もその一環であるはずであるが、安定供給不安に対処する容量市場のような制度設計において過度に規制当局の介入を強めることになれば、いわゆる政府の失敗を招いて事業者の主体的な経営活力を損なう恐れもある。
PJMにおいても、政治的なプロセスや当局の恣意的な判断に対する懸念が表明されている(上述論文)。容量市場の管理・運営について、また各市場参加者への事前介入について、裁量的な判断を伴う不透明なプロセスを許容することは、旧規制下における一般電気事業者が、透明化されたルールの下での意思決定を通じて安定供給責任を負っていた状況以上に非効率な結果を招きかねない。
「売り惜しみ」の事前監視や電源休廃止などの意思決定・実施のタイミングに過剰な制約を与えたり、「価格つり上げ」の監視と称して事前監視対象電源をもとにした維持管理コストの内訳を詳細に問うたりといった行政関与がいき過ぎると、実質的な退出規制や許認可規制時代の料金査定と同様になりかねない。減価償却費を含めないとルール化することも、原価回収できない事業者にとって不採算判断の材料となり得る。
当局には当初の自由化の趣旨に鑑みて、容量市場の引き続きのチューンアップに際しては過度な介入の排除という観点もぜひ意識してもらいたいと願っている。