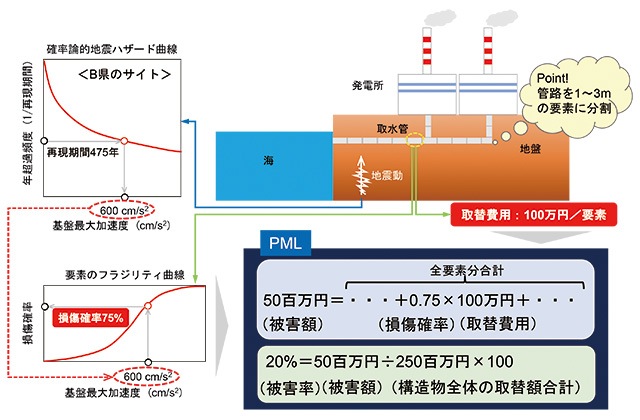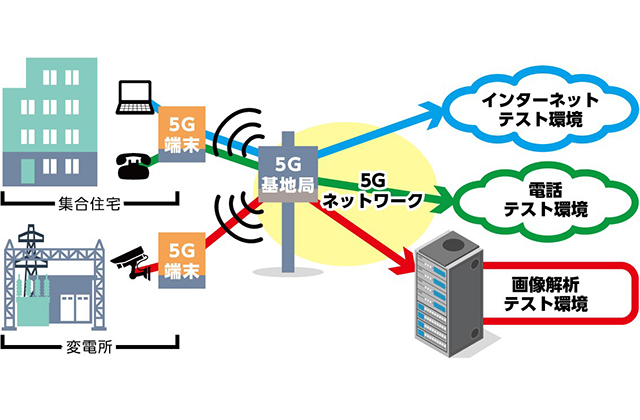加藤真一/エネルギーアンドシステムプランニング副社長
本コラムでは毎回、電気事業制度の振り返りをしているが、前回のコラムから3か月、相変わらず審議会等の動きは活発である。
8~10月でざっと90本近い審議会等が開かれており、エネルギー・環境に関する各分野について幅広く議論が展開されている。夏から秋にかけては、審議の取りまとめや、それに伴うパブリックコメントも多く出されている。例えば、エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画等が閣議決定され、カーボンプライシングは年内の一定の方向性取りまとめに向けた中間整理が、非化石証書取引については、FIT、非FITそれぞれ制度設計の見直しがなされている。
審議会等をみていて、とりわけ多く時間が割かれているのが、今冬及び来年度の電力需給状況を踏まえた対策である。昨冬(21年1月)の発電用LNG燃料の在庫下振れに伴うkWh不足は記憶に新しいが、1年経たずして、再度、厳しい冬が待ち受けることになった。
私の20年ばかりの社会人生活を振り返ると、電力需給の話題が節目で必ず出てくるなと最近よく思い起こすことがあり、少しだけ振り返ってみることとした。
電源調達が厳しかった当初の電力小売部分自由化
私の社会人生活は、20年程前に東京電力に入社したことから始まったが、入社翌年には、電力小売部分自由化として特別高圧分野の小売自由化が開始された。当初は、今のように新規参入が700者を超えるようなことはなく、事業参入した事業者(PPS)は数える程度であった。
大手電力からの離脱は民間企業を中心に行われてきたが、公共施設にも入札という形で切替えが促進されてきた。日本で初めての電力入札は2000年の通産省本省であったが、この時、応札に参加しようとしたPPSの1社が大手電力に部分供給を求め、その価格設定等の条件協議が難航したとの話があった。当時は、卸電力取引所もなく、実需同時同量や託送料金のパンケーキ問題、厳しいインバランス料金設定等、新規参入には厳しいハードルが多く、その中で、販売に十分な電源の調達も非常に難しかった時代であった。今は市場もでき、計画値同時同量で比較的、新規参入がしやすい制度となったが、当時から参入している事業者は創意工夫や努力を重ねて供給力確保や需給運用をしていたのである。
自家発電サービスから見えた課題
入社から3年程経ち、東電が新規事業として設立したオンサイトエネルギーサービスを行う会社に出向となった。電力小売部分自由化で東電は当時の売上の約1割である5,000億円の離脱を想定し、その補完として新規事業に乗り出したのである。いまや、ベンチャー企業やファンド投資、エネルギー事業以外の新規事業を大手電力会社が当然のごとく行っているが、そのルーツは20年程前にあったのである。
このオンサイトエネルギーサービス会社では、ディーゼル発電機やガスエンジン・ガスタービン発電機といった自家発電システムを企業の敷地に設置し、運用まで一括で行う事業を行っていた。設計から設置・電気工事、設備所有、燃料調達、O&M、撤去までの一貫したサービスを初期費用無料、月額サービス料をいただく形で提供しており、いまや自家消費太陽光や蓄電システムで採用されている第三者所有モデルの走りであった。
当時は原油価格が安価で推移しA重油を使ったディーゼル発電機のコストメリットを十分に享受できる状況であったこと、電力会社の季時別メニューの特徴を活かし、昼間は発電機を、夜間は安い系統の電力をハイブリッドで使うことで企業の電力コスト削減が図れることができた。
また、生産ライン等の増強で増設をしたい企業の特高化回避や、落雷や電力系統事故による停電時に製造ラインを停止したくない工場への自立運転機能による電力供給等、自家発電が電力需給に果たす役割は相応に存在感があった。
発電機の設置当初は、よくトラブルで停止し、その都度、電力会社の自家発補給電力を使わせてもらった。電力会社への申請・発電データ提出、お客さま説明等の対応も多くあった。自家発は系統連系しており発電機が止まっても電力は通常どおり供給されるため、お客さまに影響はなかったが、この自家発補給電力を使用した際のペナルティ分は事業者負担となっていたので、かなりの痛手になったことは苦い記憶である。
ちなみに、自家発を設置しているから停電でも大丈夫というわけではなく、自立運転機能等の切替え機能が備わっていない自家発は系統停電時には解列し停止してしまうので、お客さま提案時の説明には留意していた。
以上のような自家発の使い方は日常使いの常用発電機としての役割であるが、短期間に必要な供給力を賄う仮設方式も当時の会社では事業の柱として行っていた。2002年に開催されたサッカーの日韓ワールドカップでは放送用の電源として英国アグレコ社と共同で全国10会場に電源設置・運用を行い、大会を支えた。世界的なビッグイベントであるワールドカップの世界への中継を途切れさせることなく、そのための電力を送り届ける役割である。系統電力の場合、落雷等で瞬低が発生するおそれもあり、そうした影響を受けにくい仮設発電機での対応が、こうした世界的なイベントには多く採用されている。この現場を預かった当時の先輩の話をよく聞くことがあったが、設置から運用・撤去に至るまで、体力的にも精神的にも非常にタフな現場でよい経験になったとの話だった。別の意味での電力の安定供給の姿をみたものである。
この経験を活かし、様々なイベントで仮設電源のレンタルサービスも展開した。スポーツ大会をはじめとしたイベントでは運営に必要な電力がないこともあり電力会社の臨時電力を敷設するケースが多いが、コストや申請の手間等を考えると、仮設電源での供給に分があった現場もあった。この時も常用同様に一括サービスとして提供することでお客さまの手間を極力減らしたことが功を奏したこともあった。
そして、こうした地道な取り組みが活きたのが、2002年に東京電力の原子力発電所の自主点検記録改ざん問題に端を発した原発運転停止による翌2003年夏季の電力需給がひっ迫懸念への対応である。多くの企業から夏の電力供給への心配の声が届き、仮設電源レンタルへの問い合わせが多く入り、複数の企業に仮設電源を設置し、非常時に備える体制を整えた。実際に、2003年夏は冷夏であったことや老朽火力の立ち上げ等で事なきを得たが、電力会社に入社して初めて電気が足りなくなるとの不安を感じた場面でもあった。
この会社は2004年頃からの原油価格高騰の煽りを受け、2006年に事業撤退をすることとなった。この動きは他のオンサイトエネルギーサービス会社も同様で、当時の最大手であったエネサーブ社も事業撤退せざるを得ない状況になった。この際に、問題となったのは、事業撤退とともに、それまで自家発電で賄っていた供給が系統側に戻るということであった。特高回避目的で導入した企業では特高受変電設備の新設が必要になり、電力会社の送配電部門では、幹線の増強や変電所の容量増加等の工事が必要になったところもある。撤退した事業者は電力会社と調整のうえ、一気に自家発停止・撤去するのでなく、順次、行うことで系統側の負荷を軽減するよう協力したものである。今も多くの自家発電が企業に設置・運用されているが、ここ数年でサービス契約が終了する案件も多いと想定され、送配電会社側が停止・撤去はされないと高を括ってしまうと同じような事態に陥る危険性はある。実際に私の知っている企業ではピークカット用で使っていた重油焚きの発電機をこの数年内に撤去することを決定している。
これと前後する形で、今度はガスコージェネレーションが台頭し始めた。ディーゼル発電の総量規制を条例で定める自治体の出現や、環境面への配慮等も背景に、とりわけ都市ガス会社がこの分野でリードし、電力会社が追従する形となった。特に排熱の活用があるため、蒸気や温水・冷水をプロセスで使う工場で多く採用された。発電機は排熱回収ボイラ等との組み合わせにより電力だけでなく熱も供給する存在となった。
上述の通り事業撤退はしたものの、一部のお客さまについては、東電の別の子会社に譲渡し、契約満了まで対応をしてもらうこととした。そこに、引継ぎの役目もあり、出向となったのが2007年。
そして、その7月に新潟中越沖地震があり、柏崎刈羽原子力発電所が停止するに至った。大型電源の停止により周波数が一気に低下し、関東地方で運転していた自家発で一斉に周波数低下のアラートが鳴り、発電機が解列する事象も発生した。
その年の夏は比較的暑く、原発停止により電力需給も厳しさを増し、東京電力は大口顧客に需給調整やピーク調整の契約を発動することもあった。自家発を預かる立場として夏の点検の端境期への移行やトラブルへの細心の注意をしていた矢先、それも8月の最大需要電力発生日に、契約先に設置した発電機がトラブルを起こし、発電機を停止して点検せざるを得ない事態が発生してしまった。当日の関東の電力需給が厳しい中で、お客さまも生産調整をして協力をしてくれた。このように2007年は電力供給に気を使った年になった。
東日本大震災時の話
話はそれから4年経ち、2011年3月11日。東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故、多くの火力発電の損傷が発生した。
会社が復旧や計画停電等の対応をしている中で、海外から仮設電源を提供するとの話が出てきた。そんな矢先、オンサイトエネルギーの子会社で一緒に出向していた火力部門の方から、「仮設電源設置に関するデータや書類がほしい」との依頼がきた。子会社は撤退して清算したが、私が戻った部署でデータを保存したサーバを預かっていた。そのサーバを渡したのだが、なにせ5年以上の会社のデータである。必要なデータを探すのに時間がかかると言うのだ。そこで、色々と社内の伝手を手繰っていたところ、当時のデータを持っている方があらわれた。私は、その方からデータの入ったCD-ROMを借りて、そのデータを火力部門に渡して活用してもらうことになった。その後、火力発電所の敷地内に多くの仮設電源が設置され、一時の供給力として活用された。後で聞いた話だが、そこで活躍したのは、当時、あの子会社に出向して東電に戻ってきたメンバーが多かったとのことだった。大電源を動かすことに長けている人材は電力会社にも多くいるが、緊急時に野戦病院的に対応できる人材は、案外、子会社等に出されて第一線で実務に取り組んだところにいるのだろう。
このように設置された緊急設置電源は一定期間、供給力としての役目を果たし、一部は北海道電力へ移設され、大半は撤去された。東電を辞めた後に移った会社で、他電力が設置した緊急設置電源を常用でコンバインドサイクル化して使えないかとの相談があり、少し関わらせてもらったこともあったが、巡り合わせというものもあるものだと感じたものである。
時は令和となり
それから電力システム改革を経て、時代はカーボンニュートラルへの移りつつある。「S+3E」を大前提に再エネを主力電源として活用し、他の脱炭素電源と組み合わせてエネルギーミックスの目標が立てられた。
その間には、2018年の北海道胆振東部地震による道内ブラックアウトや、大型台風による関東での停電長期化等、最近は、激しさを増す自然災害への対応が必然的となっている。
そして、2021年1月には発電用LNGの在庫下振れによりLNG火力を燃料制約で出力低下せざるを得なくなり、kWhが不足するという事態が発生した。卸電力取引所への売り札が減り、新電力をはじめとして小売電気事業者は供給力確保義務のもと、高値の札を出してまでして市場買いを行った結果、市場価格は高騰、連動しているインバランス料金も上昇するという結果を招いた。
こうした反省を教訓に、今後の電力需給については短期、中長期で対策を検討し、一部の施策は既に実行し始めている。それでも休廃止予定の電源は多く、今年の冬、来年の夏・冬も供給予備率が厳しい状況であるとの見通しが発表されている。
電気事業制度を毎月追っていると、多くの議論が並行して行われており、そのスピードに付いていくだけでも大変な状況である。次から次への新たな課題が出てくる中で、「柔軟に見直し」や「ファインチューニング」「不断の見直し」といった言葉が躍ることが多い。
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではなく、まずは足元で緊急的に止血をしつつ、並行して恒久的な予防・治療対策をと議論し、一体何が最適な電力システムなのか、今一度、しっかり見直していくことが重要だろう。
【プロフィール】1999年東京電力入社。オンサイト発電サービス会社に出向、事業立ち上げ期から撤退まで経験。出向後は同社事業開発部にて新事業会社や投資先管理、新規事業開発支援等に従事。その後、丸紅でメガソーラーの開発・運営、風力発電のための送配電網整備実証を、ソフトバンクで電力小売事業における電源調達・卸売や制度調査等を行い、2019年1月より現職。現在は、企業の脱炭素化・エネルギー利用に関するコンサルティングや新電力向けの制度情報配信サービス(制度Tracker)、動画配信(エネinチャンネル)を手掛けている。