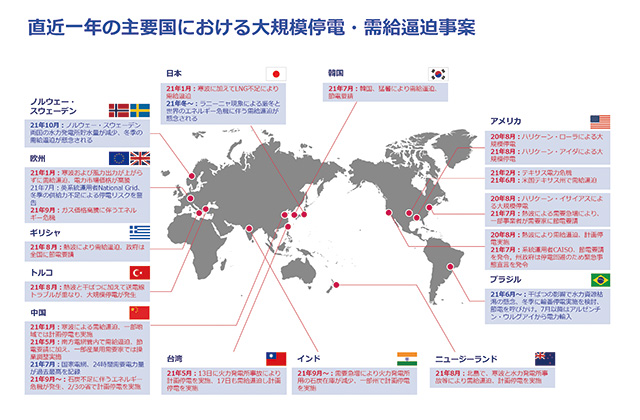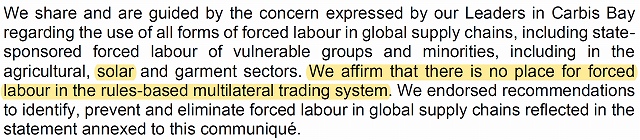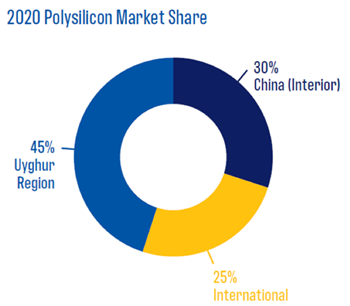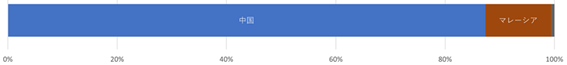COMSのモデルは? 『日本沈没』の裏事情
「わが国は地球物理学の権威、世良教授のもと、50年にCO2排出量を実質ゼロにする目標を掲げ、本格的な取り組みを進めてきた。それが『COMS』だ。9000mの海底岩盤の隙間に存在する、CO2を出さないエネルギー物質『セルステック』を、パイプを通して抽出するシステムが稼働した。セルステックの埋蔵量は日本のCO2排出量の120年分といわれ、これによりCO2排出量は飛躍的に抑えられることになる」
これはTBS系日曜劇場『日本沈没 希望のひと』の初回冒頭のシーンだ。俳優の中村トオルさん演じる東山首相が世界環境会議の場で、新エネルギーシステム『COMS』を発表、世界の温暖化対策をリードする決意の表明からドラマがスタートする。
1973年に刊行された小松左京氏の同名小説を、21年版にアレンジ。原作では日本沈没の口火を切った伊豆諸島の小島の沈没を自然現象として描いているが、ドラマではCOMSの稼働が海底プレートを刺激し、関東沈没を誘発していくストーリーに仕立てている。
COMSはもちろん架空のエネルギーシステムだが、業界関係者から見ると、どことなくメタンハイドレートやCCS(CO2の回収・貯留)を彷彿とさせる設定になっている。そんな中、エネルギー関係者X氏から興味深い話を聞いた。以前、某エネルギー団体に制作会社側から「CCSを題材にしたドラマを作りたいので詳しく教えてほしい」との問い合わせがあったというのだ。
つまり当初は、プレート崩壊の原因としてCCSを想定していたらしい。確かに、18年9月に発生した北海道胆振東部地震を巡っては、震源地近隣でのCCS実証が影響したのではないかと報じたメディアがあった。結局、CCSのイメージを大きく損ねると判断されたのだろうか。この案は見送られ、COMSに取って代わったようだ。
肝心のドラマは初回視聴率が15・8%(ビデオリサーチ調べ)と上々の滑り出し。霞が関を舞台に繰り広げられる官僚と政治家の駆け引きなど見どころ満載で、今後の展開から目が離せない。
小泉前大臣に寄せ書き 環境記者が異例の対応
菅政権の退陣に伴い、小泉進次郎氏が約2年間務めた環境相の任から外れた。この間、石炭火力輸出方針の見直し、原子力政策への言及、再エネ規制緩和、2030年46%減目標、カーボンプライシングなどを巡る発言の数々が大きく注目されてきた小泉氏。小泉氏が環境省を去るのと同時に、同省の記者会から退会する記者も多かったそうで、メディアの注目度の高さを物語っている。
そんな小泉氏は最後の閣議後会見でこの間の歩みを振り返った際、自身の成果を語った後、記者との思い出話に触れた。特に専門紙のベテラン記者であるK氏(K紙)とS氏(E誌)の名前をたびたび口にし、「環境省の今までの歴史をずっと見てきた方々から鍛えられて始まった、あの2年前の会見を忘れることはできない」「温かくこの2年間で鍛えていただいた、育てていただいたという思い」などと感謝を述べた。
さらに新大臣へのアドバイスを問われた際にも「K氏とS氏の話をよく聞いた方がよいと思う」と強調した。記者サイドも、小泉氏に寄せ書きを贈るなど異例の対応で2年間の重責を労った。
なお、小泉氏は「今後も立場を超えて環境行政に継続的に取り組んでいきたい」とも語っている。今後、どのような発言をしていくのか、引き続き注目したい。

太陽光に「反社」の影 FIT制度を悪用か
全国的な問題として広がりを見せている、山間部などでの太陽光発電所の乱開発。今夏も日本各地で、台風や豪雨の影響で太陽光パネルが損壊するなどの被害が相次いだ。のべつまくなしの開発の結果、日本の美しい里山が次々と破壊されていく様子は、目を覆うばかりだ。また自然災害の誘発は地域住民の生命をも脅かし始めている。
こうした中、反社会的勢力が太陽光開発に群がっている実態が、取材を通じて浮かび上がってきた。例えば、全国でメガソーラー事業を展開しているA社を巡っては、かねてから地元とのトラブルが頻発している。
「住民説明会がおざなりだったり、工事がずさんだったり、法令違反を犯したりと、とにかく問題だらけ」。乱開発問題に詳しいZ氏は、語気を強めてこう話す。「いろいろと調べていくうちに、A社の幹部が反社組織とつながりのある可能性が浮かび上がってきた。地元議員ら政治家との関係も深い。全国から寄せられる情報を踏まえると、こうした事例は氷山の一角だ」
もちろん太陽光事業者の多くは真っ当な企業である。温暖化防止に貢献するため、地域に根差したインフラビジネスを展開している。その一方で、参入障壁の低いFIT制度を悪用し、環境破壊もいとわず金儲けを企んでいる企業があるのも事実だ。
「サラ金やマルチ商法などでしのぎをやっていた連中が、太陽光ビジネスに目を付けた。国は傍観せず、早いとこ手を打たないと、取り返しのつかない事態になりかねない」。元警察関係者のQ氏は、こう警鐘を鳴らしている。