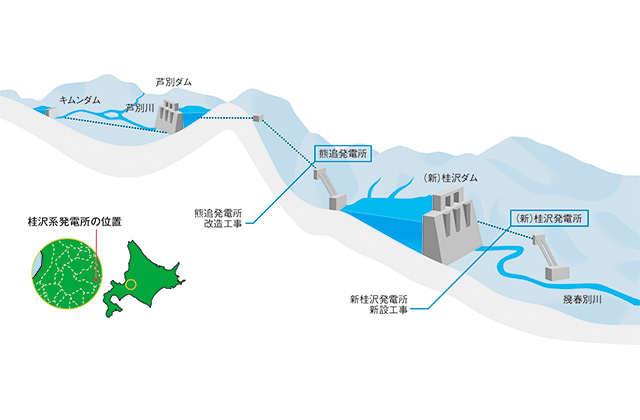テーマ:エネルギー環境予算と税制
2022年度予算要求のエネルギー・環境関連では「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」(再エネ交付金)や、税制改正要望に盛り込まれたカーボンプライシング(CP)が注目されている。業界関係者の見解はどうか。
〈出席者〉 A電力 B都市ガス C石油
―今回の目玉の一つが、環境省の再エネ交付金だ。地域脱炭素ロードマップの具体化に向け、200億円もの予算を要求している。
A 地域密着型の事業に対し交付金が有効活用されることに期待しているが、環境省には、真に脱炭素化に資する制度化を求めたい。そのために事業の選定過程で必要なのは、費用対効果で評価することだ。
太陽光発電の拡大は重要だが、非現実的なエネルギー基本計画の目標ありきで太陽光の導入量だけを追求すべきではない。30年温暖化ガス46%減にこだわりすぎると、逆に脱炭素化が遠のきかねない。CO2排出量全体に占める電力の割合は4割にも満たず、電力の供給側の対策が貢献するのはごく一部だ。脱炭素化には需要側の電化が必須で、住宅なら30年、ビルは50~100年ほどストックするから建て替えのタイミングで電化を進める必要がある。交付金では、高効率ヒートポンプや、ZEB・ZEH(ネットゼロエネルギービル・ハウス)といった需要側の対策とセットで、中長期的に脱炭素にどれだけ寄与するかを評価軸としてほしい。交付金以外でも全ての政策に同じ評価軸を導入すべきだ。
B 都市ガス業界も再エネ交付金の新設に期待しているし、環境省幹部からも業界への期待をよく聞く。ただ、対象事業について問うと、漠然とした答えが返ってくる。運用が分かりにくいと結局バラマキとなり、先進地域で事例が少し出てきて終了、となりかねない。ロードマップでは100カ所での導入を目標にしているのだから、実行性が出るような運用にすべきだ。既存の類似の補助金とのすみ分けも明確にしてほしい。中堅都市には必ず都市ガス事業者がいて、常日ごろ自治体から相談事が寄せられている。
ただ、両者とも何をすべきかピンときていない。そして現状、都市ガス事業者の貢献も限定的だ。再生可能エネルギーやEVなど複合的な提案力を身に付ける必要があり、地方事業者の支援や人材育成が急務となっている。
C 石油の場合、元売り会社は全国区だが、地域ではSS(サービスステーション)が電力や食品、介護などさまざまなビジネスを展開している。地域特性は十把一絡げではなく、ゼロカーボンシティの担い手はやはり地元に根差した企業がふさわしい。そのためのエネルギー供給と需要側への対応というセットで考えると、SSの役割も期待でき、彼らの知見を活用してほしい。ただ、SSの取り組みとしては運輸部門からEVやFCVという発想になりがちだが、台数が少なく、課金ビジネスとして自立できない。太陽光発電事業への参入も同様で、SSの売り上げの9割は燃料油であり、これが地域の実態だ。地域で自立したビジネスが育てられるかが大切で、まずは環境省のお手並みを拝見したい。正直200億円程度では大した役に立たず、気合を入れなければモデル事業止まりだろう。

太陽光偏重でバランス欠く トランジション対策も軽視
―交付金以外の環境省事業はどうか。
B これまでも指摘されてきたが、気候変動関連補助金の経済産業省と環境省のすみ分けがさらに分かりにくくなってきた。国策として取り組む以上、役割分担の明示化か、事業の統合を進めるべきだ。ほかには、サーキュラーエコノミー関連でエアコンのサブスクリプション(定額制利用)事業も、予算規模は小さいが目の付け所が良い。給湯器などに展開させても面白そうだ。
C 石油関係ではトランジション(移行期)の対応が重要であり、その点はすみ分けはできていると思う。ただし、環境省にトランジション的な事業があまりなく、経産省と連携してもっと充実化を図ってほしい。46%減目標に関しては化石燃料対策をやらざるを得ない。電源構成の8割を占める化石燃料に関する議論こそ必要なのに、注目が低すぎる。予算のバランスの悪さにもそれが見て取れる。
A その通りで、目玉事業は太陽光ばかりだ。太陽光事業者はFIT(固定価格買い取り制度)初期に大もうけし、今回の予算はFITの代わりの補助の仕組みをつくるからなんとかパネルを設置せよ、というように見えるが、お金のかけ方が間違っている。恩恵はほぼ中国に行き、グリーンリカバリーには全く寄与しない。全てエネ基のゆがみのせいであり、「小泉環境相が数字を積ませたのだから環境省が責任を取れ」という経産省の思惑もありそうだ。しかし長期スパンなら水素やSMR(小型モジュール炉)などにもっと予算をつけるべき。今後経産省に期待したい。