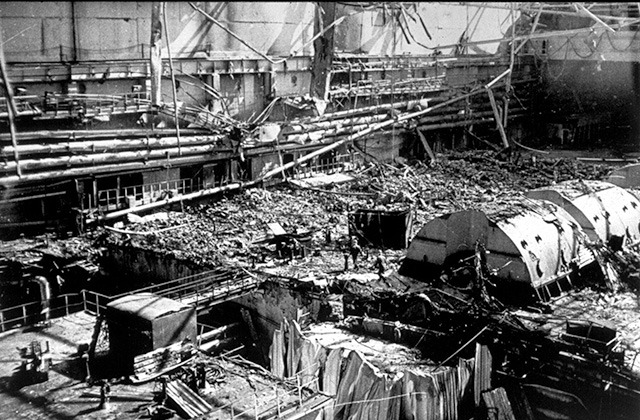4人の候補が論戦を繰り広げた自民党総裁選。その裏ではさまざまな駆け引きがあった。
環境重視に大きく振れた菅政権に対し、果たして新政権下ではどんな政策が予想されるのか。
菅義偉首相の電撃辞任に端を発した自民党総裁選挙は、群雄割拠の4人による大混戦の様相を見せた。菅政権ではエネルギー政策、とかく原子力政策の前進を期待する向きもあったが、予想に反した尻すぼみに終わった。電力会社にとって最後のとりでとも言える原発の推進が宙に浮く形になったのは大きな落胆を生んだ。今号が出る頃には新総裁が選出されているが、果たして新首相は原発政策を推し進めることができるか。
総裁選の告示日前日の9月16日、エネルギー界隈がざわついた。岸田文雄候補の推薦人名簿に経済産業大臣の「梶山弘志」の名前があったからだ。当初官房長官への打診を受けるほど菅首相に近しいとされてきた梶山氏が、菅首相が支援する河野太郎候補ではなく、しかも最も対立する陣営の推薦人に名を連ねたことは、大きな驚きを持って受け止められた。
告示と重なった17日、閣議後会見で岸田氏の推薦人になったことを問われた梶山氏は「私の手法としては対話の窓口はずっと開いて、業界各社ともいろんな話を聞く機会を設けてきた。そうした対話を重ねる姿勢が見える方を応援したいという点で、岸田氏の推薦者になった」と理由を説明した。
梶山氏の真意を自民党関係者はこう解説する。「この1年はっきりいってコケにされてきた。水面下で丁寧に粘り強く交渉を重ねてきて、いざ固まったという場面で横やりを入れられたことは一度や二度じゃない。相当腹に据えかねてたということでしょう」。梶山氏はわざわざ菅首相のもとに出向き「今回は岸田氏を支援します」と報告に行ったという。菅一派とは完全にたもとを分かったのだ。
菅一派―。それは総裁選に立候補した河野太郎氏、そして河野氏を支援する小泉進次郎氏の神奈川人脈を指す。第六次エネルギー基本計画をめぐり、この二人が何かと言いがかりをつけてきたのだ。
「原発は22%『まで』と明記しろ」、「再エネは38%『以上』としろ」。有識者会議を経てパブコメにかけているにもかかわらず、河野、小泉の両氏は経産省を攻め続けた。河野氏が経産省幹部をいじめた話が週刊文春に大々的に報じられたのは記憶に新しい。

河野氏らしい変節ぶり 岸田氏との違いが鮮明に
総裁選に立候補する前、反原発の河野氏は威勢良く「核燃サイクルは廃止。原発の新増設もできない」と持論を展開した。しかし立候補が現実味を帯びると急に「安全が確認された原発を再稼働していくのが現実的だ」と急降下。いかにも彼らしい「変節」ぶりだ。
総裁選で得意のエネルギー政策、脱原発を争点化し、党員票を掘り起こそうとした河野氏のもくろみについて、ある政府関係者は「菅首相も含めて共通するのはセンセーショナルなことを打ち出して一時的に注目を集めるが、警戒感を持たれるとすぐに方針転換する。このパターンが定着して信頼を無くしていることが見えない。彼は菅首相の劣化コピー」と解説する。
むしろ高市早苗氏、野田聖子氏の出馬で河野氏の票は目減りするばかりだ。その焦りからか、情勢を見て寝返る議員に対し「選挙での応援は一切しない」(政府筋)と脅しをかけたという。河野氏の選挙対策本部で先頭に立つ小泉氏が「水面下で強烈な引きはがしをしている」と派閥を批判していたが、「自分らのことを棚に上げてよく言うよ」(自民若手議員)と不評を買う始末だ。
どうやらエネルギー業界が戦々恐々としていた河野首相の誕生は夢と化しそう。100代目の首相に就任するのは岸田氏になりそうだ。岸田氏のエネルギー政策についてはいま一つつかめない。ただ河野氏が核燃サイクル廃止を宣言すると、すぐさま「核燃サイクルは維持」と公言するなど、都合良く持論を押しつける河野氏とは真逆の考えを持つようだ。しかも総裁選中、岸田氏が常に言い続けてきたのは「対話を大事にする」ということだ。冒頭の梶山氏の政治手法と重なり合う。菅政権下で強引な手法に振り回された人たちにとっては福音といえるだろう。
岸田政権に高まる期待 菅政権の負の遺産を修正
そして岸田氏には強烈なブレーンが存在する。経産官僚で前首相秘書官の今井尚哉氏だ。連続在任期間が最長の安倍政権を支えてきたその辣腕ぶりはエネルギー業界でも定評がある。いま一つ自信なさげな様子だった岸田氏が、テレビや討論会に出て堂々としている姿は「今井氏のアドバイスのおかげ」(永田町関係者)というのがもっぱらだ。
今井氏が就いているとすれば、背後には安倍晋三元首相がいる可能性も。岸田氏が総裁選出馬表明をした前日の8月25日。衆院第一議員会館の自室に、安倍元首相に近いNHKの岩田明子氏を招き入れた。政策についての意見交換をしたというのが表向きだが、永田町界隈では「安倍氏の支援意向を岩田氏が伝達したのではないか」との臆測を呼んだ。
いずれにせよ、安倍政権時に活躍したアクターが岸田氏を下支えしているのだ。さらに推薦人には山際大志郎氏、高木毅氏と原発推進派が名を連ねた。岸田政権のエネルギー政策は安倍政権時に戻ることを示唆している。となれば、エネ基の閣議決定が先送りになる可能性も出てきた。特に原発を巡る記述はパブコメを受けて修正される公算が大きい。経産省内では「11月のCOP(気候変動枠組み条約会議)に間に合わなくてもいい」という見方も出ている。
国際的な名声のために性急な気候変動対策を採る裏で、エネルギー政策をないがしろにしてきた菅政権時の混迷が去ることは間違いない。岸田氏はエネルギー業界などさまざまな業界と対話し、日本特有の事情を理解することになるだろう。脱炭素というまやかしに惑わされず、エネルギーの安定供給と気候変動対策を両立する政策を打ち立てるに違いない。
ただ、それは岸田氏が政権維持のため、一部の国民の人気取りに走るという愚を犯さなければの話である。