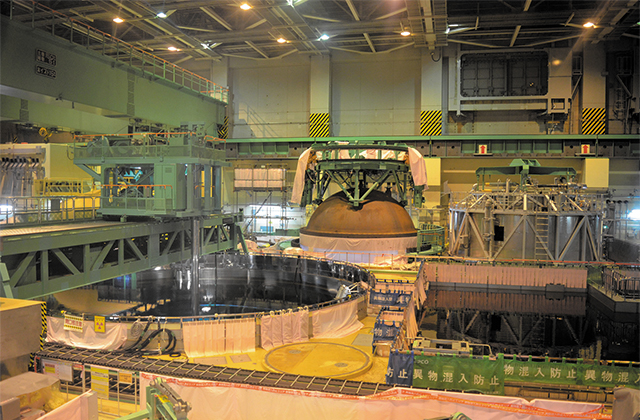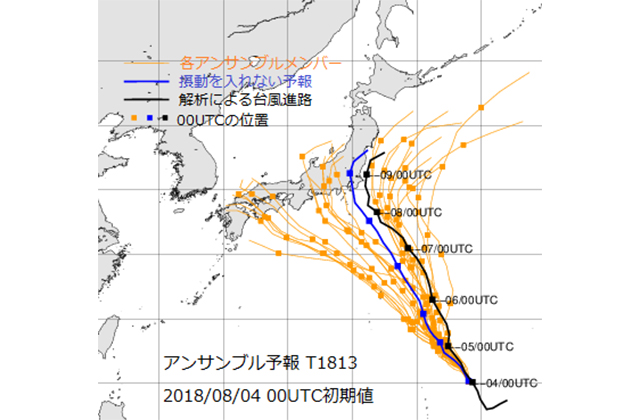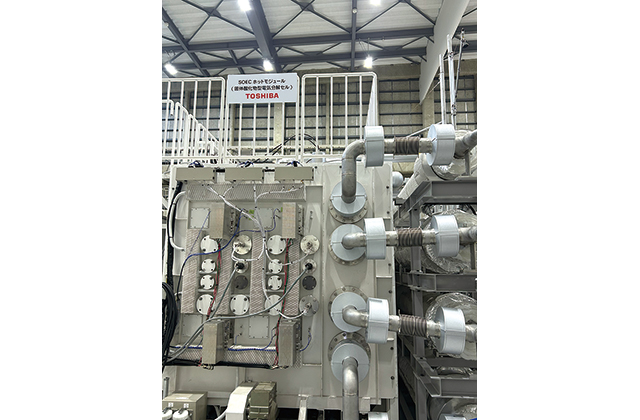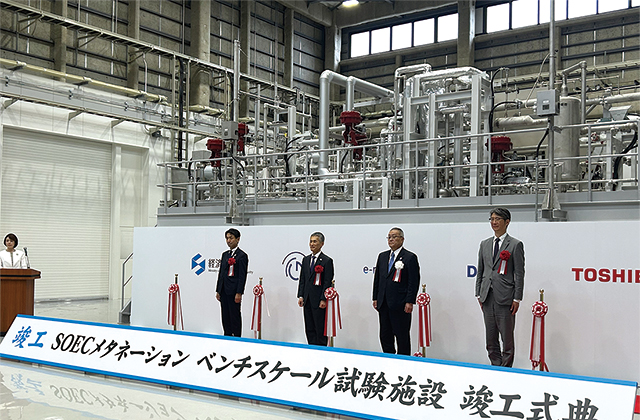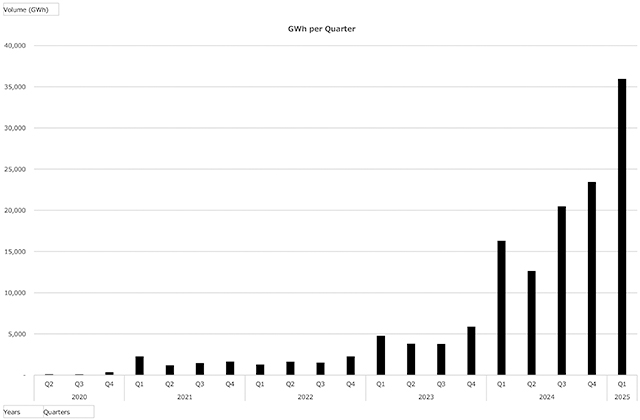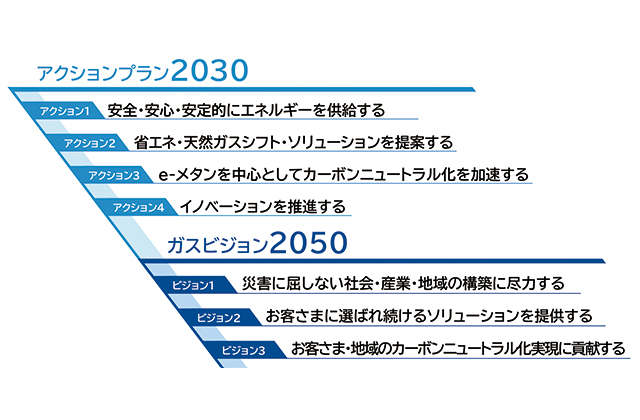テーマ:2040年に向けた再エネ政策
政府が本腰を入れるFIT(固定価格買い取り)からFIP(市場連動買い取り)への転換や太陽光の集約化などは、狙い通りの成果を挙げられるのか。また、各社厳しい局面を迎える洋上風力政策へのテコ入れが、引き続き重要な検討課題となっている。
〈出席者〉 A 再エネ事業者 B 再エネ業界関係者 C コンサル
―再生可能エネルギーの市場統合や国民負担の軽減に向け政府はFIP転を促進するが、実際どう受け止めているのか。
A 政府の狙いは理解しているものの、実際は簡単ではない。FIPではプレミアム収入の予見性が低く、特に大型のプロジェクトファイナンスではレンダーとの交渉で難しい面がある。一方、アップサイドのチャンスも。詳細は後述するが、バランシングコストの支援があることに加え、併設蓄電池による収益向上、また好条件なPPA(電力購入契約)を獲得できれば、FITのままより収益が上がる可能性がある。
B 難易度は発電所の規模に左右される。大規模なら蓄電池併設でもペイするが、小規模は簡単ではない。小規模は事業規律などの課題が残る領域でもあり、問題が濃くなっていくことが懸念される。地上設置の低圧をいつまで増やすのか、そろそろ考えるべきかもしれない。また、国民負担が減るというけれど、蓄電池によるタイムシフトのプレミアムが大きくなる可能性もあり、ネットでみて逆のインパクトをもたらす展開もあり得る。
C やはり制度的に分かりづらい面がある。参照価格(市場取引などにより期待される収入)などの情報を事業者は使いこなせているのか、オペレーションに資する仕組みかというと疑問が残る。実際、FIP転をした電源は、FIT・FIPの3%程度に過ぎない。

インセンティブが不十分 不良アセットを集約しきれるか
―今春始めた「長期安定適格太陽光発電事業者認定制度」では、一定規模の事業集約を進めようとしている。
B 認定制度の目的をどこに置くかが重要になる。今の仕組みがインセンティブになるのかというと疑問だ。元々太陽光は、JPEA(太陽光発電協会)がカバーしているアセットの割合が小さく、業界での規律確保の体制に課題があった。その観点から、例えば新電力が小規模太陽光などを保有・管理するというのは、規律の面からも新電力の事業面からも効果的であり、環境省の脱炭素先行地域とも方向性が合致する。ただ、本制度は結局発電事業者に寄せる形へ。さらに審議会では「不良なアセットも集約させていくべき」との意見が出ていたが、必要な収益性が確保できなければ受け入れる事業者は株主に説明できない。そのためのインセンティブがなければクリームスキミングが起き、やはり残されたアセットの課題が濃くなるのではないか。
C 2012年から5年間の事業用太陽光の認定量は2900万kW程度で、これが退出すれば電力システムのバランスが崩れてしまうし、蓄電池が収益を確保する見込みがなくなってしまう。長期電源化は進めるべきで、今ある設備を卒FITとして残すことは重要だ。しかし、認定制度で売却希望者情報が3カ月早く見られる程度では、インセンティブといえない。また、特高から低圧までコミットできる事業者は限られ、特に低圧は忌避されがちだ。申し込みサイトが立ち上がり2カ月経つ中、そろそろ進捗を示してほしい。
A 引き取ろうと思える低圧はごく一部で、その下のボリュームゾーンは投資や補強が必要となる可能性が高い。また、適格事業者にはいつまでにどの程度の規模を引き受けるのか、義務ではないものの、目標を中計などに掲げ進捗をウェブ上で公表するよう求められる。例えば、追加投資などが必要な案件を需要家がPPAで高く評価する仕組みなど、再エネを減らさず使い続けることの社会的価値を示せなければ、この制度は機能しないのではないか。また、資源エネルギー庁は再エネの悪いイメージを変えるべくあえて厳しい規律を設けている。当然事業者も努力すべきだが、加えて政府には原発で行っているように、再エネでも人々の不安に向き合いイメージを払拭するような取り組みに注力してほしい。