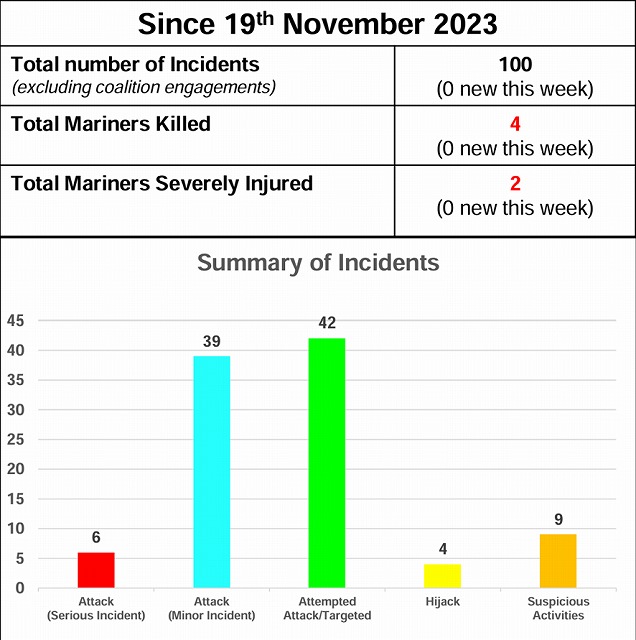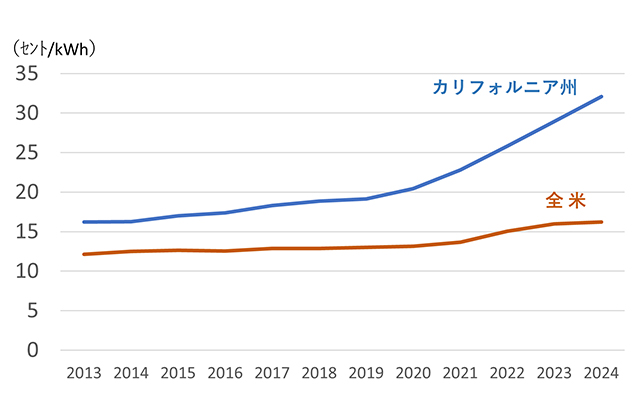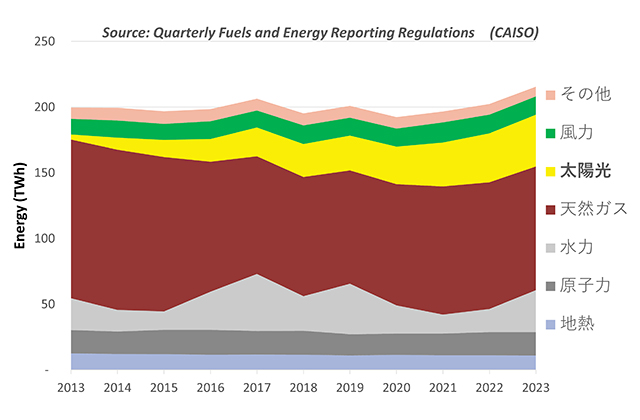NEWS 01:バイオ燃料を営業列車に搭載 鉄道業界が脱炭素で本命探し
カーボンニュートラルの実現に向け、鉄道業界が脱炭素車両の選択肢を広げている。JR西日本は9月、バイオ燃料を100%用いた営業列車の長期走行試験を開始。JR各社からは、水素を動力源とする次世代車両の導入を目指す計画も浮上した。エネルギー関連企業と連携しながら、技術開発や供給網づくりを進める機運が高まりそうだ。
バイオディーゼル燃料使用の列車
JR西が主に山口県内を走る岩徳線の一部列車に導入したのは、廃食油などを原料に製造された次世代バイオディーゼル燃料。フィンランドの再生燃料大手ネステが製造し、伊藤忠エネクスが供給を担う。2025年1月末までの走行試験でエンジンなどの車両性能に影響がないことを確かめ、25年度以降の本格導入を目指す。
背景には、架線のない非電化区間を走る既存ディーゼル車両を環境に優しい車両に置き換える要請がある。その一環で、蓄電池で走る電車を採用する動きが一部で進んでいるが、1回の充電で走行できる距離が限られる上、割高な車両価格がハードルとなっていた。対照的にバイオ燃料は既存車両や給油関連施設がそのまま使えるため、普及する可能性を秘めている。
JR東日本は30年を目標に水素と酸素で電気をつくる燃料電池と蓄電池を併用するハイブリッド車両の実用化を狙う。中長期の視野で脱炭素車両の本命を探す動きが活発化しそうだ。
NEWS 02:供出義務化巡り波紋 調整力の市場調達に疑問符
需給調整市場における応札不足の常態化を解消する手立ての一つとして、発電事業者に供出を義務化する議論が浮上し電力業界に波紋を広げている。
電力広域的運営推進機関(広域機関)は9月10日の有識者会合で、供出義務化を求める制度的措置を講じる上で必要な論点の整理に着手した。5月10日の資源エネルギー庁の審議会で応札不足への対応策の基本的な考え方の一つとして、同措置が示されたことを受けたものだ。
これにより、発電事業者による出し惜しみをなくし高単価応札を排除することで、膨れ上がる送配電事業者による調整力の調達コストを抑制する狙い。一方で、義務に見合った確実な費用回収が見込めない限り、発電側の運営に与える影響はあまりにも大きい。
「慎重な検討が必要」との意見もあることから、広域機関は「あくまでも予備的な検討であり、実施の要否に関わる検討ではない」とのスタンスだが、電力業界関係者の一人は、「議論するからには規定路線なのだろう」と見る。
今年度、同市場で予定されていた全ての商品区分の取引が始まったが、募集量と応札量の乖離が顕著。2026年度には、現行では1週間前に取り引きされている一次~三次①が前日取引に移行することが決まっているが、それまでは調達未達が継続しかねず、エネ庁としても苦肉の策とも言える。
とはいえ、そもそもこの問題の背景には、大手電力の発電部門に対し限界費用ベースの価格規律を押し付けていることがある。「制度的な欠陥があるにもかかわらず、〝供出義務化〟というさらなる規律を押し付けようとしている。〝市場機能の活用〟とは一体なんなのか」(コンサルタント)
NEWS 03:HPと燃焼技術がコラボ 競合メーカーの連携加速
「大手電力・ガス会社が描くエネルギー供給構造の大きなグランドデザインに則って、メーカー各社は技術開発を進め、機器を製造・販売してきた」。ある空調メーカー関係者はこれまでのビジネスモデルの側面をこう話す。しかし、全面自由化時代の到来やカーボンニュートラル(CN)の動向は、そんなビジネス様式を大きく変えようとしている。
「三浦工業によるコベルコ・コンプレッサの株式取得」「ダイキンと三浦工業による資本業務提携」「パナソニックとヤンマーが分散型エネルギー事業で協業」「パナソニック、ヤンマー両社がGHPの開発製造に関する合弁会社設立へ」「独ボッシュが日立グループの空調企業を買収」―。
燃焼技術やヒートポンプ(HP)技術を培ってきたメーカー各社に限った近年の動向をみると、従来では考えられないような動きが顕在化しつつある。いわば競合同士のコラボだ。前出各社の動きを要約すると、「HP技術を取り込むボイラー企業」「HP・燃焼機器のアライアンス」「ライバル企業間連携」「日本のHP技術を手に入れる独企業」―といった形だ。
電力、ガス各陣営の結束が崩れていく中、「指南役」を失ったメーカー各社が荒波を乗り越えるため生き残りへの戦略にかじを切ったことは間違いないが、その動向から見えてくることがある。それは、CNへの道筋を多角的に捉えているという点だ。HP技術は再エネ電力を有効活用することに他ならない。片や燃焼技術を維持し、深堀りすることでメタネーションや水素社会の到来に備える。
旧来の業界の垣根を乗り越えたメーカー間のアライアンスが、どのような形で新たなエネルギー利用技術を生み出していくのか、注目される。
NEWS 04:26年度にETS本格稼働 制度の論点整理に着手
2026年度から排出量取引制度(ETS)が本格稼働する。方向性について、岸田文雄首相は今年1月の施政方針演説で「大企業の参加義務化や個社の削減目標の認証制度の創設を視野に法定化を進めていく」と述べていた。その議論が9月3日に始まった。
政府は「GX実現に向けたカーボンプライシング(CP)専門ワーキンググループ」で検討を進め、来年の国会でGX推進法の改正を行う予定だ。今WGでETSの具体的なルールが決まるのではなく、その前段階での論点整理を目的とする。
実証・試行を経てETSが本格稼働へ
現在ETSは試行段階。「GXリーグ」では目標設定や達成に関しては自主的な取り組みとしている。一方、本格稼働の段階では参加率向上や規制色を強める方針で、対象者の定め方や目標設定の在り方、目標達成に向けた規律強化などについて議論を深める。例えば対象に関しては、省エネ法などと平仄を合わせ、年間エネルギ―使用量(原油換算)1500㎘以上がラインとなる可能性がある。
同日は日本鉄鋼連盟、石油連盟、電気事業連合会などに聞き取りを実施。電事連はトランジションへの考慮や、事業・投資の予見性確保が重要だと強調。さらに電化の推進と整合的なCPの水準などの設計や、GXに伴う負担への理解醸成を求めた。
価格水準など望ましいCPは業界によって千差万別。政府はどう議論を収れんさせるのか。