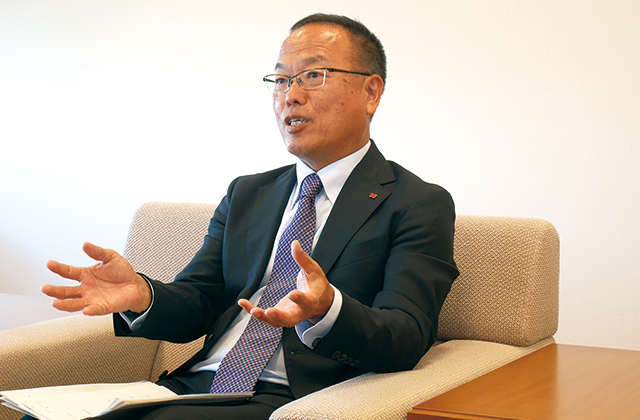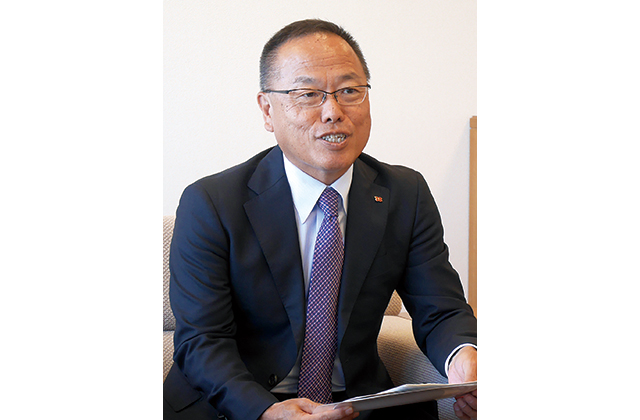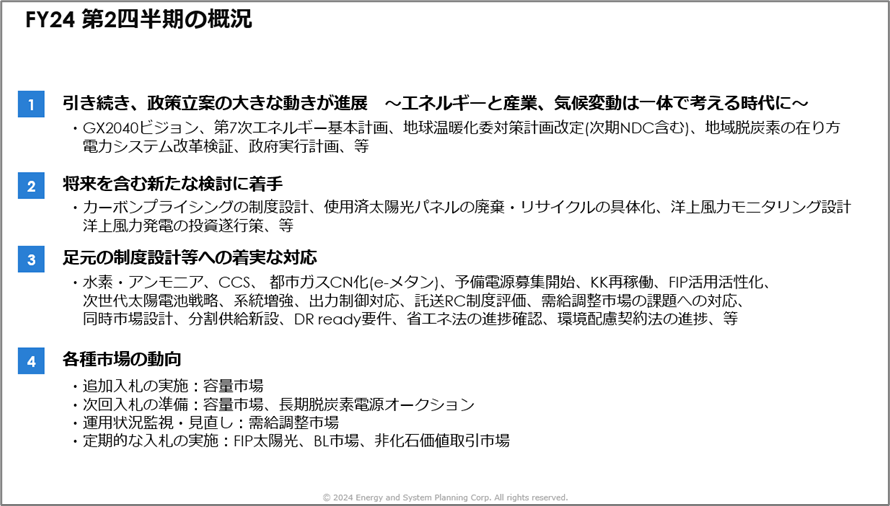SMR導入を検討するエストニアでは、国民が原子力の必要性を実感する電気料金制度があった。
わが国で新増設を実現するには、国民理解の一層の醸成と適切なリスク計画に基づく規制の導入が必要だ。
岡本孝司/東京大学大学院教授
先日、エストニアを訪問する機会を得た。バルト三国の一つで、古都タリンの街並みは世界遺産にも登録されており、中世の面影を残しカラフルな建物や石畳の路地が目に付く。IT先進国としても有名だ。
エストニアで改めて感じたのは、脱炭素に向かう欧州の強い意志と、原子力の必要性である。欧州においては、安定供給とのバランスの観点から天然ガス火力と水力、原子力が主力である。これに太陽光と風力が変動電源として乗ってくる。そうした中で、原子力に対する国民理解を醸成する上での鍵を握るのが、電気料金との関係性であるという視点に着目してみた。

エストニアでは、電気料金単価が1時間ごとに変わるプランがあり、国民の多くが利用している。翌日の電気料金が、前日の午後3時に発表される。その電気料金を見ながら、エコキュートの沸き上げ時間や電気自動車(EV)の充電スケジュールを調整する。例えば8月のある日の電気代は、1kW時当たり0・08ユーロ(約13円、1ユーロ=160円換算)がベースで、朝は0・15ユーロ(24円)、夕方は0・25ユーロ(40円)だった。なお日本と同様の固定価格のプランも選べるが、相対的には高くなるため変動型を契約する人が多いそうだ。
エストニアは人口100万人の小国だが、エネルギーの自給率はおよそ9割で、残りは輸入に頼っており、そのうち9割をフィンランドが占めている。フィンランドでは、豊かな資源を活用した水力発電所と原子力発電所が動いている。原子力については昨年4月にオルキルオト3号機が運転を開始し、年間国内総発電量の約15%を占める。また化石燃料への依存度が低いため、化石依存度が5割強と高いエストニアよりも電気料金は格段に安い。産業が動いていない深夜時間帯はおおむね0ユーロ。人々が活動を始める朝は少し値上がりし、午前9時に0・016ユーロ(約2・5円)の最大値をとる。それでも日本に比べればかなり安い料金だ。
エストニア国民の多くは、毎日スマートフォンを使って電気料金の安い時間帯を調べるなど、節約を考えているという。そこでフィンランドの電気料金の安さに気づき、その理由が原子力であることを理解するようになったようだ。エストニアはかつてロシアからの輸入に依存していたものの、エネルギー安全保障の強化を図ってきた。こうした流れの中で現在、国内初となる原子力発電所として小型モジュール炉(SMR)の導入を柱に建設の検討が進められているが、原子力への国民理解があってのことだ。
需給を価格で整える 価格の東西差がより明確に
さて、日本の電気料金単価は固定価格である。関西電力の時間帯別料金であるハピeタイムRは、1kW時当たり深夜15・37円、朝夕22・80円、昼(夏)28・87円である。東京電力エナジーパートナーで同じような時間帯別料金である電化上手は、深夜28・85円、朝夕35・87円、昼(夏)43・93円となる。原子力の動いている関電は東電のほぼ半額であることが分かる。
そこで日本でも、エストニアのように1時間ごとの変動価格オプションを導入してはどうだろうか。現在、ほとんどの家庭にスマートメーターが導入され、電力消費量をリアルタイムで計測している。短時間の変動価格を導入するためのハードはそろっているのだ。市場価格のデータをもとにマージンを乗せれば、小売事業者が1時間ごとの電気料金を設定するのは難しくない。翌日が雨であれば電気料金は高く、晴れであれば安くなる。こうして需給を価格でバランスできるようになる。

以前は毎月郵便ポストに電気の検針票が入っていたが、今はウェブサイトで確認する人がほとんどだ。毎日の電気料金が変動し、スマホで毎日チェックするようになると、エストニアのように国民が電気料金の仕組みや特性に気づくのではないだろうか。消費者はエストニア国民のように毎日の電気代とにらめっこし始めるので、料金の高低が直接見えてくる。原子力発電所が稼働している関西は安く、動いていない関東が高いことが極めてシンプルに分かるだろう。省エネ促進にも極めて有効である。