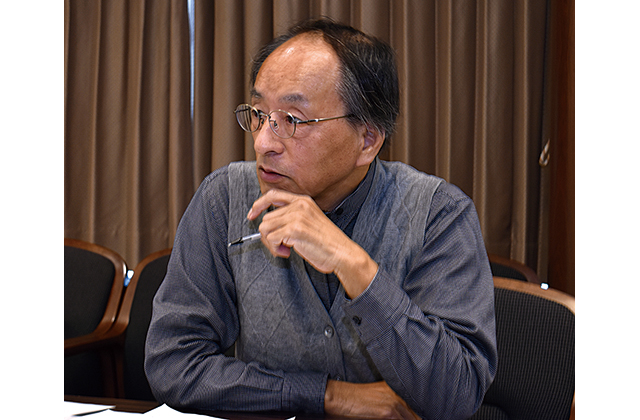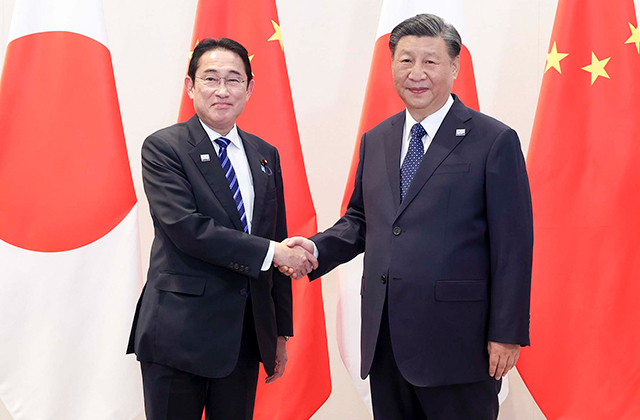【エネファームパートナーズ/「エネファーム」が累計販売台数50万台突破】
エネファーム普及推進協議体(エネファームパートナーズ)は1月、家庭用燃料電池「エネファーム」の累計販売台数が50万台を突破したと発表した。エネファームは、都市ガスやLPガスから取り出した水素と空気中の酸素の化学反応で発電する燃料電池システム。発電と同時に排熱を給湯などに利用することで、省エネ・省CO2に寄与する。2009年にPEFC方式、11年にSOFCタイプが販売開始となり、マンション設置機種、停電時発電機能搭載機種などのラインアップ拡充が図られてきた。近年は、数千台のエネファームを遠隔制御し、系統電力に対する調整力の供出や系統需給状況に応じた制御の確立に向けたVPP実証への参画など技術確認の取り組みも実施している。
【JERA/横須賀火力発電所2号機が営業運転開始】
JERAはこのほど、子会社のJERAパワー横須賀合同会社を通じて進めてきた横須賀火力発電所2号機のリプレース工事を終え、営業運転を開始した。これにより、2019年8月から取り組んできた同発電所1、2号機のリプレースが完了した。同発電所2号機は、超々臨界圧発電方式(USC)を採用した高効率な石炭火力発電所で、発電出力は65万kWに上る。安定した供給力として電力需給に寄与すると同社では考えている。なお、営業運転の開始日は23年度の冬季重負荷期の供給力として貢献するため、当初予定していた24年2月から前倒しした。JERAは、引き続き、最新鋭の火力発電所へのリプレース工事を進め、電力の安定供給とCO2排出量の削減に努めていく構えだ。
【商船三井/海運で世界初となるブルーボンドを発行】
商船三井は国内市場において、公募形式によるブルーボンドを発行した。海運業界として世界初。調達資金の使途を、海洋汚染の防止や持続可能な海洋資源に関連する事業などに限定して発行する債券で、100億円規模の予定だ。策定したブルーボンドフレームワークは、資金使途が持続可能な海洋経済に貢献し、環境改善効果が期待される点が評価され、日本格付研究所から最上位評価の「Blue1(F)」を取得した。資金使途の候補例は、洋上風力発電関連事業や海洋温度差発電に係る設備投資、同社開発の次世代帆船「ウインドチャレンジャー」や、開発中のゼロエミッション船「ウインドハンター」など。同社は環境課題解決への投資額を2023~25年度で6500億円規模としている。
【Looop/市場連動型プランのアプリがグッドデザイン賞受賞】
Looopの電力小売事業「Looopでんき」の市場連動型プラン「スマートタイムONE」と、そのスマートフォンアプリが2023年度のグッドデザイン賞を受賞した。同プランでは、市場価格が高い時間帯から安い時間帯へ電力使用をシフトさせるピークシフトを推奨。そのピークシフトを直感的に実践できるアプリのデザインが評価された。電気を使う時間帯の工夫で、電気代の節約を実現し再エネを有効活用していく。
【NTTファシリティーズ/無停電電源装置の販売 安定した給電を実現】
NTTファシリティーズは12月21日、サーバールーム向け無停電装置「FU―T3シリーズ(30~100kVA)」の販売を開始した。整流器とインバーターを通して電力を供給する、常時インバーター給電方式を採用。停電、瞬断、電圧低下、波形乱れなどの入力電源異常が起きても、無瞬断でバッテリー運転に切り替え、負荷設備に常に安定した給電が可能だ。また電力変換効率が前シリーズの92%から94%に向上したことで、運用時の電気使用量を削減し、ランニングコストとCO2の低減に貢献する。
【ノーリツ/水素100%で燃焼 家庭用給湯器を開発】
ノーリツは水素100%を燃料とし、安全に安定した出湯が可能な家庭用給湯器を開発した。現行の家庭用給湯器と同等の最大能力24号、最小能力2.4号に対応し、変わらない快適性を実現。また導入時のインフラを考慮し、ガスから水素への仕様変更も可能としている。同社は水素をはじめとするエネルギーの変化に対応しながら、安全に安定したお湯の提供を使命としている。CO2を排出する機器の中で大きな割合を占める家庭用給湯器を水素100%燃焼に対応させることで、脱炭素社会の実現に貢献する。
【大成建設/既築自社ビルのZEB化で見学会】
大成建設は、省エネと創エネ技術を導入してリニューアルZEB化した同社横浜支店ビル(築50年)で見学会を行った。外装・壁面の発電システムやBEMSによる高度環境制御などを取り入れており、中規模オフィスに最適なZEB化技術を紹介。家具や照明に神奈川県産木材を取り入れるなど、地産地消で地元の産業・環境にも寄与する。今回のZEB化で、CO2削減量は年間150t、光熱費は同700万円を削減した。同社は今後も既築建物のZEB化の取り組みで脱炭素を進めていく。
【中部電力ほか/AI活用の水力運用 最適計画の策定支援】
中部電力とツナグ社、コミュニティアナリティクス社の3社はAIを活用して水力発電所の最適な発電計画を策定する支援システムを共同で開発し、特許を出願した。中部電は既存電源の増電に取り組んでいる。本システムではダムへの流水量予測や気象の類似条件における過去との比較、売電価格の最大化など目的に合わせて発電する計画を支援する。
【住友電気工業/業界で最小最軽量 家庭用蓄電池を発売】
住友電気工業はこのほど、家庭用蓄電システム「POWER DEPO V」の販売を開始した。同製品は小型・軽量を生かした屋内への設置に加え、太陽光発電システムが未設置でも使用可能なため、マンションなどの集合住宅でも使用できる。また、鉛電池の代替としてバックアップ電源用途でも使用可能だ。この他、本体の保証期間を10年から15年に延長した。
【IHI/専・混焼可能なボイラー トヨタ九州で試験開始】
IHIのグループ会社であるIHI汎用ボイラ社は、都市ガス専焼モードと水素混焼モードを備えた産業用小型水素混焼ボイラーを開発した。水素燃料は体積比60%(熱量比30%)が上限で、盤面の操作だけでモードを切り替えられる。水素燃料の調達計画に応じてボイラーを稼働できるため、ラインを止めずに熱源供給が可能だ。トヨタ自動車九州宮田工場内に発生蒸気量750kgの試験機を設置し、工場敷地で生成した水素を燃料とする運用評価試験を始めており、2024年度の販売開始を目指して開発を進めている。
【静岡ガス/静岡ガス&パワー富士発電所ガスエンジン発電設備2基増設】
静岡ガスのグループ会社で、電力事業を展開する静岡ガス&パワーは、同社が運営する静岡ガス&パワー富士発電所(静岡県富士市)において、ガスエンジン発電設備2基(最大出力合計1万5600kW)を増設し、昨年11月末から稼働を開始した。今回の増設工事は、静岡ガスグループの静岡ガス・エンジニアリングが元請けとなり、川崎重工業製カワサキグリーンガスエンジン「KG―18―T」(発電効率クラス世界最高:51.0%)を2基設置、12月に発電所が完工した。発電した電力は「SHIZGASでんき」として地域(8.9万件)に販売される。同社では電力調達における自社発電出力が2倍に向上し、電力の安定供給、調達コストの低減化・平準化が可能となる。