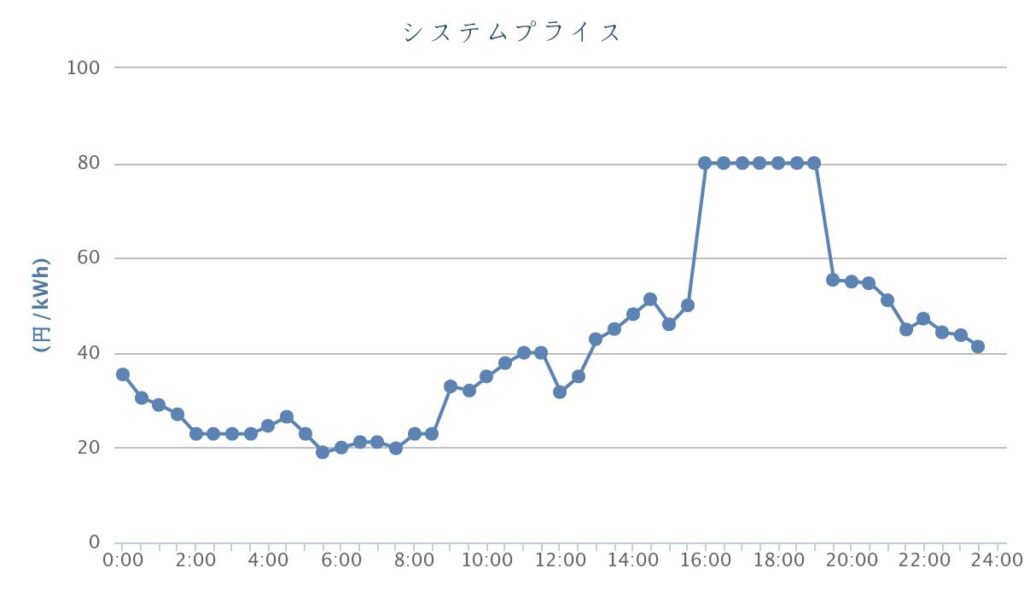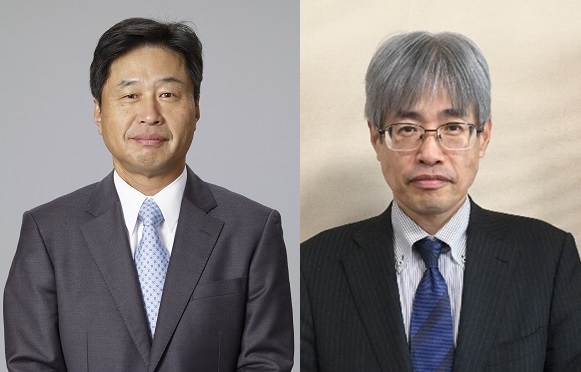JR東海の葛西名誉会長が5月に亡くなった。国鉄改革とJ Rの再生に活躍した。最近はリニア、高速鉄道、それに関連して日本のエネルギー問題に関心を寄せていた。ご冥福を祈りたい。
筆者は、電力・電機メーカーの技術者や研究機関、学者などのOBで構成する日本原子力シニアネットワーク連絡会が2014年におこなった会議に参加し、また仕事の関係で、葛西氏と懇談する機会があった。
ある懇談の際に、ドイツの作家シュテファン・ツヴァイクの伝記『ジョセフ・フーシェ』の話を聞いた。葛西氏はその本について書評を書いていた。フーシェはフランス革命の際に、警察部門のトップになり、その権力を使ってナポレオンの帝政時代、体制の変わった王制時代の途中まで地位を維持し続けたが最後に失脚し、現代に至るまで批判される人物で。落ち着いた口調で、「フーシェは、自分のために権力を使いました。力は人によって善にも悪にもなる。私は1民間企業や社会にほんの少し影響力を出せる程度ですが、自分の行為がどのように社会に影響し後世に残るか、その影響が良きものであるか、常に考えています」と話した。葛西氏には剛腕の評価があるが、一見すると物静かで教養あり、人間的に練れた人との印象を受けた。
その2014年8月の講演を思い出して、記してみよう。
◆電力の経営危機は当然の帰結
葛西氏は当時の講演で、まず電力会社の経営を分析した。「企業経営のポイントは財務諸表から見える。今の電力会社は支出の4~5割が燃料費、そして次に設備費だ。燃料費の負担は原発を停止して、火力発電を焚きますために非合理に増えている。原子力規制委員会の対応の遅れ、政治の不作為で行政手続きが曖昧で、再稼動ができない。電力会社は一番のコスト要因が取り除けず、経営で手の打ちようがない」。
さらに経済への影響を述べた。「このまま出血が続き企業体力を消耗するジリ貧では、電力会社の経営が危険になる。電力価格は転嫁されて消費者が苦しみ、日本経済をむしばむ。日本は現在、原発停止の代替燃料として年間4兆円程度、中東からLNG(液化天然ガス)を焚きまし分として多く購入している。原子力の長期停止は国益を損ない、日本経済、そしてアベノミクスを失速させかねない」。
その上で「高品質で安定的かつ低価格でエネルギーを利用できることが、経済活動の土台になる。日本は無資源国という宿命を持つ。経済の悪影響が深刻になるまで、残された時間はあまりない」として、原子力政策、エネルギー政策で、当時の安倍政権が原発再稼動、電力自由化の検証、そして正常化のために早急な決断をすることが必要と強調した。
ただし、さすがの葛西氏でも見通しが外れた。14年末ごろから米国のシェール革命の影響が出て、ガスとオイルが市場に供給されて化石資源価格が下落。14年初頭に当時1バレル100ドル以上だった石油価格が、15年に30ドル台へ急落した。日本の表面上の好景気は維持され、原子力とエネルギーの問題は、自民党政権によって先送りされた。
ところが22年、世界的なエネルギー価格の高騰とインフレで、日本経済の先行きが懸念される。そして原子力発電所の再稼働は進まない。電力会社の経営危機も葛西氏の懸念が、現実になりつつある。
◆民主党のポピュリズムの悪影響
葛西氏は、民主党政権とそのエネルギー政策について批判した。「政治家が自分の意見を持たず、他人の意見ばかり聞き、ポピュリズム(大衆迎合主義)に陥ることが多かった。エネルギー・原発問題で悪しき側面が出た」。
その上で、当時の菅直人政権の政策の失敗を4点あげた。①福島事故に際して、初動時点で適切な広報をせず、放射能への過度な恐怖感を広げてしまった、②原発を無計画に止めた、③東京電力に事故での無限責任を負わせた、④その結果、除染や賠償で東電に負担させればよいという無規律な状況が生まれた――。
その後の安部政権に対し、葛西氏は「民主党の失敗を早急に是正するべきだ」と訴えている。しかし、現実は民主党の政策をほぼ継続し、福島に資金を注ぎ込む政策を継続してしまった。福島の復興は進んだ面があるものの、それが合理的で、適切であったかは、見方によって異なるだろう。
◆信頼回復には何が必要か
葛西氏は、原子力関係者に「福島事故からの信頼回復のためには、関係者は反省を深め、安全確保のための努力を重ねてほしい」と注文をつけた。そして「主張には大義名分、つまり『正当性』が常に必要になる。自らの主張にそれがあるか常に考えてほしい」と自省をうながした。過去の国鉄の大事故では、安全を向上させて適切に列車を動かすことで、失墜した信頼を少しずつ回復できたという。
福島原発事故の後で、関係者の間には、原発への反感からの批判を怖れて原子力問題での意見表明を自粛してしまう雰囲気がある。葛西氏は日本的な『空気』に萎縮してしまうことに理解を示した上で、「一般の人々に対し、原子力を活用しない場合の問題、特に負担増などの問題が起こることを示すことが必要ではないか。それぞれの持ち場で一人ひとりが責任を果たすリーダーシップを取ってほしい。非日常の状況では、リーダーシップがなければ、物事も組織も動かない。使命感を持ってエネルギー・原子力を再生してほしい」と、期待を述べた。
◆葛西氏の残したメッセージを噛み締める
「改革に大義があり、状況が熟せば水か高いところから低いところに流れるように、状況が自然と動くことがある。ただし、おかしな方向に転がることもある。その結末に最新の注意を払ってほしい」と、葛西氏は締めくくった。
原子力への逆風の中であっても、財界、そして企業の要職にありながら、社会への憂いから、おかしいことには「おかしい」と正論を述べる葛西氏の態度は、大変参考になった。
葛西氏の講演から8年。筆者はエネルギー業界の末席につらなるが、エネルギー・原子力を巡る状況は悪化しているように思われる。葛西氏の懸念が現実になりつつある。それに良い影響を与えられない自分の力のなさにも、歯痒さを感じる毎日だ。
電力関係者に、今の苦境を打ち破る、葛西氏のようなリーダーはいるのだろうかと考えてしまう。そして自分も含め、もう一度、葛西氏の考えを思い出し、自分の仕事を見直したい。