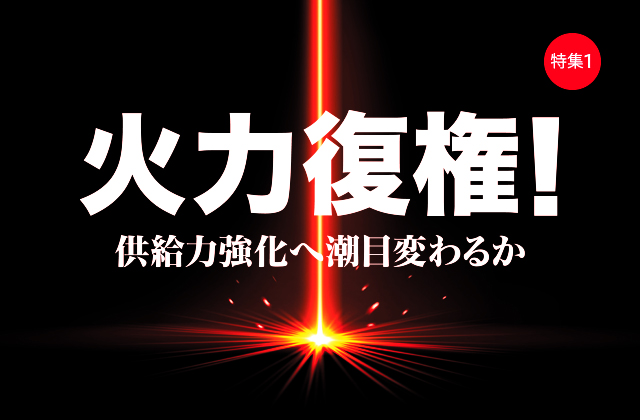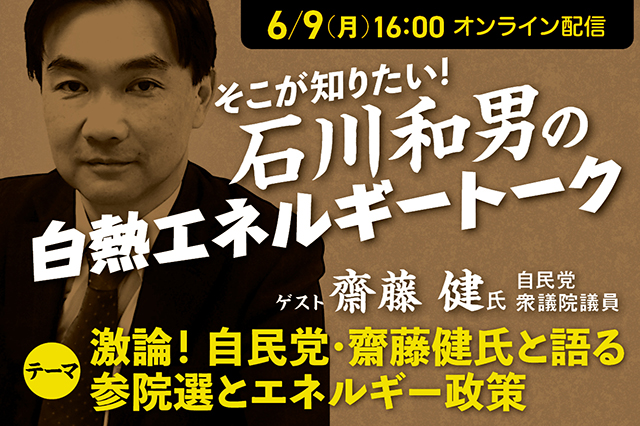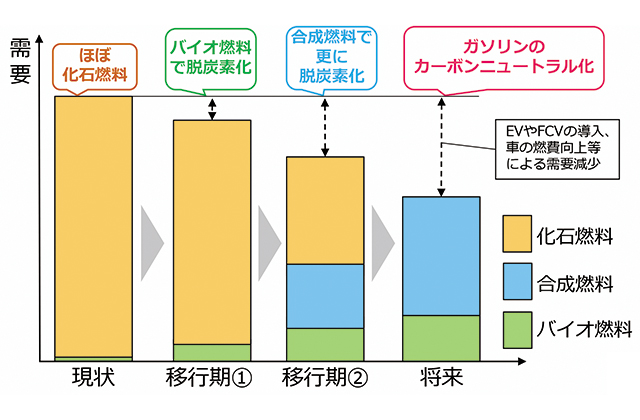地方のエネルギー事業が承継難の渦中にある中、LPガスではM&Aの動きが目立ってきた。
その実態を探りつつ、都市ガスやSSを含めた地域インフラの将来像を、識者3人が語る。
【出席者】角田憲司(エネルギー事業コンサルタント中小企業診断士)、橘川武郎(国際大学学長)、中原駿男(スピカコンサルティング代表取締役)
 左から中原氏、橘川氏、角田氏
左から中原氏、橘川氏、角田氏
―自由化や脱炭素、人口減少などを背景に、エネルギーの需給構造が大きく変わる中で、地方の生活基幹エネルギーと言えるLPガス業界ではM&A案件が増えている印象があります。その実態を教えてください。
中原 もともとLPガス業界では商圏の売買が一般的でしたが、最近では株式譲渡によるM&Aが増えてきました。売り手が株式譲渡を選択する理由の一つが、法人格が残ることです。創業家からすれば社名や屋号を残せることは大きな魅力ですし、従業員にとっても就業環境の変化が少なく安心感があります。需要家に契約変更の手間をかけないことからも、事業承継を円滑に進めることができます。
橘川 さらに言えば、業界特有の四つの要因がM&Aを後押ししていると考えられます。一つ目は、需要の減少や後継者の不在、人手不足などを解消する最良な選択肢であることです。二つ目は、エネルギー業界の中でも粗利が高い構造にあることです。シェールガス革命を契機に米国で副産物として生産されるシェールLPガスの輸出が拡大し、サウジアラムコが主導してきたCP(コンタクトプライス)による価格決定の構造が崩れました。それに伴い、輸入価格や卸売り価格は大幅に低下しましたが、日本国内の小売価格はそれに連動して下がらなかった。つまり、小売段階で粗利が生じる構造であり、M&Aの買い手にとっての魅力になっています。三つ目は、大手LPガス事業者による顧客獲得戦略の変化です。一部大手は取引適正化の流れを受けて、かつての「過大な営業行為」に代わってM&Aを重視する動きを見せています。経済産業省は、過大な営業行為に厳しい態度を示す半面、M&Aについては歓迎する姿勢を取っています。これが四つ目の要因です。
角田 昨今の情報開示に対する社会的な要請の高まりで、かつて水面下で行われていたM&Aが可視化された面もあるのでは。
中原 その通りです。件数自体も増えていますが、公開される案件が増えたことが実態だと思います。例えば、当社が仲介の依頼を受けたエネサンス北海道が和光商会に出資した案件では、買い手のエネサンス側が積極的に情報を公表しました。きっかけは和光商会から「エネサンスを候補に考えたいが、株式譲渡での買収事例を聞いたことがなく難しいのではないか」と相談を受けたことです。エネサンスに話すと「M&Aの経験は豊富にあり、もちろん対応可能だ」と即答でした。業界では株式譲渡が一般的ではなく事業者が慎重な傾向にあると伝えると「それなら積極的に開示していこう」と、非上場企業ではあるもののプレスリリースを出すことになりました。
時代が変えた事業承継の価値観 レモンガス買収で浮き彫りに
―SMBCキャピタル・パートナーズがアクアクララレモンガスホールディングスを買収したことは業界関係者にとって驚きでした。
橘川 独立志向が強い会社であるだけに、今回の買収はやや衝撃的でした。業界内では日本瓦斯と親しい企業として知られていますが、同社が主導するプロジェクト「夢の絆・川崎」(川崎市)には加わりませんでした。こうした過去の姿勢を振り返ると、単なる身売りというよりも、プライベートエクイティ(PE)ファンドを活用しながら再生や発展を目指している可能性もあると注目しています。
中原 PEファンドは2000年初期から増えはじめ多くの業界でM&Aを手掛けてきましたが、LPガス業界では全く事例がありませんでした。関心がないわけではなく、むしろ当社への業界についての問い合わせは多かったくらいです。ですが、営業権1件に対して評価額が付く上にその水準が高く、長期的に利益を出し続けるイメージが湧かなかったのでしょう。そうした中でSMBCCPによるレモンガス買収で、ようやくこの業界に風穴が開いたという印象です。ファンドによる買収は、事業承継や成長戦略の有力な選択肢になります。加えて、複数の卸売り事業者と取引している場合、特定の卸売りに売却してしまうと他との関係が悪化するリスクがあります。そうした懸念を払しょくするためにも、ファンドは有力な選択肢になります。
角田 創業家の赤津裕次郎前社長はなぜ、パートナーを求めたのでしょう。経営的に困窮しているわけではなく、むしろ優良企業です。
中原 理由の一つは後継者問題です。今は息子に継がせることが唯一の選択という時代ではなくなりました。また、市場が縮小傾向にあるため、単独での打開は難しいとの判断もあったのでしょう。代々続いた家業であるため、身内で引き継ぎたいという思いはあっても時代は変わりました。さまざまな選択肢を天秤にかけた上で選択したと見ています。
―LPガスとは状況が全く違うのがサービスステーション(SS)です。事業承継が難しく、SS過疎地問題が深刻化しています。
角田 政府は長年、SS過疎地対策を行っていますが歯止めはかかっていません。22年度末時点の国内SSは2万8000カ所弱で、この10年で7000カ所近く減少しました。過疎地SSの地上タンク設置を認めるなど大胆な規制緩和策も講じていますが設備を更新する余裕すらない事業者が多いのが現実です。
橘川 この問題に拍車をかけているのが大型量販店コストコの存在です。昨年、滋賀県に1店舗進出したことで県全体のSS需要の1割が流れたと言います。残念ながら業界と行政は現時点で反論できるロジックを持っていません。とはいえこの環境下で残っている事業者はそれなりに経営体力があるはずですが。
中原 SS事業で利益を出している会社は少なくありません。ただし、M&Aの視点で言うと、買い手を探すのが長期戦になる。瞬間的に儲かっているとはいっても将来「負ののれん」になってしまうとの懸念が強くあり、買収判断のハードルを高くしています。
角田 長野県が3月に立ち上げたガソリン価格の適正化に向けた検討会の中で、会合に参加した王滝村の村長が、「SSがなければ観光需要にも応えられない」と危機感を示していました。SS過疎地問題はもはや、地域住民だけのものではありません。
 人手不足は配送業務に直結する
人手不足は配送業務に直結する