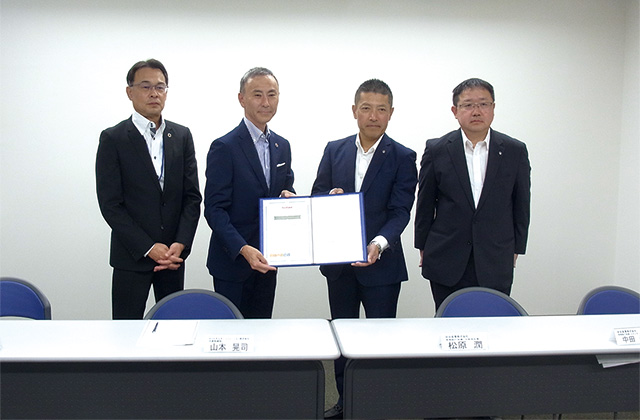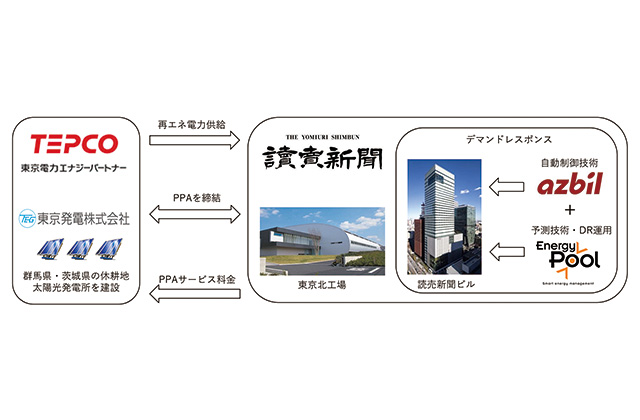【東京ガスエンジニアリングソリューションズ】
JR鹿児島中央駅直結の「アミュプラザ鹿児島」は、JR鹿児島シティが運営する県内有数の複合商業施設だ。九州新幹線の部分開業に合わせた2004年のオープンから時が経ち、カーボンニュートラル対応など施設運営を巡る環境は大きく変化。当初からコージェネレーションなどは導入済みだが、一次エネルギー消費量がベンチマークを超えており、23年度にコージェネと排温水投入型吸収冷温水機(ジェネリンク)を更新。東京ガスエンジニアリングソリューションズ(TGES)がエネルギーサービス(ES)事業者となり、遠隔自動制御システムの「ヘリオネットアドバンス」も導入し、運用改善に取り組んだ。
年間約1000㎘、約18%の一次エネルギー削減目標に対し、23年度実績で1542㎘、27・0%もの削減を達成。CO2削減効果は27・9%で、ランニングコストも圧縮した。TGESは「最適なES設備の導入に加えて、基本的な運用改善対策を、需要家(JR鹿児島シティ)、設備管理者(JR九州エンジニアリング)との3人4脚で着実に実施することで大きな効果が生まれた」(栗原英明・営業技術ソリューション部副部長)と強調する。
ES設備では、コージェネは電熱負荷を精査しスケールダウンする一方、ジェネリンクは熱源運用の自由度向上による省エネを目指し容量アップ。コージェネは遠隔自動制御により熱負荷やデマンドレスポンス指令に合わせた最適運用を行い、再エネ出力制御が頻発する中間期には発電を抑制した。排温水は冷房需要が高まる夏季でも、熱変換効率の高い給湯・暖房にて優先利用する制御を試行錯誤し、実現した。
運用改善では、ES対象外の空調や搬送設備についても、基本的な取り組みを徹底。具体的には、①冷水温度の引き上げ、②外気取入量の適正化、③ポンプ制御の最適化―などだ。
JR鹿児島シティは「室内環境は悪化することなく1年目から数値で成果が見えたことはありがたい。加えて、管理者との間でエネルギー使用に関する話をする文化も醸成できた」(後藤浩義・設備運営課次長)と、さらなる省エネや設備更新に意欲を見せる。
需要家、管理者、ES事業者がそれぞれの立場で積極的に省エネに取り組むことが大きな成果につながっている。この成功事例の横展開ができれば、日本全体の一層の省エネにつながりそうだ。