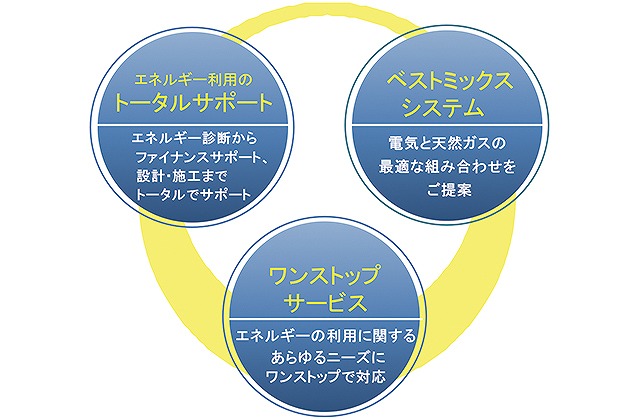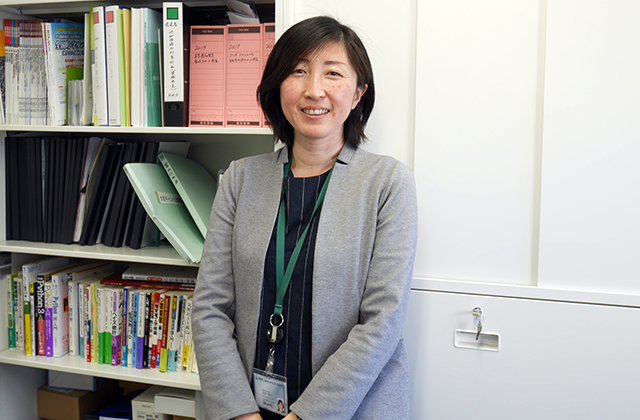<出席者>電力・ガス・石油・マスコミ/4名
大手電力の一連の不祥事問題は収まるどころか拡大する一方だ。
電力システム改革10年の節目に、業界は最大のピンチを迎えるのか。
―大手電力の一連の不祥事問題は全く収まる気配がない。むしろ次々に新たな事実が発覚している。
石油 石油業界は電力より早く再編が進み、かつて不正問題でもエネルギー業界内で真っ先に突き上げられた。翻って今、電力は四面楚歌だろう。談合は許されない時代に変わり、特に厳しく追及している読売の記事には記者の怒りを感じる。ただ他紙からは、エネルギー危機ほどの熱量は感じない。
―一連の不祥事が電力業界最大のピンチとなるかもしれない。
ガス というか、自らまいた種だ。電力システム改革第一弾の施行から10年という節目にうみが出た。総括原価時代から見直さなければならなかったことが、経営全体で徹底できていなかった。閲覧した情報を営業に使ったと指摘されたのは今のところ関西電力だけだが、今後他社でも発覚する可能性がある。ただ、強力なライバルが存在しない地方電力がなぜ不正閲覧をしたのかについては、クエスチョンが残る。
石油 システム改革のうみについて、有識者のコメントを用いてビシッと指摘するような記事を期待しているが、これまで政策議論に関わってきた有識者が自らの意見を否定することは難しいのだろう。
電力 電力のコンプライアンスが徹底されてこなかったことは問題だ。他方で自由化以降、大手電力の体力を削るような政策が次々実施され、燃料高騰局面では電気を売れば売るほど赤字でも耐えてきたと言う側面もある。ようやく規制料金値上げを各社が申請したものの、持続的に電気事業を営んでいくために必要な設備投資を行えるような環境整備が必要だ。この点について、政府には不祥事問題とは別の議論として進めて欲しい。
問題の余波どこまで エネ業界全体にも影響か
石油 一方、電力の規制料金値上げ申請に関する公聴会が各地で開催されているが、四国電力の公聴会では意見陳述人がゼロだったね。消費者にとって値上げは腹立たしいはずだが、新聞の投書欄でも批判する内容は意外と見当たらない。
ガス 地域間の電気料金格差を指摘する記事も出てきた。ほかの公共料金と比べて、これまで電力の内外価格差はほぼなかったが、今後は差が拡大していく。一般紙も、電力会社ごとの個別事情を踏まえた分析記事をもっと書くべきだ。
マスコミ 東京電力ホールディングス(HD)にメガバンクが4000億円の緊急融資を実施する件だが、昨年からHDはエナジーパートナー(EP)の増資を計5000億円を引き受けたのだから、この対応は当たり前。EPの経営問題とHDの資金繰りの話について、日経などは冷静に報じるべきだろう。いずれにせよ各電力の資金繰り問題が今後表に出てくる。業界でくくらずに各社の状況を掘り下げることが重要で、中でも東電の経営計画に注目している。
―電力の不祥事問題は、今後どのような展開が予想されるだろうか。エネルギー業界全体への波及もあり得るか。
石油 依然、エネルギー危機は続いている。東洋経済の特集は力が入っていて、国内外のさまざまな著名人にインタビュー。その中でサハリン2の停止リスクとガス危機長期化に警鐘を鳴らす記事がある。そんな状況下で今後、ガスにまで不正問題の影響が飛び火してしまうと、安定供給上のリスクが高まってしまうのではないか。
ガス 電力の不祥事問題の解明は途中経過で、不正閲覧の規模がどこまで広がるか。また中部電力と東邦ガスのカルテル問題も年度が明ければ表に出てくる。ガス業界も無関係ではいられない。
マスコミ 与党議員からはエネ庁にシステム改革の非を認めるよう迫る声も出始めた。電力・ガス事業部長はこれまで電気事業連合会の社長会に出ていたが、カルテル問題発覚後は出席しないようになった。また、アンバンドリングが徹底できていないことや、不祥事があっても電気事業法上の業務改善命令発出しかできないなど、さまざまな問題が表面化した。これらをまとめて検証する場が今後設定されるだろうが、いずれにせよ電力有利の改革とはならなそうだ。
ガス そこで問われるのが業界紙の立ち位置。業界のことを一番知っている。電気新聞の報道は業界に遠慮しすぎ。起きていることについては、忖度せず客観的に報じる姿勢が必要だろう。
―電気新聞にせよガスエネルギー新聞にせよ「プラウダ」や「人民日報」になってはいけないな。小誌も自戒しないと……。
高浜4号の緊急停止 PWR稼働への影響は
―ところで1月末、原子炉格納容器外で中性子の急減を検出したとして、高浜4号が自動停止した。政府の原子力政策のてこ入れに水を差さなければよいが。
電力 関電が原子力規制委員会に今回の理由を報告した後、規制委がどう対応するかによる。悪い言い方をしようと思えばいくらでもできる。現規制委員長らは以前のメンバーほど変な物言いはしない印象だが、どう出るかな。
マスコミ 情報があまり出てこなかったので、メディアも書きにくかった。今後については、規制委は基本横展開させるので、対応が決まった暁にはPWR(加圧水型炉)全てで実施するだろう。下手をすればPが一斉に停止する事態もあり得るよ。
電力 関電は福井県の使用済み核燃料の県外搬出問題も抱えている。今年中にけりをつけなければ、美浜3号、高浜1、2号が停止する。6月の青森県知事選は、むつ市長の宮下宗一郎氏有利との見方もある。もちろんまだ勝敗は読めないが宮下氏が勝った場合、青森の原子力事業はより対応が難しくなる。
―原子力問題は引き続き楽観視できないな。