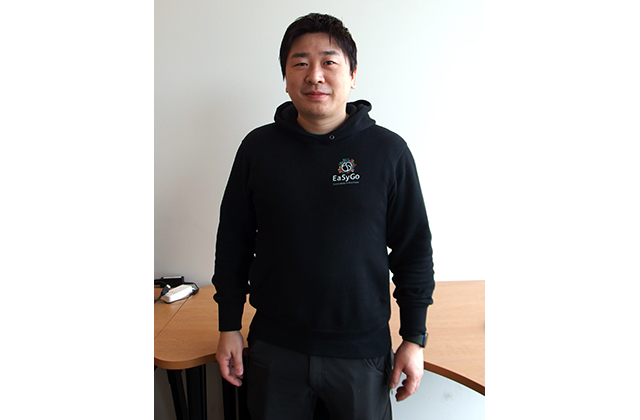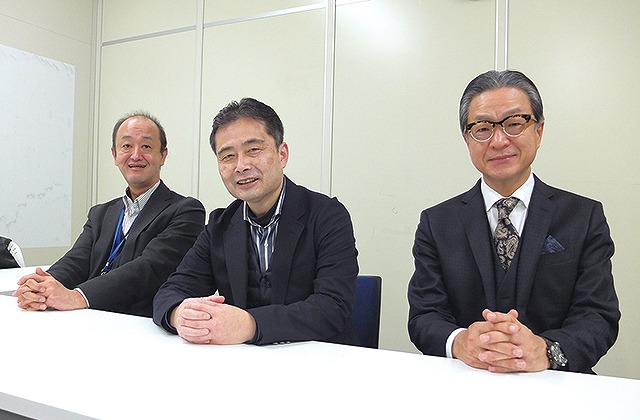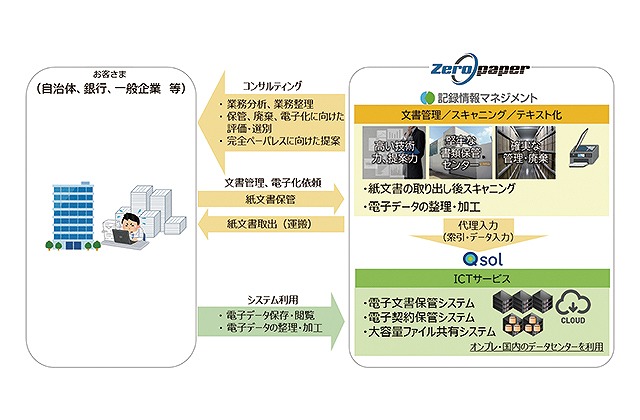飯倉 穣/エコノミスト
1,電力改革の行き詰まり
電力システム改革は、昨今電力販売に熱心な営業マンを生む一方、電力供給不安もばら撒いている。21年1月の電力卸価格の高騰・需給逼迫懸念以来、22年6月電力需給逼迫注意報、そして晩秋、冬季の電力需給逼迫警戒・節電を再度呼びかけた。
節電に追われる越冬中に、電力事業者の倫理を問う情報漏洩(不正閲覧)問題が発覚した。この事案を受けて電力供給システムを混迷する動きも登場する。報道は伝える。「不正閲覧「大手電力に蔓延」送配電部門「所有権分離を」有識者会議 政府案目指す」(朝日23年3月3日)、「小売・送配電の資本分離案 電力不正閲覧巡り有識者会議 実現にはハードル高く」(日経同)。
提案は、迷走する現電力システムの合理的な見直しでなく、電力自由化の不都合を更に助長すると思われる。情報漏洩と電力システム再改革を考える。
2,不正閲覧は、現行法での対応問題、競争浸透の副産物
情報漏洩は、商道徳と公正競争問題である。電力託送業務で知り得た新電力の顧客情報を、閲覧可能な電力側の社員・委託先が閲覧し、営業に活用すれば不正である。
電力・ガス取引監視等委員会が、報告徴収したところ、大手電力10社中7社で情報閲覧があり、顧客対応や一部営業に使用されたことが判明した。営業用に使用する行為は、電気事業法(23条等)で禁止されている。一般送配電事業者は、顧客情報を託送供給及び電力量調整供給業務(及び再エネ特措法の業務)以外に提供できない。当該規定は送配電事業者の中立性の確保を図る趣旨である。違反があれば、経産大臣が、行為の停止・変更命令、業務改善命令を行う。命令違反となれば罰則・罰金である。
故に今回の情報漏洩(一部不正閲覧)問題は、現行法で対応可能である。今回違反行為ありの前提で、さらに厳罰を求める声もあるが、現行制度を考慮すれば、制度変更は不要である。また情報漏洩が、競争の視点でもし不公正取引なら、独禁法の適用(2条9項)もある。現実の行為を調査し、違反する行為があれば、現行法で適正に処分すれば十分である。
皮肉となるが、現状は、電力システム改革(自由化)の狙い通り、販売面で自由化浸透中ということであろう。電気の商品化を前提とする販売競争が認められる(安定供給上問題続出だが)。経験論で言えば、日本における競争市場は、しばしば販売・収益獲得のために様々な局面で適法行為のみならず、脱法行為もあり、また行き過ぎで違法行為も見られる。この意味で電力業界は競争状態になっている。
問題があるとすれば、改革後の法体系・制度が、電力の供給不安を出現させたことである。
3,再エネタスクフォース提案の「罰則強化と所有権分離」は不要
この事案を受けて、再生可能エネルギー等規制等総点検タスクフォースは,公正な競争の確保というお題目で提言を行った(23年3月2日)。
概述すれば、不正閲覧は、発送電分離の基本要件が確保されず、公正な競争を揺るがしかねない。現行法令上の事業許可・登録の取り消しなど厳正な処分を行い、改めて公正な競争環境の整備を目指し、行為規制の強化や所有権分離を含む構造改革を実施すべきである。
具体的には第一に現行法令で、真相の徹底究明、厳正な処分の実施、第二に今後の制度改正で、行為規制の抜本的強化、罰則の強化、行政上の制裁のさらなる強化、電取委の権限強化と組織拡充、更なる送配電事業の中立、所有権分離の実現を求める。
その意図は様々あろうが、提案は、自由化後の電力システムの欠陥を無視した「どさくさ紛れ」か「火事場泥棒」的である。現行規程を徒に搔きまわしても混乱するばかりである。電力供給の安定・低廉の視点か見れば、有識者の提案を離れて基本に戻り、改革後の電力システムの再検討・再考が必要である。
4,不祥事が適切な対応を歪めることに留意
提案の動きを見ると、1990年代の経済金融混乱への対応や思い付きの構造改革が思い出される。現在の雇用不安定・経済の停滞は、90年代の対応不首尾の延長にある。国民感情・マスコミ誘導に煽られた一連の金融問題処理等である。政府(行政)、政治、エコノミスト等は、「バブルの結末でほとんど真実を無視し、崩壊の原因を別の要因に見つける行動に走った」(ガルブレイス「バブルの物語」参照)。
ゼロ成長経済を直視せず、需要崩落・過剰能力の実態を把握できず、また金融問題に抜本的に取り組まず、経済不振打開(バブル崩壊後)を、内外格差・高物価構造・日本型システムに求め、構造改革旗印の市場崇拝の規制緩和・中央省庁嫌気の地方分権を崇めた。構造改革お題目の電力システム改革もその一つである。
そして政治家・官僚・企業・民間金融機関の不祥事が、報道の煽りを招来し、国民感情を突き上げ、金融問題処理の時期・方法を歪め、構造改革信奉となった。いつの世も不祥事は、物事の処理を歪める。
今回の事案は、情報漏洩という不祥事で、電力自由化論者が、これを奇貨として、電力システム改革の不都合をさらに混迷の方向に誘導している。不祥事を起こしたサイドへの厳正な対応は、対応として行い、有識者の有識程度を勘案して、他の問題に拡散させないことが重要である。
5,議論すべきは、電力自由化による供給不安定
繰り言になるが、電磁気学・経済学の論理から、電力自由化という市場任せは、ここ数年の軌跡から明らかなように非合理的で電力需給を混乱させている。
自由化は、市場競争で効率を上げ、安い電力の安定供給可能を喧伝し進められた。電力供給不足や停電が起きても市場が、価格変動で、供給投資や節電を促し、需給調整する。競争による効率化で電気料金が下がる。卸電気市場等を整備すれば、誰でも供給・販売に参加可能で消費者に利益をもたらすと、論者は強弁した。
結果は、「あなたに合った電気を選べる時代」と同時に「電力供給の不安定、価格のボラテイリテイ、輸入エネルギーへの適応力低下、そして需要家の戸惑い」という事象である。安定供給の要となる投資は生起しなかった。そして自由化された市場は非効率で、国監視・管理の市場・事業となった。電力自由化は、電力システム国有化現象であった。そしてある意味で企業理念の蒙昧、経営不在、従業員のモラル低下を誘発する。
電磁気学等の法則に沿えば、安定性で発送電一貫体制が合理的かつ自然あり、且つ発送電一体の相互連結が、限界費用に基づく発電の効率性を確保するうえで優位である。発送電分離なら、ホールドアップ問題(不確実性)が発生し、リスク回避で過少投資となり、予備力低下を招き、且つ供給義務の所在が不透明なため、安定供給が覚束なくなる。発送電分離は、垂直統合の相互連結と発送電のコンビネーションの合理性を無視している。
電力の安定供給は、電源確保で適切な予備率、適切な電源投資が依然重要であり、ピーク対応の低稼働電源も必要である。それらの投資を回収するため、また安定的な燃料調達には、コスト(固定費・変動費・燃料費)プラスフィー(報酬)の料金が、依然合理的である。
6,基本に戻ろう
今回の情報漏洩が販売面で公正な競争を歪めるとしたら、当然市場における不正競争は、本来独禁法の問題である。電力システムの特異性から、電気事業法の各規定があるとすれば、その法律の定めに従い、淡々と処分を行えば足りる。
今回提案のあった罰則・制裁強化、電取委の権限強化(自由化と矛盾するが)、所有権分離等は、電力の安定供給や効率化・価格低廉と関係希薄で、本質論のすり替えである。ある意味で電力システム改革の失敗を糊塗している。今後は、電力供給の安定性向上を目指す視点で提言すべきであろう。
【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。