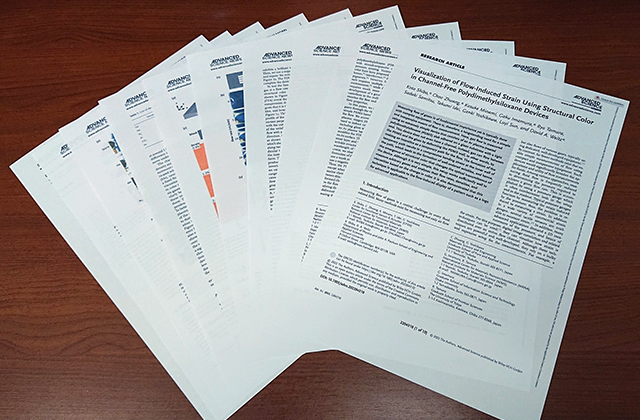杉山大志/キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹
「GDP(国内総生産)の2%」という防衛費騒動の陰で、より巨額な「GDP3%」もの費用を伴うGX(グリーントランスフォーメーション)=「脱炭素」の制度が、公開の場でほとんど議論されることなく、導入されようとしている。
岸田文雄首相肝いりで政府が進めてきた「GX実行会議」は昨年12月22日、「GX実現に向けた基本方針」をまとめ、1月22日までの期間でパブリックコメントを募集 している
基本方針やGX会議の資料は以下の通りだ。
GX実行会議HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html
GX実行に向けた基本方針(案) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou1.pdf
GX実行に向けた基本方針(案) 参考資料 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou2.pdf
政府は昨年末のわずか3カ月ほどの短期間に、官邸主導のGX実行会議でこの案をまとめた。しかし、審議会などの公開の場での議論はほとんどなかった。
同案では「安定・安価なエネルギー供給が最優先課題」とし、「原子力の最大限活用」を掲げた。ここまでは良い。
だが、政府は「10年間で150兆円を超えるGX投資」を実現し、脱炭素と経済成長を両立する、としている。そして、この投資を「規制・制度的措置」と政府の「投資促進策」で実現するとしている。
これは年間15兆円だから、実にGDPの3%である。防衛費よりも巨額の費用の話になっている。
そして、中身を見ると「再生可能エネルギーを大量導入する」(約31兆円~)、「水素・アンモニアを作り利用する等」(約10兆円~)となっている。
これは既存技術に比べて大幅に高コストだ。政府はこれを丸抱えで進める。研究開発、社会実装を補助し、既存技術との価格差の補塡までする。
これでは日本経済も高コストになり成長など望めない。
RITE(地球環境産業技術研究機構)の試算
RITEによるGDP変化の要因分解
負担は再エネ賦課金の数倍か 実質的なエネルギー増税へ
政府が「脱炭素と経済の両立」と言い始めたのは2009年の民主党政権にさかのぼる。当時の目玉は、太陽光発電の大量導入だった。だがその帰結として、いま年間3兆円の再エネ賦課金の国民負担が発生し、「経済の重荷」になっている。今の政府案は、これを何倍にもして再現するものに見える。
また、政府は投資に充てるため20兆円の「GX経済移行債」を発行する。これを新設の「GX経済移行推進機構」が運営する「カーボンプライシング」制度で償還するとしている。
カーボンプライシングとは、エネルギーへの賦課金とCO2排出量取引制度で、実質的にはエネルギーへの累積20兆円の増税だ。
だが、これは論理的におかしい。政府は新しい制度が経済成長に資すると言うが、ならば法人税や所得税などによる一般財源の増収があるはずで、それで償還できるはずだ。これは建設国債と全く同じ話である。新たな償還財源など要らないはずだ。
そして累積20兆円もの規模で特別会計のごときものを作り、その運営のための外郭団体である「機構」を設立するというのは問題だ。行政の本能として、この機構を維持・拡大するようになる恐れがある。そのためにカーボンプライシングが強化されるならば、これも「経済の足かせ」になる。
排出量取引は欧州が先行したが、失敗の連続だった。排出権割当ての制度変更が延々と続き、不安定で経済は混乱した。行政は肥大化した。なぜ、日本が追随するのか。
一連の新しい制度を通じて、政府はエネルギーの生産・消費に関連する投資に、ことごとく関与するようだ。だが、何に投資するか政府が決めるというのは計画経済で、経済成長は望めない。
以上のように、現行の政府案には、巨額の国民の財産が関わっており、重大な問題が山積している。
いま多くの事業者が政府からお金を受け取ろうとし、政府担当者はそれだけ予算を増やそうとしている。このため一連の制度設計について、必ずしも賛同していなくても、表立った異議の声はほとんど聞こえてこない。だが目先の利益ばかりを考えるだけではいけない。
国全体としてのエネルギー需給および経済の将来について、本当にこの制度設計で良いのか、真剣に検討すべきだ。
月末に始まる通常国会では、公開の場で大いに議論すべきだ。一連の制度の性急な導入は控えるべきではないか。
【プロフィール】1991年東京大学理学部卒。93年同大学院工学研究科物理工学修了後、電力中央研究所入所。電中研上席研究員などを経て、2017年キヤノングローバル戦略研究所入所。19年から現職。慶應義塾大学大学院特任教授も務める。「中露の環境問題工作に騙されるな! 」(共著)など著書多数。最近はYouTube『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志