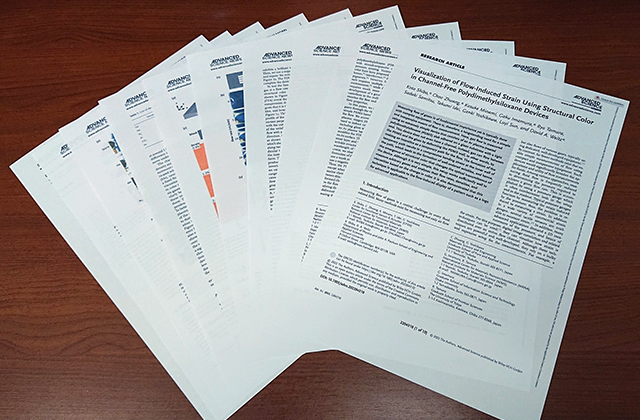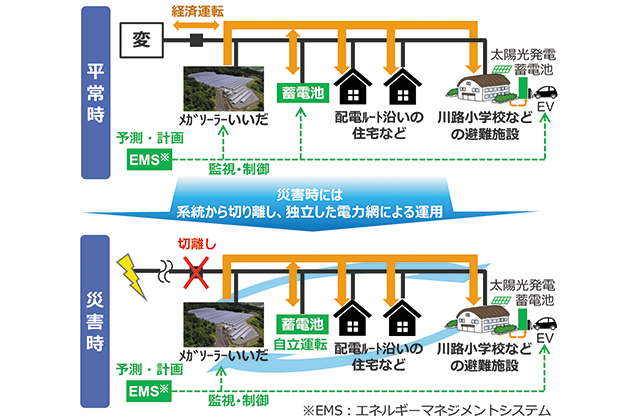【おやおやマスコミ】井川陽次郎/工房YOIKA代表
偏執的にすぎないか。朝日のツイッター報道のことだ。米起業家イーロン・マスク氏が2022年10月にツイッター社を買収し、最高経営責任者(CEO)として改革に乗り出して始まった。
まず、11月6日「ツイッター、従業員の半数解雇、広告止める動きも」で、社内に混乱と報じた。「マスク氏は『売り上げや経費に深刻な課題』と話した」と言い分も伝えたが、同8日は「従業員呼び戻す?、差別的投稿の急増、指摘」、同10日も「ツイッター、差別・中傷懸念、買収で投稿監視に変化、政府議論にも影響」と同趣旨のニュースを伝えた。
ツイッターをおとしめる狙いか、30日夕刊は「『北京』『上海』検索→アダルトサイト大量表示、ツイッター」、別記事で「ツイッター、コロナ偽情報の対応撤回」を掲載した。後者は「新型コロナウイルスの感染者数は減っているが、冬場に増えるとの見通しもあり、偽情報が拡散されやすくなる」と批判するが、それを朝日に言われても、と思う。
朝日は、子宮頸がん予防のためのHPVワクチンの否定的報道で広く知られる。接種の恐怖が拡散され、世界の動向に反して日本では、22年春まで接種勧奨が控えられた。この結果、子宮頸がんの罹患者は年間1万人、死者3000人と、異常事態が続く。
同年3月の千葉県知事のツイートは、「朝日新聞がHPVワクチンの積極勧奨再開にあたり、『医療者側の理解が進んでいる』と記事要約ツイートしたことが医療関係者を中心に問題となっています。朝日等が報じた理解不十分な記事をきっかけに反対が広がり、積極勧奨が停止されたのが実態で、私も正直目を疑いました」だ。
朝日12月3日「耕論、ツイッター買収、その意味」は、憲法学者も動員した鼎談である。
冒頭でマスク氏を「富豪」と紹介し、憲法学者氏の「富の集中、政治的な力にも」とする主張が続く。「1人の人間がツイッターのような巨大プラットフォームを簡単に買収できる巨額の富を持つことは妥当か」「(ツイッターで)名もなき個人でも、『つぶやき』が政治を動かす力になる。同時に、(ツイッターは)どんな言論を流通させ、排除するか。それを決定する潜在力を持ちます。民主的に選ばれたわけではない所有者に、世界の民主主義の行方が委ねられている」と警告する。
よく分からない。嫌なら使わなければいい。同種プラットフォームは、他にもたくさんある。
朝日の執着の理由と疑われるのは、投稿の常連席、特等席が消えたことへの不満、反発だ。
買収後、まず廃止されたのは「キュレーション」部門とされる。デマや危険情報を排除する役割に加え、特定の傾向の投稿を集めて利用者の目に触れやすくする業務を担うが、行き過ぎれば情報操作、印象操作になる。
買収以前は、朝日や関連ニュースサイトからの投稿が多く表示された。朝日記者が福島県の風評をあおる投稿まで流れてきた。買収後は減った。この部門は、大手メディアがニュース拡散を直接依頼する窓口も設けていたとされる。朝日と相性が良かったのだろう。
ツイッターでは「炎上」もよく起きる。政治家、企業などを標的に罵詈雑言の投稿が量産され、大手メディアが世論と紹介する。こうした虚しい騒ぎも今後、減ればいい。エネルギー業界などが、メディアと対等に情報発信できる。チャンスである。
いかわ・ようじろう デジタルハリウッド大学大学院修了。元読売新聞論説委員。