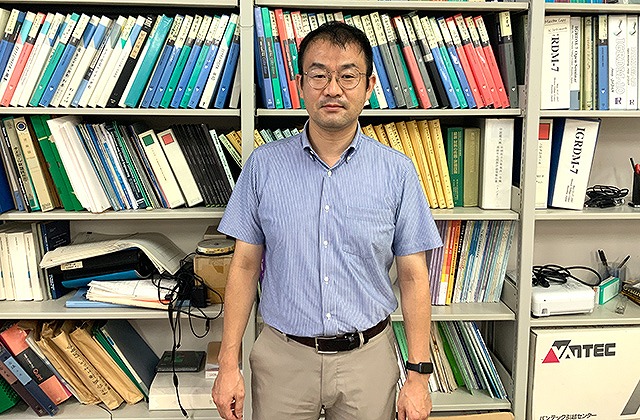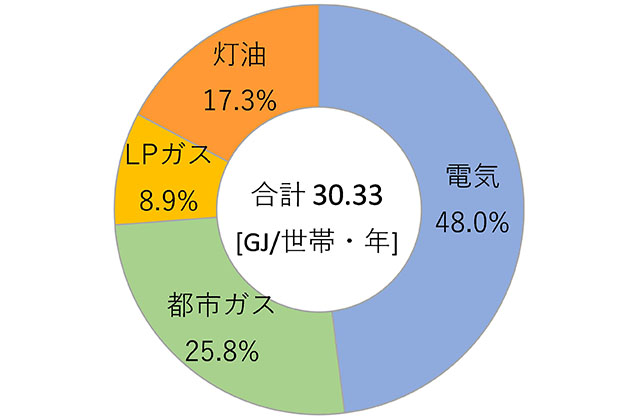<出席者>電力・ガス・石油・マスコミ/4名
ロシアのウクライナ侵攻でエネルギー需給に黄信号がともっている。
だが、それで原発の再稼働が早まると考えるのは早計のようだ。
―ウクライナ侵攻に端を発した石油・ガスなどの供給不安と価格高騰、電力・ガス料金の値上げと需給ひっ迫―。エネルギー問題が世間の注目を集めている。これだけ関心を持たれるのは、オイルショック以来だ。マスコミの論調も変わってきているのでは。
石油 ロシアは西欧へのガス供給を止め、「サハリン2」で強権を発動した。エネルギー資源を「武器」にして、ウクライナ侵攻に反対する西側に圧力をかけている。
今までほとんどの大手紙は、福島第一原発事故と地球温暖化問題で、再エネ=推進、原発・火力=低減を編集の軸に置いていた。しかし、隣国ロシアの横暴ぶりを目の当たりにして、さすがに安定供給に目を向けざるを得なくなった。
ガス といっても、今までかざしていた旗を急に降ろすわけにはいかない。電力・ガスの値上げ、需給ひっ迫をどう取り上げるか、今、どこのメディアも苦慮している。
ただ、脱炭素一辺倒だったドイツの政策転換の影響は大きい。ロシア産ガスの供給不足で、今年末で停止する予定だった原発も稼働を延長するかもしれない。今までほとんどの大手紙がドイツを「環境先進国」として持ち上げて、手本とすべきとしていた。さすがに考え直さないといけないと思っているはずだ。
電力 日経が変わり始めている。特別編集委員の滝田洋一さんが書いたコラム「核心」(7月18日朝刊)には「おや」っと思った。
―BSテレビ東京の経済番組で解説をしている経済の専門家だ。
電力 当面の大きな課題のひとつが物価上昇だ。滝田さんは、政府は「物価上昇の大きな要因であるエネルギーの問題に取り組むほかない」と指摘している。まったく同感。
次に電力問題だ。需給ひっ迫解消に「安全性が確認された原子力発電所の再稼働がカギを握る」と本質を突く。なぜ再稼働が進まないかも掘り下げる。原子力規制委員会の審査について、「運営ルールについては国会が責任を持って基準を示すべきである」と述べている。
マスコミ 旧東京電力経営陣の「弁護」までしている。東京地裁が勝俣恒久さんらに命じた13兆円の賠償について、原発は国策民営であり、「事故が起きた際の責任を会社と経営者だけに負わせるのは無理がある。エネルギーの中で原発が欠かせないとするなら、首相は政府による関与と支援を明確にさせるときだ」と「核心」を結んでいる。
日経に出た「主張」「意見」 読売の連載は中途半端
―よくここまで踏み込んで書いたな、と思った。
マスコミ 今まで日経には原発について「主張」「意見」がなかった。「より安全性の向上を」や「国民的議論を深めよ」は主張でも意見でもない。知っている限り、原子力政策について具体的な主張をしたのはこの記事が初めてだ。
電力 滝田さんは経済が専門。その視点でみると、原発の再稼働は当然なんだろう。エネルギー・環境担当の記者や編集・論説委員だったら当然、再エネ、水素に触れる。ここまでストレートに書けなかったはずだ。
石油 要するに、「色眼鏡」をかけないで純粋に見ると、原発は必然ということだ。日経がどういう意図で掲載したか、「核心」欄がどういう位置付けなのかは分からない。しかし、社としての方針が変わってきているのは間違いないと思う。
―読売新聞も8月3日から「進むか、原発再稼働」の連載を始めていた。
ガス がっかりした。新味がないし、具体的に何をすべきか提案もない。
石油 とにかくこの分野の著名人を一通りインタビューすればいい、という感じだ。しかもつまみ食い的に発言を使われて、「困った」と話す学識者もいるらしい。読売は原発推進が基本方針。それを考えると、中途半端な連載との印象は拭えない。
ガス 時々、エネルギーの分野で目を引く記事が毎日、産経に載る。中でも若手記者ががんばっている。よく取材して記事をまとめている。朝日、読売、日経に比べて待遇は良くないはずだ。それだけに応援したくなる。
原発再稼働の行方は 統一教会問題が影響も
―日本原燃の増田尚宏社長が六ケ所再処理工場について、9月末の完成予定を見直す考えを明らかにした。新聞各紙は「26回目の延期」と書いている。
電力 増田社長は「審査の状況を踏まえ、今後の見通しについて検討する」と言っただけだ。まだ2022年度上期完成の旗は降ろしていない。ただ、関係者は9月末が絶望的なことを分かっている。その場合のマスコミ対応も準備していると聞く。
マスコミ 国、青森県と発表のタイミングを見計らっているようだ。完成が遅れる場合、主な理由は原子力規制員会の審査の遅れ。でも、それをマスコミに強く言えない。原燃は歯がゆい思いをしているだろう。
とはいえ、今回の完成遅れの影響は大きい。エネルギー安全保障に関心が高まって、準国産エネルギーとして、ようやく原発に追い風が吹き始めている。それに水を差すかたちになる。
ガス それよりも、再稼働への影響が避けられないのは統一教会の問題じゃないか。この問題で原発推進の清和会の議員が集中砲火を浴びている。自民党の支持率も低下気味だ。すると、岸田政権としても不人気な原子力政策には手を付けづらくなる。
―統一教会系の「世界日報」はは原発をどう報じていたんだろう。気になるな。