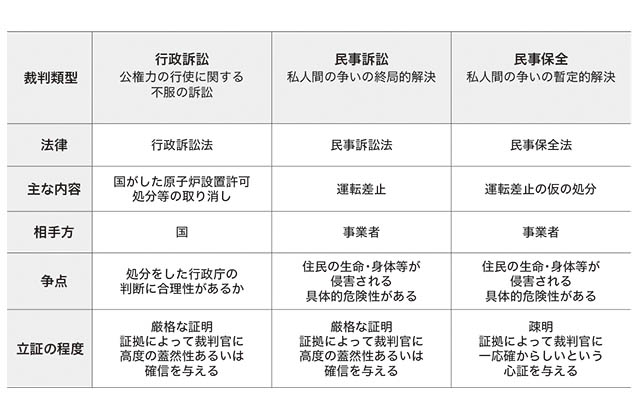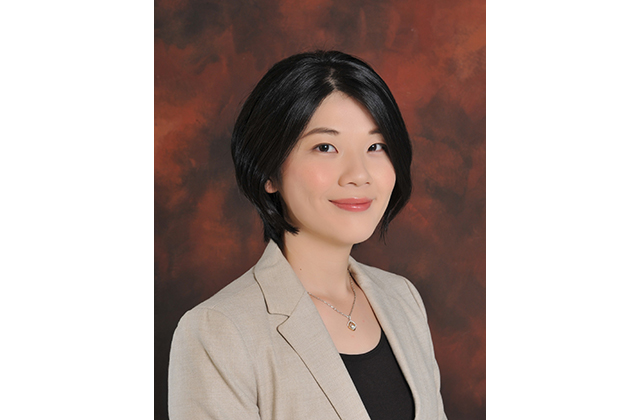【福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.11】石川迪夫/原子力デコミッショニング研究会 最高顧問
福島1号機は圧力容器の底が抜け、炉心が格納容器に落下した。
その主因は、高温の物体による大きな輻射放熱だ。
1号機は炉心の冷却水が全て蒸発して高温となり、圧力容器の底が抜けて炉心が格納容器に落下した。半日後に入った注水で水素爆発が起きた。今回はその主役である輻射熱の説明から入る。
やかんから湯気が出るのは見慣れた光景だが、湯気になるのは蒸気の熱が空気に伝わって冷えるからだ。この現象を伝熱という。ほかに真空を通して熱を伝える輻射熱があるが、われわれが住む低温の世界では量的に小さい。
輻射熱の代表は太陽だ。温度6000℃の太陽の表面から放射される熱は、真空の宇宙を通過して地球に届く。その距離、実に1億5000㎞。スペースシャトルで200日かかる。こんな遠方に届く太陽の熱を温かいと感じる人は多いが、太陽に言わせれば、輻射熱を出して己を冷やしているというであろう。輻射熱という言葉は、熱の出し手(冷える)と受け手(温める)では意味が正反対となる。間違いやすいので、本稿では出し手を輻射放熱と書く。
輻射熱にはステファン・ボルツマンの法則がある。輻射熱量は、色や形など物体の表面状態と、出し手と受け手の温度(絶対温度)の4乗の差で定まるというものだ。この4乗が利いて、温度が高くなると輻射放熱はがぜん大きくなる。
表面状態を同じとして、常温の物体(300K(ケルビン度))と溶融炉心(UO2:融点約3000K)とでは輻射放熱はどれほど違うか。10の4乗の比較だから、違いは1万となる。低温の世界に住むわれわれが、1万倍大きい輻射放熱を感覚的につかむのは困難だが、1円と1万円の差と考えれば、何となく頭で理解できる。
NHKの流したフェイク映像 崩壊熱でメルトダウン起きず
水が流れるのはわれわれには常識だが、高温の世界では、発熱を失った液体は輻射放熱ですぐ固化する。流れを見ることはまれだ。その好例が融点の高い物質の液体物性の測定だ。融点が2000℃を超える材料は液体の維持が困難で、レーザー照射で溶かした途端に、試料は重力で照射範囲外に移動し、測定する間もなく固化する。このため試料を浮遊させて照射し、測定を行うという。最近は国際宇宙ステーションでの実験が可能となり、少量の試料を無重力空間で溶かして測定しているという。
高温の溶融物が出す輻射放熱はかくも大きい。大見当だが、輻射放熱が伝熱を超えるのは1500℃くらいと覚えておくと便利だ。
高温の炉心に冷水を注ぐとジルカロイ・水反応が起き、その反応熱で溶融が始まるが、反応が終わると溶融していた炉心はすぐに固化する。確かに、TMIのスケッチ図に描かれた溶融燃料の流下距離はわずかだった。融点約3000Kの溶融炉心の輻射放熱はかくも大きい。僕がメルトダウンはないと主張する根拠はここだ。
事故直後にNHKが毎日のように放映した福島の映像は、溶けた炉心が流れて圧力容器を溶かし、格納容器の床に落ちる動画であった。輻射放熱を無視したフェイク映像だが、映像を見て炉心溶融を信じる視聴者は非常に多い。
輻射放熱の説明は以上だ。高温物体が出す輻射放熱の大きさは理解されたと思う。この説明を下敷きに1号機の溶融を考えよう。
空っぽ状態の1号機の炉心温度を約2000℃と推定したのは、0・8%に低下した崩壊熱と、輻射放熱の大きさとの比較からだ。この温度で輻射熱の均衡状態を計算すると、圧力容器が約600℃、格納容器が約150℃となる。炉心溶融(融点2880℃)には程遠いが、炉心シュラウドや下部支持盤といったステンレス鋼製の炉心構造体(融点約1400℃)は、溶けた部分が多かったであろう。支持盤が溶ければ、燃料棒は落下する。
鉄は700℃になると構造材としての強度を失う。600℃の圧力容器は落ちてきた燃料棒や炉心材料で熱されて、重量を支え切れずに底が抜けたに違いない。燃料棒や炉心材料は、底と一緒に格納容器の床上に落下したに違いない。
この時刻が、圧力上昇のあった3月12日午前2時半だ。異見ありと前報で書いたのは、圧力容器は炉心溶融でなくとも壊れ得るからだ。借問するが、原因を炉心溶融と考えた人は、半日後の注水で起きた爆発をどう説明するつもりか。溶融して変質した炉心が、半日もの輻射放熱で冷えた状態で、爆発前の1時間の注水で大量の水素を発生させるとは考えられないが。
ここで再び輻射放熱が登場する。格納容器の温度は150℃と低いから、格納容器床での輻射放熱は増大する。午前2時半から注水の始まる午後2時半までの半日、落下燃料は冷えて、温度は200℃くらいに下がっていたと考える。
ところが午後3時36分、注水開始の約1時間後に1号機は爆発した。注水で水素が大量発生したのは明白だ。床上の燃料棒は冷えて反応できないから、圧力容器の中に残った燃料棒が反応するしかない。推測だが、炉心に残った燃料棒は相対的に多く、崩壊熱により互いに高温を維持し合っていたのではなかろうか。

出所:ISASニュース467号