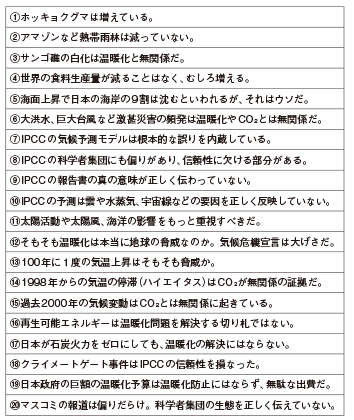<出席者>電力・ガス・石油・マスコミ業界関係者4人
今夏は重油流出、LPガス爆発など、石油関連の事故が国内外で起きた。 またエネルギー政策の見直しの議論が始まる中、石炭・原発・再エネの報道も増えている。
―環境問題といえば、地球温暖化防止が最大のテーマになっているけれど、インド洋の島国モーリシャスの沖合で、商船三井が運航する貨物船が座礁して、8月6日から大量の重油が流れ出た事故があった。マングローブ林や、絶滅危惧種がいる海洋保護区の汚染が心配されている。
石油 日本ではあまり大きく報道されなかったが、ヨーロッパではバカンス先として知られていることもあって、イギリスのBBCやフランスの公共放送、アンテンドゥなどは、事故が起きてからすぐに大きく取り上げて伝えていた。環境問題にうるさい人たちは、かなり危機感を持っているようだ。
ガス 日本は政府、企業、メディアの対応が遅い。ようやく8月中旬になって取り上げられるようになった。船長をはじめ船員に日本人はいなかったが、商船三井がチャーターした船で、船主は日本企業。当然、日本に批判の矛先が向くことになる。
1997年にロシア船籍の「ナホトカ号」が難破して、重油が島根県から石川県に掛けて漂着する事故があった。あの時は海上保安庁や自衛隊、自治体の関係者、それに全国からボランティアが駆けつけて油を回収した。今回も、商船三井がジャンボ機をチャーターして、社員や家族のボランティアを現地に送ってもおかしくない事故だった。
電力 政府も商船三井も初めは「どの程度かな」と様子見だったようだ。モーリシャスは生物多様性の「ホットスポット」と呼ばれているらしい。日本は、2010年に名古屋市で生物多様性条約の10回目の締約国会議を開いている。それだけに損害賠償とは別に、道義的責任は免れない。
マスコミ 小泉進次郎環境相は地球温暖化防止で張り切っているけれど、現地に行くとか、もっと本腰を入れて対応すべきだった。それを進言しなかったのなら、環境省の役人のセンスを疑うね。
郡山でプロパン爆発事故 LPガスのイメージ悪化
―今年の夏は、石油関連の事故が世間の注目を浴びた。国内では、福島県郡山市でのプロパン爆発事故。LPガス業界にはショックだったと思う。
石油 まず原因究明が重要になる。だけど、実は業界も役所も事情をよく把握していなくて、報道ベースの情報しか分からない。
死亡者が出たので、地元の警察と消防本部の担当になる。それで詰めている地方紙の記者が情報を取ってくる。その記事を共同通信が報道して、関係者はそれを読んでいる。だからまだ対策の打ちようもない。
ガス LPガスのコンロの調子が悪くて、IHに転換する工事の中で起きた事故のようだ。すごい爆発だったから、中には、「これはテロにも使える」と心配する人もいた。LP業界はかなりのイメージダウンだろう。
マスコミ 「やっぱりIHがいいな」という声が世間で増えてくるかもしれない。小売り自由化前は、電力会社は「敵失」をよしとするようなことはなかった。でも、今は分からないね。
―7月に梶山弘志経済産業相が非効率石炭火力のフェードアウト、再エネ主力電源化の具体的検討を指示して、エネルギー関連の報道が増えている。
ガス 週刊東洋経済の「脱石炭、待ったなし」は良い特集だったし、週刊ダイヤモンドの連載「SDGsの裏側」にも良い記事があった。日経も「経済教室」で電源構成の連載を始めたけど、初回が東工大の柏木孝夫さんだったのには驚いた。
石油 柏木さんは以前からコージェネとか分散型電源の普及に力を入れていて、エネルギー関連の学者の中では本流から少し外れるからね。でも、しっかり原発の役割を主張していて、電力業界はありがたかったはずだ。
電力 国際大の橘川武郎さんが週刊エコノミストオンラインに投稿した「読売新聞のスクープはどこがミスリードだったのか」も、読売の報道の間違いを指摘して、経産省の狙いを分かりやすく説明していた。
しかし、敏感に反応したのは、やはり電気新聞。「岐路に立つ石炭火力」の連載は読みごたえがある。RITEの山地憲治さんから始まって、常葉大学の山本隆三さん、橘川さん、エネ研の小笠原潤一さんと続けていた。執筆者も順番も適当に選んでいるのではなくて、電気新聞なりに考えていることが分かった。
エネ基本計画の議論 原発比率をどうするか
―来年はエネルギー基本計画の見直しが始まる。これから非効率石炭火力の廃止と合わせて、再稼働、新増設が進まない原発と再エネの扱いの議論は避けられない。
ガス 2030年の電源構成は、いまは原発が20~22%の比率なっている。だけどそれが難しいことは皆、分かっている。すると原発の比率をどこまで落とすか、それと非効率石炭火力が減る中、石炭とガスのバランスをどう取るのかが最大の課題になる。
もし原発の比率を15%に下げると、いま22~24%の再エネを30%にしなければならない。原発嫌いの環境省は当然、それ以上に増やしたい。でも、経産省はそれくらいが限度と考えている。
マスコミ 経産省は洋上風力に力を入れるようだけど、ドイツやオランダなどと違い、遠浅の海辺が少ない日本でどれくらい設置できるのか、疑問に思っている人は少なくない。環境省がゴリ押しして無理に入れようとすると、電気料金を上げざる得なくなるかもしれない。
―コロナ禍の不況対策で消費減税を唱える人がいるけれど、まずそんなことを止めた方がいいね。