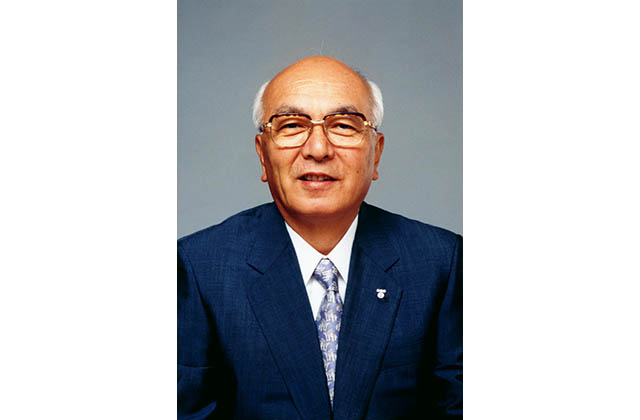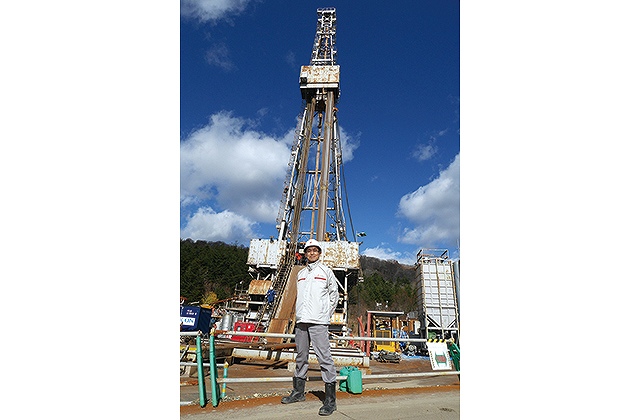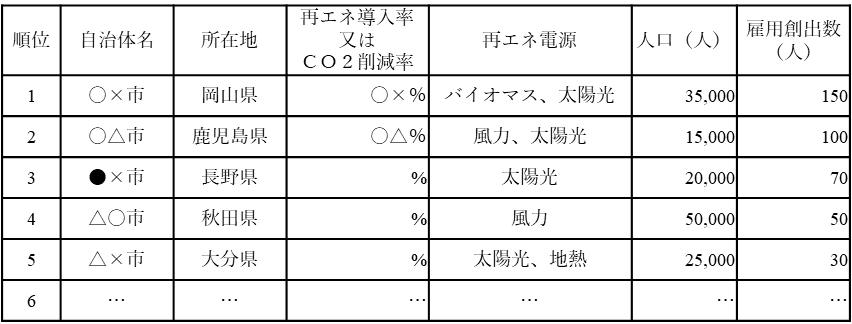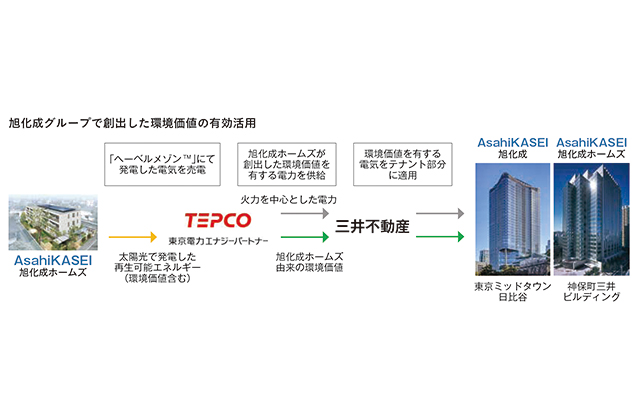【業界紙の目】田中信也/物流ニッポン新聞社 東京支局記者
原油高による軽油価格の上昇は、トラック運送事業者の経営に大きな打撃を与えた。
働き方改革に関する「2024年問題」も抱える中、運賃への燃料価格の適正な反映が至上命題となる。
2021年はレギュラーガソリンの全国平均小売価格が10週連続で値上がりし、1ℓ当たり169円と約7年ぶりの高水準に達した。全日本トラック協会(全ト協)は11月9日、軽油高騰対策を緊急決議し、斉藤鉄夫国土交通相に要望書を提出した。
トラック運送事業での営業費用のコスト構成を見ると、「燃料油脂費」が約15%と「人件費」の40%に次いで高い割合を占めており、トラックの主要燃料である軽油の価格が高騰すれば、事業者は大きな打撃を受けることが分かる。
業界求めるトリガー条項解除 政府は消極姿勢崩さず
このため、要望では「軽油価格の高騰が続けば、中小零細事業者が99%以上を占めるトラック運送業界の経営は悪化の一途をたどり、将来的に安定した輸送力を確保できなくなることも懸念される」として、政府備蓄原油の放出に加え、①燃料高騰分の価格転嫁対策、②税制および補助金による燃料費の負担軽減措置、③高速道路料金の割引制度の拡充―など、マクロ、ミクロの両面で支援策を求めた。
マクロ対策のうち政府備蓄原油の放出は、米国が協調放出を要請したこともあり、日本政府は初めて国内需要の1~2日分に相当する420万バレルを放出する方針を表明。だが、税制措置として求めていた、燃料高騰時に軽油引取税の課税を停止する「トリガー条項」の凍結解除については、政府与党は消極的な姿勢を崩さない。
これに代わる政策として創設されたのが、レギュラーガソリン小売価格(全国平均)が1ℓ当たり170円を超えた場合、5円を上限に石油元売りへ給付する激変緩和措置だ。ただ、原油価格の変動に合わせて価格を示す元売りへの支援より、「ガソリンスタンドや自動車ユーザーに直接補てんすべき」との声はトラック事業者のみならず根強く、日本維新の会と国民民主党、立憲民主党は、トリガー条項を発動させるための法案をそれぞれ臨時国会に提出した。
導入できない理由として政府与党は、発動後にトリガー条項を解除するのに最低3カ月を要するため税収低下が懸念されることや、凍結解除に法改正が必要なことを挙げているが、「自公政権として、民主党政権時に創設されたトリガー条項を復活させたくない」といった事情も見え隠れする。これに対し、全ト協の坂本克己会長は「われわれへの経済対策はしょぼい」と断言。軽油価格はこの1年で25円程度上がっており、5円ではどうにもならないのだ。トラック業界は12月2日、「燃料価格高騰経営危機突破総決起大会」を開き、自民、公明両党の国会議員に対し、トリガー条項に代わる制度も含む財政出動を求めた。
一方、荷主との交渉が基本となる価格転嫁の対策については、国交省は全ト協からの要望を踏まえ、直ちに荷主関係団体に対して「燃料費の上昇分を反映した適正な見直しを行う」よう書面で要請した。
価格転嫁対策としては、燃料価格の上昇・下落によるコスト増減分を別建ての運賃として設定する「燃料サーチャージ制」が08年に規定されている。同年、ガソリン小売価格が180円超と未曽有の高騰にひんしたことから導入する事業者が拡大したものの、その後、軽油価格が安定したことで導入の動きは鈍化。現状、全事業者の2割程度の導入にとどまっている。
サーチャージ制「もろ刃の剣」 標準的な運賃導入も推進
全ト協は「燃料サーチャージなどによる適正な運賃・料金の収受に向けた荷主関係団体・企業の理解・醸成」を求めているが、軽油価格が下落した際、荷主からの過度な値下げ圧力につながる「もろ刃の剣」になることも懸念される。また、適正なコストや利潤が反映されていない契約運賃のままサーチャージ制を導入すれば、「運賃本体の値上げがしづらくなる」として導入を敬遠するトラック事業者も一定数あり、軽油価格高騰対策の決定打とはなり得ていない。
 全ト協を中心に財政出動を要望している
全ト協を中心に財政出動を要望している
こうした中、サーチャージ制の導入以上にトラック業界が尽力しているのが「標準的な運賃」に基づく運賃・料金の導入だ。働き方改革関連法に基づき、24年度からトラック、バス、タクシーの各事業者に対し、時間外労働を「年間960時間以内」とする罰則付き上限規制が適用される。これにより、ドライバー不足や業績低下が懸念される「2024年問題」に備えるための特例措置が、標準的な運賃の導入で、改正貨物自動車運送事業法の規定に基づき、23年度末までの時限措置として、国交省が20年4月に告示した。
ただ、即座に値上げにつながるものではなく、標準的な運賃に基づいて適正なコスト・利潤を確保できる運賃・料金を算出し、これを基に荷主と交渉を行い、合意に基づく運賃・料金の変更を所管の運輸支局に届け出るのが通常の流れだ。また、「標準」ではなく、あくまで「標準的」と称するように、かつての認可運賃とは異なり、導入に対する強制力もない。
標準的な運賃は、新型コロナウイルス感染拡大の本格化と重なる最悪のタイミングで告示されたため、出鼻をくじかれた。その後、経済活動の復調や、国交省、全ト協とその傘下の都道府県トラック協会の普及推進運動により、導入するケースが徐々に増えてきた。
実際に、どの程度の事業者が告示に基づく適正運賃を実現したか把握するのは困難だが、導入状況を測るデータとして、全国の運輸支局などへの届け出状況を国交省自動車局が公表している。これによると、届け出件数は21年11月末時点で2万2806件あり、届け出率は40%に上っている。ただ、運賃・料金の届け出を先行し、荷主との交渉を「後回し」にしているケースが相当数に上ると見られる。加えて、都道府県ごとの届け出率の格差も顕著になっており、特例措置の期限まであと2年強と迫る中、問題は山積している。
12月以降、原油高は落ち着きを見せているが、「24年問題」の解決には、燃料費と人件費の収支改善は避けて通れない。トラック業界は高い政治力を生かすとともに、荷主に対しても毅然とした態度で臨むことが求められる。
〈物流ニッポン〉〇1968年創刊〇発行部数:15・8万部〇読者構成:陸上貨物運送業、貨物利用運送業、倉庫業、海運業、港湾運送業、官公庁・団体、荷主など