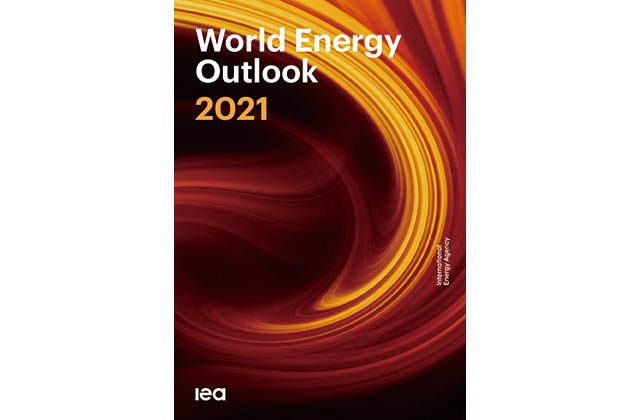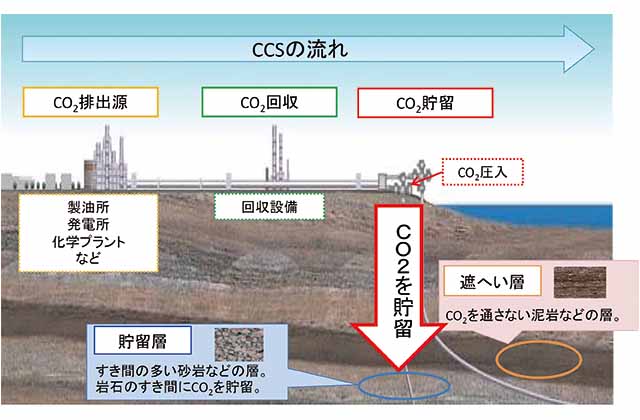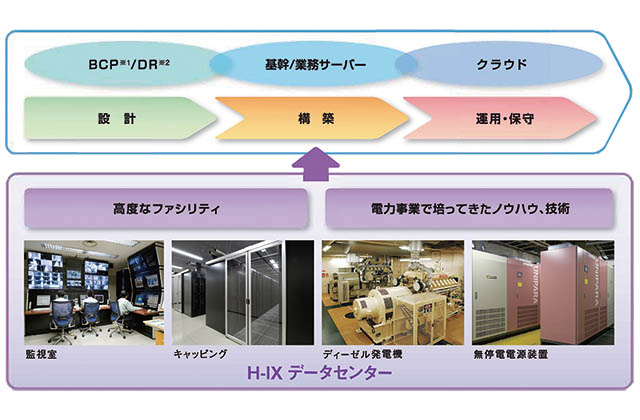杉山大志/キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
資本主義が大きく変わり「グレート・リセット」されて、2050年にはCO2排出量がゼロになる(=脱炭素)、という将来シナリオがある。このような将来シナリオは今や、国連、G7(主要7カ国)政府、日本政府、日本経団連などの大手経済団体、NHK・日本経済新聞・朝日新聞などの大手メディアが共有する「公式の将来」となっている。
だが、この将来像の技術的・経済的・政治的実現可能性は極めて乏しい。それにも関わらず、今日本の主要企業は軒並み、公式にはこの「脱炭素」を掲げている。
正にこのために、事業を預かる現場では混乱が起きている。不可能に向かって突き進むという事業計画を立て、実施しなければならないからだ。
ありそうにない将来像に基づいて事業を計画・実施することは、企業としての経営判断・投資判断を大きく歪め、利益を損ない、事業の存続すら危うくする。
そもそも将来は不確実であるため、複数の将来シナリオを描いた上で、ロバスト(強じん)な事業計画を立てる必要がある。これがシェル流のシナリオプランニングの思想と手法の要諦である。
筆者は、このシェル流のシナリオプランニングの実践として、3つの異なるグローバルシナリオを検討した。以下に手短に紹介する。なお詳しくは論文を参照されたい。
①「再起動」シナリオ、またはグレート・リセット・シナリオ
概要
これは、国連、G7諸国政府、日本政府、経団連など大手経済団体、NHK・日本経済新聞・朝日新聞などの大手メディアが共有する「公式の将来」のシナリオである。このシナリオでは、資本主義が大きく変わり「グレート・リセット」されて、50年にはCO2排出量がゼロになる(=脱炭素)。原動力は、環境問題に目覚めた国民である。それが政治を動かし、金融機関・企業が投資をすることで再生可能エネルギー・電気自動車などのグリーン技術が発達し、それが普及することで実現する。
展開
1. ドイツの新政権では緑の党が入閣し、50年となっていたCO2ゼロの目標年を45年に前倒しして、22年のG7議長国として他国に同調を求めた。支持率低迷にあえぐ英国ボリス・ジョンソン首相と米国バイデン大統領がこれに合わせて、一層野心的な目標を発表した。
2.日本もこれに前後してCO2ゼロの目標年を45年に前倒しをする。これに合わせて30年のCO2削減目標も46%から54%へといっそうの深堀をした。
3.世界的なエネルギー危機は、OPEC(石油輸出国機構)、ロシアによる原油の増産、ロシアとカタールによる天然ガスの増産、および中国の石炭増産によって緩和する。エネルギー価格が下がったことで、脱炭素政策への支持が継続する。
4.コロナ禍後の、諸国政府による大型財政支出継続は継続する。これによってグリーン投資にも膨大な資金が投入される。
帰結
A)再生可能エネルギー・EVは順調に拡大し、不要になった石油・ガス価格はIEA(国際エネルギー機関)のネットゼロ・シナリオで予言されたように低迷する。
B)環境・人権と経済安全保障を重視する先進国では、重要鉱物の採掘業・精錬業と製造業が復活する。
C)国連気候会議では毎年、継続的に諸国の脱炭素政策が強化される。
D)産業を取り戻し、環境対策に率先して取り組むG7は、リーマンショック以来の地政学的な失地を回復し、世界のリーダーとして復権を果たす。
②「脱線」シナリオ、またはグレート・デレイル・シナリオ
概要
このシナリオでは、グレート・リセットを目指した政策がことごとく裏目に出て、G7が衰退し、中国が世界の支配的地位を占めるようになる。
展開
「再起動」シナリオ1~4に同じ
帰結
A) G7諸国ではCO2排出量が厳しく制限されるようになり、これに排水・土壌汚染などの環境規制強化も追い打ちをかけ、化石燃料の生産・供給、およびエネルギー集約産業の工場が次々に閉鎖され、弱体化する。
B) 石油・ガス市場の支配力は、G7諸国のIOCs(国際大手石油会社)から、OPECプラスのNOCs(国営石油会社)へとバランスを大きく変える。
C) レアアース、太陽光発電用結晶シリコンなどの重要鉱物の生産・精錬、およびそれを用いた材料・部品・最終製品生産などを含め、あらゆる製造業の中国へのシフトが進む。
D) 毎年行われるCOPは、産業の空洞化をグリーンな活動な成果だとPRするG7諸国による「グリーンウオッシュ」の祭典と化す。
E) 地政学バランスはG7から中国およびOPECプラスに大きく移る。自信を深めた中国の介入によって台湾は1国2制度を経たのちに併合される。
③「反動」シナリオ、またはグレート・リアクション・シナリオ
概要
このシナリオでは、国民の反発を招いてグレート・リセットが失敗し、グリーン・バブルが崩壊する。脱炭素政策も忘れ去られるようになり、化石燃料が復権する。
今、先進国は無謀な脱炭素目標を競い、世界中でエネルギー価格が高騰し、インフレも高じている。この行き着く先は、と考えると、このシナリオにも蓋然性がある。
展開
1. 米国議会において審議されているビルド・バック・ベター法案は、民主党マンチン議員らの造反によってグリーンな政策は骨抜きになり、バイデン政権のもとではCO2削減は進まないことが明らかになる。
2.コロナ後の景気刺激策、放漫な財政、エネルギー・資源価格高騰などによるインフレが進み、米国各地で暴動に発展。食料品店などが略奪に合う。
3.米国政府はインフレ対策として急遽金融引き締めに入り、株価は大幅に下がる。株安は世界に波及。政策的な支援を得る見込みながなくなったEVや再エネ産業はとりわけ大きく値を下げ、グリーンバブル崩壊となった。
4.早くもレームダックとなったバイデン政権は22年11月の中間選挙でも大敗。米国の「30年CO2半減、50年CO2ゼロ」という目標は全く達成される見込みが立たなくなった。
5.22年末のCOP27はエジプトで、23年末のCOP28はUAE(アラブ首長国連邦)で開催される。だがグリーンバブルの崩壊を受けて、ダボス資本家は参加を取りやめ、グリーンウオッシュの祭典では無くなる。COPはもっぱら途上国が先進国に援助の増額を巡る交渉の場となって、南北問題を扱う国連機関であるUNCTAD(国際連合貿易開発会議)と変わり映えがしなくなる。気乗りのしないG7諸国は首脳を派遣しなくなり、メディアの関心もなくなる。
帰結
A) 次期大統領を狙うトランプは連日、バイデン批判を繰り広げる。「インフレを招き国を破壊したのはバイデンのグリーン政策だ。24年にはパリ協定から脱退し、脱炭素政策は全てキャンセルする」。そして24年、その通りのことが起きる。
B) 日本でも政変が起きて、共和党とのエネルギー・環境政策の協調が図られる。エネルギー基本計画は見直されて、土砂災害と人権問題によって人気が凋落した「再エネ最優先」政策は撤廃される。
C) 米国共和党が推薦する科学者が日本の国会にも招聘されて証言を行い、50年CO2ゼロという目標に科学的根拠が無いことを訴え、国民の支持を得るようになる。同目標は政府計画から撤廃される。
3つのグローバル・シナリオのうち、いずれの蓋然性が高いだろうか。
もちろん、他のグローバル・シナリオもさまざまであろう。どのような将来像があり得るだろうか。
そして、政府の計画、企業の事業計画は、あり得る複数の将来シナリオに適応できるものになっているだろうか。
【プロフィール】1991年東京大学理学部卒。93年同大学院工学研究科物理工学修了後、電力中央研究所入所。電中研上席研究員などを経て、2017年キヤノングローバル戦略研究所入所。19年から現職。慶應義塾大学大学院特任教授も務める。