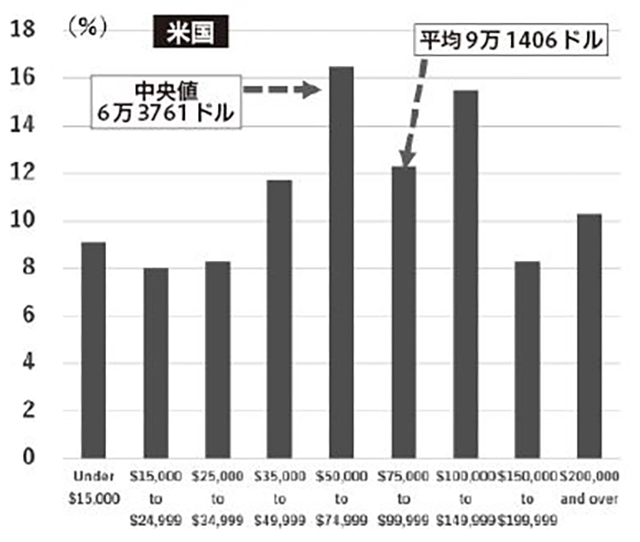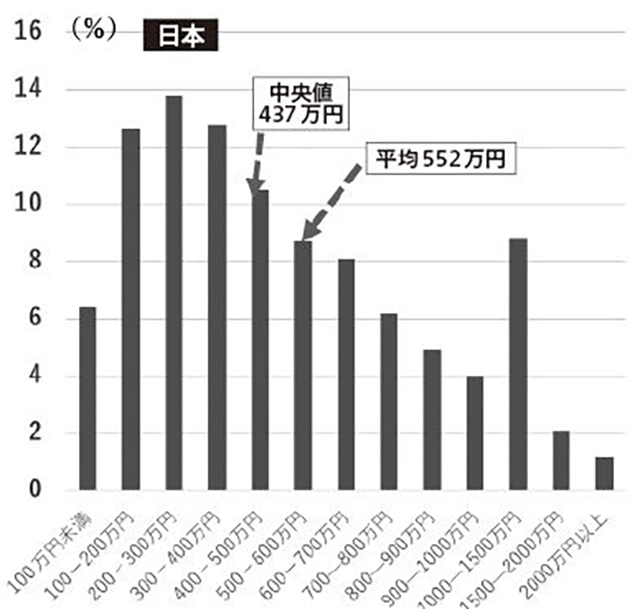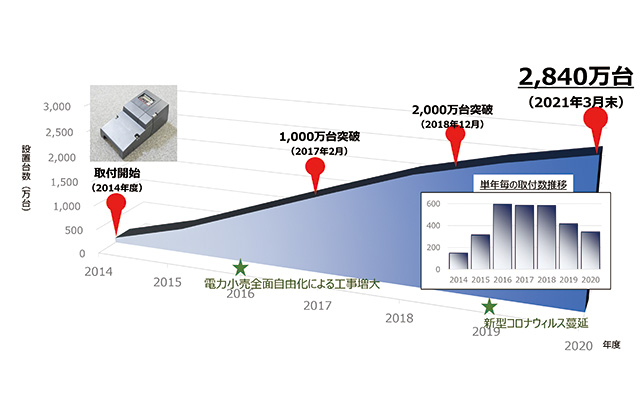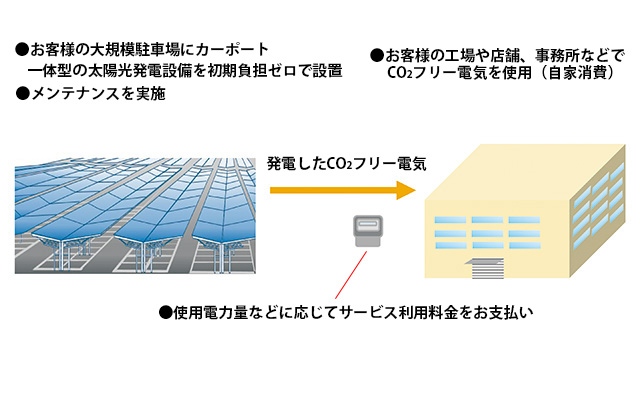矢島正之/電力中央研究所名誉研究アドバイザー
わが国は、2020年10月に、2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。これを踏まえ、政府は、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を作成している。この「グリーン成長戦略」では、14の重要な分野ごとに高い目標を掲げた上で、現状の課題と今後の取組を明記し、予算、税、規制改革・標準化、国際連携などの政策を盛り込んだ実行計画を策定している。また、「グリーン成長戦略」は、「我が国の企業が将来に向けた投資を促し、生産性を向上させるとともに、経済社会全体の変革を後押しし、大きな成長を生み出すもの」と強調し、2兆円規模のカーボンニュートラル基金を創設すると言明している。
「グリーン成長戦略」は、エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業と幅広く産業をカバーしているが、市民の参加というボトムアップのアプローチが言及されていない。しかし、地域密着型の電力会社や日本型シュタットヴェルケを目指す自治体にとって、グリーン成長戦略との関連で、このようなアプローチに対しての政策支援があれば、大きなビジネスチャンスが生まれるのでないだろうか。欧州では、市民によるカーボンニュートラルへの取り組みが進展しており、今回のコラムではその動向について紹介したい。
まず、EUであるが、 2018年12月に発効した「クリーンエネルギーパッケージ」の「再生可能エネルギー指令」は、「再生可能エネルギー共同体」について、「加盟国は、最終需要家、特に家庭用需要家が、最終需要家としての権利または義務を維持しつつ、再生可能エネルギー共同体への参加を妨げるような不当なまたは差別的な条件や手続きに従うことなく、再生可能エネルギー共同体に参加する権利を有することを保証しなければならない」と規定している。これに基づき、加盟各国は、この規定についての国内法化が求められている。
同指令にいう「再生可能エネルギー共同体」とは、次のような法人と定義されている。
(1) 適用される国内法に従い、オープンで自発的な参加に基づき、自律的であり、当該法人が所有・開発する再生可能エネルギープロジェクトの近傍に所在するステークホルダーまたは構成員によって効果的に支配されていること。
(2) ステークホルダーまたは構成員が、自然人、中小企業、または自治体を含む地方公共団体であること。
(3) 金銭的な利益よりも、ステークホルダーや構成員、または事業を行う地域に対して、環境的、経済的、または社会的な利益を提供することを主な目的としていること。
欧州では、このEU指令に先立って、「再生可能エネルギー共同体」の設立の動きがすでに散見される。ドイツでも、そのような動きがあるが、それを支えているのが、手厚い政策支援である。同国では、従来から「エネルギー効率の高い都市再開発」の立案と実施に関して、地方自治体は、KfW(ドイツ復興銀行)へ資金的支援を申請し、これが認められれば、同銀行から費用の65%の助成を受けることができる。2021年4月以降は、都市開発のテーマは拡大され、「モビリティ」、「気候保護と気候変動への適応」、「デジタル化」も含まれるようになった。また、州によっては、 助成の上乗せがある(ニーダーザクセン州では同州開発銀行により20%)。同国では、シューレスヴィッヒ・ホルシュタイン州のボルデルムで「再生可能エネルギー共同体」構想が進展している。
また、1990年に地球温暖化防止のために行動する都市のネットワークとして設立された
気候同盟(Climate Alliance)のドイツ地域のネットワークは、Region-Nプロジェクトにより、2030年までに、地域の省エネポテンシャルを活用するとともに、再生可能エネルギー供給量を100%にし、気候保護を強化することを目指している。このような動きは、地域密着型電力供給事業者に大きなチャンスを提供するとともに、地域の活性化につながることから、わが国でも大いに参考になると思われる。
【プロフィール】国際基督教大修士卒。電力中央研究所を経て、学習院大学経済学部特別客員教授、慶應義塾大学大学院特別招聘教授などを歴任。東北電力経営アドバイザー。専門は公益事業論、電気事業経営論。著書に、「電力改革」「エネルギーセキュリティ」「電力政策再考」など。