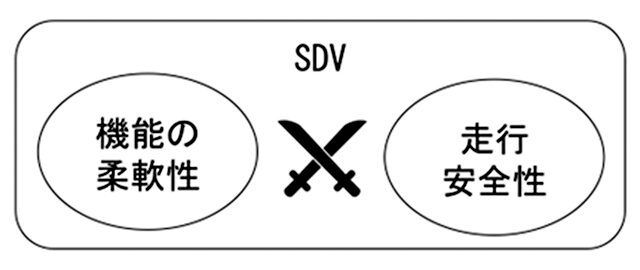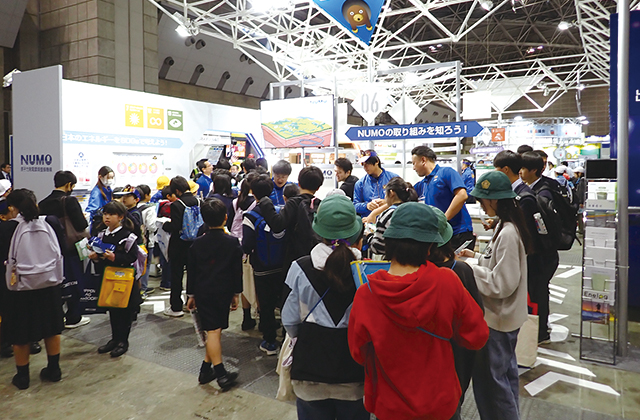NEWS 01:大間原発の基準津波了承 安全対策工事開始に前進も
原子力規制委員会は2024年11月29日、大間原子力発電所の審査で基準津波を7・1mとするJパワー側の説明を了承した。大間原発は出力が国内最大級(138万kW)で、完成すれば世界で唯一MOX燃料だけで運転できる最新鋭の発電所。まさに日本の未来を担う原発と言っていい。
Jパワーはこれまでに6度、安全対策工事の開始時期を延期してきた。基準津波や基準地震動が未策定のままでは、工事に取り掛かれないからだ。ただ大型クレーン設置の基礎工事を事前に進めるなど、工事開始から運転開始までの時間を短くする方針を打ち出している。大間原発は地元にとっても、財政や雇用に影響を与える「最重要課題」(大間町の野﨑尚文町長)だ。
規制委は24年秋、大間原発以外にも浜岡原発と泊原発の基準津波を了承した。どのサイトも審査申請から10年が経過している。もちろん審査の進展は歓迎すべきだが、事業者が地元の同意を得て建設に動く中で、災害時に最大でどれくらいの津波が押し寄せるかの判断に10年掛かる─。行政手続法上の標準処理期間2年を持ち出す前に、常識的に考えて異常ではないか。安全性の重要性は語るまでもないが、これでは民間企業の収益機会や地域の経済活動を制限していると見られても仕方ない。
こうした現状に政治がメスを入れてほしいのだが、それどころではなさそうだ。
着工から16年が経過した大間原発
NEWS 02:第7次エネ基原案を提示 複数シナリオ用い抜本見直し
資源エネルギー庁は12月17日の総合エネ調・基本政策分科会で、第7次エネルギー基本計画の原案を提示した。30年度のエネルギーミックスは維持しつつ、40年度は複数シナリオを用いた見通しを提示した。
40年度に13年度比73%減の方向で検討が進む新たなNDCを念頭に置きつつも、自給率や発電電力量、電源構成、最終エネルギー消費量など各項目に幅を持たせる。電源構成では再エネ4~5割、原子力2割、火力3~4割程度などとした。
今回は、地政学リスクの高まり、データセンターや半導体製造などで電力需要増に転じる可能性にフォーカス。第6次から軌道修正し、第7次では野心的なCN目標は維持しつつ、多様かつ現実的なアプローチを拡大する。S+3Eは、安全性を大前提に、「エネルギー安定供給を第一とし」と表現が変化した。
さらに、「再エネか原子力かといった二項対立的な議論でなく、あらゆる選択肢を追及する」と強調。再エネは引き続き主力電源として最大限導入しながら、特定の電源に過度に依存しないよう、バランスの取れた電源構成を目指す。原子力も「最大限活用する」とし、第6次の「可能な限り原発依存度を低減」という一文は姿を消した。
加えて原子力政策の変更点が、リプレース方針だ。これまでは「廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替えを具体化する」としていたところ、今回は「廃炉を決定した原発を有する事業者の原発のサイト内」と修正。つまり同じ事業者なら廃炉とは別のサイトでの建て替えも可能となる。
エネ庁は24年内にもう一度会合を開き、ミックスに関する複数シナリオや、NDCを実現できなかった場合のリスクシナリオなども提示する予定だ。
NEWS 03:排出量取引制度の論点整理 25年通常国会で法改正へ
26年度に本格稼働する排出量取引制度(ETS)の概要が固まった。内閣官房GX実行推進室は12月19日、ETSの論点の整理案を提示した。制度の基本フレームを書き込んだGX推進法改正案を、25年初頭の通常国会に提出する予定だ。
対象は、直近3カ年平均でCO2の直接排出量が10万t以上の法人で、当面は排出枠を全量無償で割り当てる。発電事業者は、33年度から一部有償割当となる。対象者は毎年度自らの排出量を算定し、排出枠の償却義務量を確保。過不足分は市場で取引し、余剰分は翌年度に持ち越し可能だ。義務未履行の場合は、応分の負担金を支払う。
EUのような強力な規制は避け、排出枠はNDCとリンクさせない方針だ。他方、NDCとの整合性は、削減目標などを掲げる移行計画の提出を毎年度求めることでバランスを取る。目標年度は当面30年とする。
割当量については、エネルギー多消費分野は業種別のベンチマーク方式で算定し、他分野は、基準から毎年一定比率で引き下げるグランドファザリング方式とする。電力会社や石油元売り、そしてガス会社の発電事業についてはベンチマークとなる。ただし、ガス事業自体は直接排出量がそれほどの規模ではないため、別途28年度から化石燃料賦課金を徴収する。
排出枠価格の安定化に向け、上限・下限価格を設定。価格高騰時は、上限価格を支払うことで義務の履行を可能とする。他方、一定期間下限価格を下回る場合は、リバースオークションを実施し需給を引き締める。
ただし、具体的な業種別の割当量や、上限・下限価格の水準は今回示さなかった。規制の強度を左右するこれらの水準は、25年度引き続き専門家を交え検討する。
NEWS 04:電源別発電コストを試算 エネ政策への影響は?
40年度の電源構成比(エネルギーミックス)はどうあるべきか―。資源エネルギー庁は12月16日、その議論の叩き台となる電源種類別発電コストの試算結果を公表した。
注目すべきは、新たな発電設備を建設・運転した際の1kW時当たりのコストに加え、総発電設備容量に占める変動再生可能エネルギー比率が4、5、6割の3ケースについて、統合コストの一部を考慮し算出していることだ。
それによると、事業用太陽光のコストは「4割」のケースで15・3円と全ての電源の中で最も安くなるが、5割を超えると原子力、LNGよりも高くなる。電力システム内に変動再エネが増加するほど、火力の効率的運転が困難となり燃料使用量が増加するためだという。
再エネのコストは安いのか?
一方、21年度に試算した30年度の試算では、コスト優位性が高かったLNGにはCO2対策費を反映。これにより、専焼で20・2~22・2円、水素10%混焼で20・9~23円と、原子力の16・4~18・9円よりもコスト高になるとの結果が示された。
こうした情報が出ると、ともすると世間では電源間の優位性を巡る議論に陥りがちだ。だが、この試算が示すのはあくまでも一定の前提を置いた上での経済性という一面に過ぎない。電力システム全体で安定供給性、環境性をいかに追求するべきかという視点を持ち、今後の政策議論を見守る必要がある。