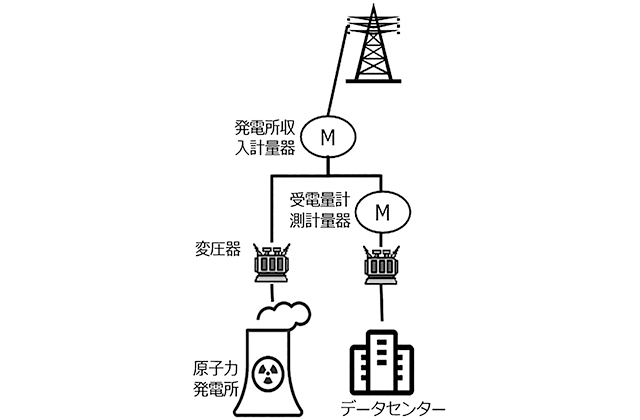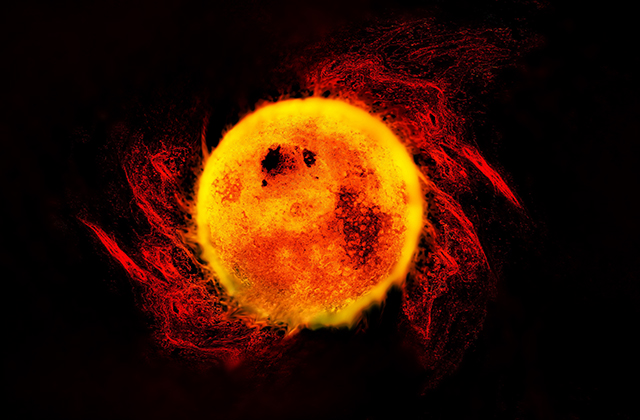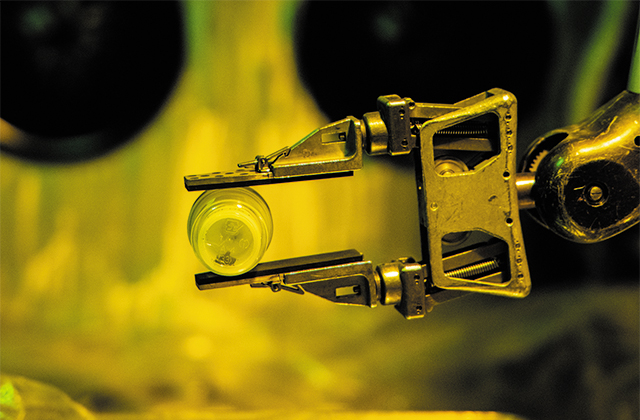【脱炭素時代の経済評論 Vol.09】関口博之 /経済ジャーナリスト
10月、エネルギーの長期見通しに関する恒例の報告が二つの専門組織から出された。国際エネルギー機関(IEA)の「ワールド・エナジー・アウトルック(WEO)」と日本エネルギー経済研究所の「IEEJアウトルック」だが、世界のLNG需給の将来展望にはかなりの開きがある。
IEAは2030年までにLNGの供給能力が現在の50%近く増える一方、需要は30年でピークに達し、その後もほぼ横ばいと予測。このため供給過剰になり価格も低下すると見る。そして各国の脱炭素政策が公約通り進められるとすれば、既存生産設備と既に投資決定済みのプロジェクトだけで50年までの需要は賄えると試算する。
さらにIEAが脱炭素化という目標から逆算して描く「ネットゼロシナリオ」では50年の需要は急激に細り、今後の新規投資案件は資金回収すら難しくなるという姿が描かれている。

一方、エネ研の長期見通しでは、脱炭素技術が進展するシナリオでさえ、50年の世界のLNG需要は現在の4億tと変わらないと推定。既存設備の減耗も考えれば、今後も毎年1000万t分の生産能力投資が必要だとする。
かたや「生産増強はもう打ち止めに」と言い、他方は「安定的な投資継続を」と提言する。ともに権威ある機関だけに業界は当惑するかもしれない。
言うまでもなく日本にとってLNGはカーボンニュートラルへの「移行期」にとりわけ重要な役割を果たす。IEAが予測するように供給過剰の時代が来るのなら慌てて動かなくてもよいかもしれないが、だとしても大半をスポットや短期買いに頼るのは危うい。安定調達のためには長期契約がやはりベースだ。ただ国内でもガス火力発電へのLNG需要は再エネ・原子力を最大に入れた後のいわば調整弁になるので、先行きが見極めづらい。電力ガス業界からは「さすがに20年契約では取れない」という本音も聞こえてくる。
一方でカタールのガス田拡張で欧米メジャーや中国はプロジェクトに出資もし、生産の一定量を25年にわたって引き取る契約を結ぶ。日本が取り負けることはないのか。
個別企業ではリスクを負い切れない。LNGのリポートを作成したエネ研の橋本裕上級スペシャリストは「東南アジアの新興国とタッグを組んで共同購入などを」と提言する。需要をプールすることで量がまとまる。仮に日本の国内需要が見込みを下回った場合でも新興国側に転売できればバッファーになる。新興国の需要自体が伸びるとすれば長期契約でも座礁資産化は避けられる。仕向け地条項の廃止・弾力化を求める必要はあるが、輸出国側にしても無制限の仕向け地変更よりは受け入れやすいはず、と橋本氏は見る。
スキームには国の支援があればなお有効だろう。民間ベースの契約を両国政府がエンドースするといった形はどうだろう。日本が提唱し11カ国で形成したアジアゼロエミッション共同体(AZEC)の活用もあり得るのではないか。まずは具体案件の開拓から。アイデアは民間が出し、国を動かしていく、こうした官民連携が望ましい。
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.01】ブルーカーボンとバイオ炭 熱海市の生きた教材から学ぶ
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.02】国内初の水素商用供給 「晴海フラッグ」で開始
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.03】エネルギー環境分野の技術革新 早期に成果を刈り取り再投資へ
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.04】欧州で普及するバイオプロパン 「グリーンLPG」の候補か
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.05】小売り全面自由化の必然? 大手電力の「地域主義」回帰
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.06】「電気運搬船」というアイデア 洋上風力拡大の〝解〟となるか
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.07】インフレ円安で厳しい洋上風力 国の支援策はあるか?
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.08】これも「脱炭素時代」の流れ 高炉跡地が〝先進水素拠点〟に