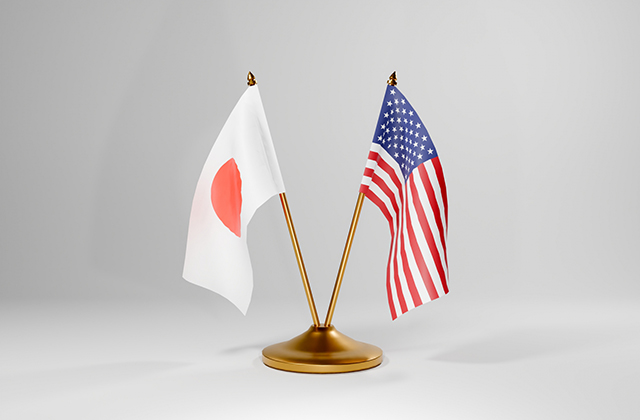飯倉 穣/エコノミスト
1、迷走が続く
石破首相の所信表明演説があった。デフレ脱却し、経済あっての財政という経済運営で賃上げと投資が牽引する成長型経済を目指すと述べた。報道もあった。「所信表明演説 首相「生産性上げ賃金増 成長型経済 投資に力点」(日経24年10月5日)、「経済対策でデフレ脱却、物価上昇を上回る賃金増加、起業支援などを掲げたが、岸田政権の路線承継で、独自性は乏しい」(朝日記事同)。そして選挙となった。
党首討論等で、この30年間の経済停滞を嘆き・不満・攻撃・打開の言葉が飛び交う。従前は、金融政策、財政の発動、近時は、物価上昇見合いの賃上げ、中小企業の賃上げ支援、消費税引き下げ・廃止等々の主張が聞こえる。与党以上に野党の主張を聞いても、働く人の疑心暗鬼が消えない。財源沈黙且つ意味不明なバラマキ継続ばかりである。
政治万能の巧言令色と日銀の国債買取頼りの経済運営が、国民経済をたよたよとした。各党の主張は、マクロ的に論拠薄弱で、次の経済の姿が浮かばない。報道も選挙で経済問題を取り上げるが、財政破綻・論理不知等の本質問題回避である。今後の経済・企業行動を、石破総理の所信表明演説における経済政策から考える。
2、石破政権発足と経済政策
(冷ややか且つ投げやりの起草)
所信表明演説の内容は、納得と共感の政治を強調する。政治家として「すべての人に安全と安心を」を掲げ、ルールを守る、日本を守る、国民を守る、地方を守る、若者・女性の機会を守ると続く。この5本柱で日本の未来を創り、そして未来を守るという。経済では、「デフレ脱却」を確実にする。「経済あっての財政」で経済財政運営を行い、賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現する。イノベーション促進で高付加価値創出や生産性の向上で、GDPの5割を占める個人消費を回復させ、消費と投資を最大化する成長経済を実現する。それでコストカット型経済から高付加価値創出型経済へ移行する。また「物価に負けない賃上げ」を述べる。物価上昇を上回る賃金上昇を定着させる。賃上げと人手不足緩和の好循環に向けて、一人一人の生産性を上げ、付加価値を上げ、所得を上げ、物価上昇を上回る賃金の増加を実現すると。賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現を強調する。個別政策で、脱炭素・最適エネルギーミックス、GX取り組みの加速、科学技術等フロンテイアの開拓推進、スタートアップ支援策強化、貯蓄から投資で資産運用立国(投資大国)、地方こそ成長の主役で地方創生の交付金を当初予算ベースで倍増する等々である。(石破首相の所信表明演説10月5日参照)
(経済政策をまとめれば)
要すれば、経済活力で①物価を上回る賃上げでデフレ脱却、②個人消費回復・投資の最大化で経済成長、③貯蓄から投資で資産運用立国・投資大国実現、④省エネ・再エネ・原子力発電活用でエネ確保、⑤イノベーションとスタートアップ支援で高付加価値創出、⑥地方創生交付金で地域経済活性化等を取り上げる。相変わらず財政・金融活用が大事な実現手段のようである(補正予算13兆円示唆:日経10月16日)。これらの事項は、過去アベノミクスや新しい資本主義で幾度も重点施策として取り上げられながら、いずれも実効性に乏しかった。勿論財政・金融政策一体の財政拡大は、些か経済を膨らますと同時に、国債残高を著増させ、今日の金融政策の足枷となる。見果てぬ夢を語る国風なのであろうか。
3、アベノミクスとは何であったか
アベノミクス(評価対象13~19年)は明瞭だった。3本の矢(大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略)である。そして思い違いであった。2012年以降は、景気の戻りの時期だった。その間の政策は、幾つか改善に力を貸したかも知れないが、流れで見れば、日本経済(経済均衡)改善とは評しにくい。やってもやらなくてもさほど変わりないか、問題をドロドロ化させた。財政の膨張で、国の借金を増加させた。金融緩和がそれを手助けする。企業経営は、自立自営の活力を低下させ、次の方向の葛藤に明け暮れる。
4、新型コロナ感染ショック
そこに新型コロナ感染ショックである。感染症の防止は最優先事項で、一応の規模で移動禁止の措置となった。GDPに対する影響は、1%程度と推測された。サービス業中心に、業務停止で、支援が適切な状況となる。影響を受ける人は、50~70万人程度で一定期間の給付が必要だった。必要額は、貸付を除けば20兆円程度(当方試算)である。政府は、100兆円を超す巨額な補正予算を組み、吟味無きバラマキに走る。綿製マスクが揶揄された。同時に緊急時に必要な施設等の不足が目立った。
5、岸田政権が登場し、新しい資本主義の言葉が舞った。
中身は、未定だった。到達点の「経済財政運営と改革の基本方針2024」(24年6月)は、賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現を副題にしている。今を、デフレから完全脱却し成長型経済実現の千載一遇のチャンスと見た。賃上げを起点とした所得と生産性の向上が移行の鍵で、日本を成長型の新たなステージに移行可能と考える。故に本年、物価上昇を上回る所得の増加を確実に実現し、来年以降物価上昇を上回る賃上げ定着と決意を述べた。ジョブ型人事指針、スタートアップ育成5か年計画、資産所得倍増プラン・資産運用立国実現プラン、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針などを呈示する。お上対応である。賃上げはしたが、「健全な経済均衡」回帰に必要な問題の解消にほど遠い。