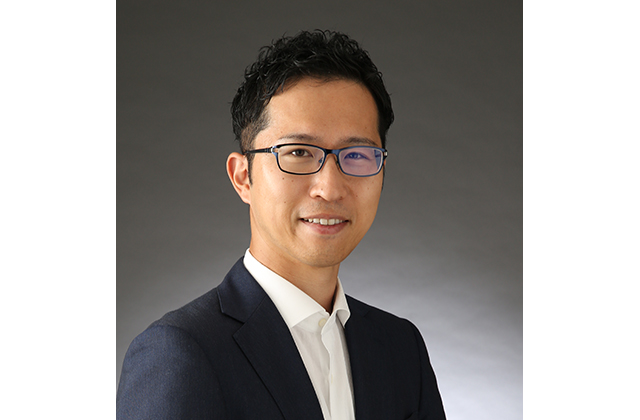【エネルギービジネスのリーダー達】齊藤 洸/伊東ガス社長
静岡県伊東市で90年以上の歴史を持つ伊東ガスの6代目社長に就任した。
ガスという既存事業を大切にし、地域の魅力を高める新規事業で持続的な成長を目指す。

城ケ崎海岸など雄大な自然に囲まれ、日本有数の温泉地として名高い静岡県伊東市。今年3月、この地で1932年から都市ガス事業を手掛ける伊東ガスの6代目社長に就任したのが齊藤洸氏だ。
温泉旅館など宿泊施設が多く、ガス販売量の半分近くを商業用が占める。新型コロナウイルス禍では、多くの宿泊施設が閉館した影響で商業用の販売量が半分程度まで落ち込んだ月もあったが、観光需要の回復でだいぶ持ち直してきた。より深刻なのは家庭向けだ。市街地では空き家が年々増え、メーター取付件数は、年間50~100件減少し、足もとでは1万件を切るなど、販売量が減り続けている。
収益基盤を多様化 まずは水事業に参入
入社当時は、何ら手を講じられないまま、少しずつ販売量が減り続けることに強い危機感を抱いた。それと同時に、プロパンガス販売を含めると約1万5000軒という顧客基盤があり、新規事業にチャレンジする土壌があることに高いポテンシャルも感じたという。
そこで打ち出したのが、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を進めながら、新規事業を新たな経営の柱に育てる戦略だ。その第一弾として、22年に蛇口直結型「電解水素水生成器」のサブスクリプションサービスを開始した。
ガス事業の繁忙期は冬。反対に水事業は夏場が繁忙期になるため、両利きの経営にはぴったり。実際、ウォーターサーバーの宅配サービスに取り組む同業他社は多い。ただ、それでは注文に応じて配送する必要があり、新たな人員確保が求められる。
これに対し、現行の従業員のみで収益拡大が期待できるビジネスモデルとして着目したのが、一度機器を取り付ければ、あとは年に1度カートリッジを交換するだけという、電解水素水生成器のサブスクサービスだった。「ペットボトルの水を購入するよりも安価でおいしい。そして、海洋プラスチックごみ問題の解決に繋がるサステナブルな事業」(齊藤氏)として、今後10年でガスに並ぶもう一つの経営の柱に育てていく考えだ。
新規事業を立ち上げるに当たって欠かせなかったのが、新たな顧客管理システムの開発だ。既存の基幹システムはガスに特化しているため、新規事業に伴い拡張しようとすると費用も時間もかかってしまう。そこで、サイボウズが提供するノーコード開発プラットフォームである「キントーン」を使い、自らYouTubeなどで勉強しながら、管理業務や社員間の情報共有を全てスマートフォンで完結できるシステムを構築した。
新事業で得たDXの成果は、今は他の分野にも及んでいる。これまで紙で管理していた運転日報の記録や、発注・出荷管理などの社員同士の情報伝達もシステム上で行えるようにしたことで、業務効率を格段に向上させることができた。 さらに今年からは、社員のシステム構築スキル習得も進めながら、人事・労務管理のDX化にも乗り出している。宿・日直簿や配属、資格、人事評価といった、これまで紙で管理していた情報をクラウドシステムに入力し情報を集約。紙による管理を廃止してもクラウド上で全ての社員情報を閲覧可能にした。
働きがいのある社風へ 社長自らが挑戦
今後、リフォーム事業や伊東市の魅力を高めるような第三、第四の新規事業を立ち上げることも念頭に置く。空き家事業への参入を見据え、現在は、宅地建物取引士の資格取得に向けて猛勉強中。「ガス会社にとって、空き家問題は大きな経営課題。空き家を活用した民泊事業をはじめ、街づくり会社を目指していきたい」と、会社の将来の在るべき姿を見据えている。
もともと、会社を継ぐつもりはなかったが経営には興味があった。大学卒業後は日本生命保険に入社し、在職中にMBA(経営学修士)を取得。さらに経営に関するスキルを高めようとアクセンチュアに転職した矢先、先代社長の父から後継者のなり手がいないなど事業継続への不安を聞き、「今まで学んできたことを還元できるのであれば」と、跡を継ぐことを決めた。
自ら業務システムを開発し、新たな資格取得にも挑戦する―。それは、「社長が率先して頑張ることで社員のやる気を引き出す社風にしていきたい」との思いからだ。社員にとって会社で働くことが幸せか、社会への貢献を実感できるか。そうした気持ちを大切にしていこうと、管理職研修や新たな人事評価制度についても試行錯誤している。
「成長し続ける魅力ある会社でありたいし、お客さまや地域、社員から愛される会社にしていきたい」と齊藤氏。挑戦はまだまだ続く。