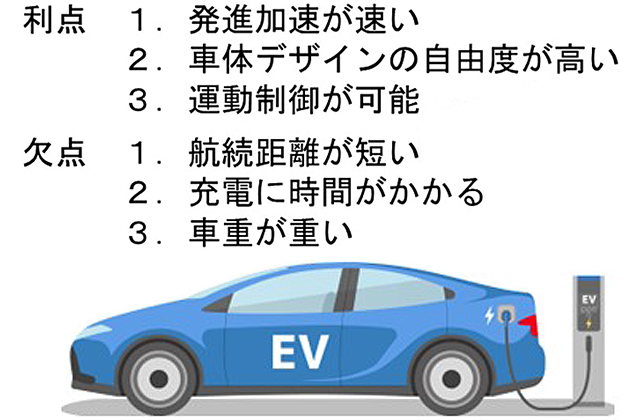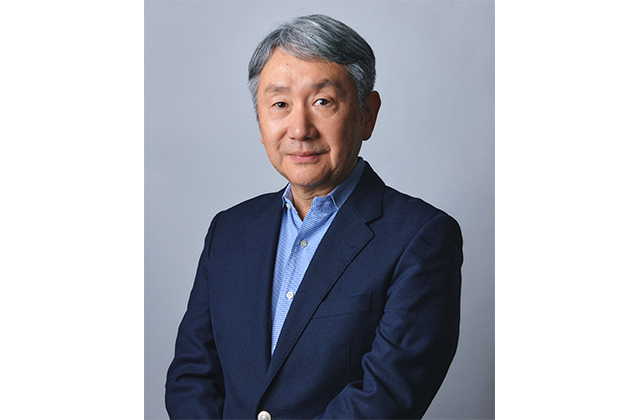<メディア人編> 大手A紙・大手B紙・大手C紙
中国ロゴ問題を巡り、甘利氏が河野氏を痛烈批判。
総裁選に向けて河野氏はどう動くのか。
─昨年1月に始まった電気・ガス料金に対する補助金が5月使用分をもって終了した。
C紙 朝日が一面で報じていたが、他紙は2面や3面での扱いだった。読者層が高齢化しているので、「くらし情報」として掲載した社が多かったのだろう。補助金の是非は丁寧に取材すべきテーマだが、深く迫った記事は見ない。
B紙 5月22日には、共同通信が「6月電気代、最大46・4%上昇補助金終了、再エネ賦課金負担増」との記事を掲載した。46・4%という上昇幅は衝撃的だが、これは前年同月比での数字。なぜ前月比で報じなかったのか。事業者からは不満の声が上がっていた。
A紙 夏に向けて電力需要が高まる中で、補助金終了のタイミングは最悪だ。料金明細を見た時に驚く人は多いはずで、今後は「電気代、なぜ上がった?」というQ&A方式の記事を目にするかもしれない。
反原発が執筆の足かせに エネルギー記事はウケない
C紙 民放は「電気代が上がって大変だ」とあおり立てる報道が多かった。「なぜ上がるのか」という視点が求められていると思うのだが。
B紙 第7次エネルギー基本計画の議論中で腰を据えた記事を書きたいが、連載記事でも全てをカバーするのは至難の業。エネルギー問題はとにかく複雑で難しい。FIT(固定価格買取制度)とFIP(フィードインプレミアム)の違いを書いても、デスクが理解できるか不安だ。
A紙 エネ基の議論の中心は、電力需要増と脱炭素。この2点を前提にすると、朝日・毎日・東京は、原発を推進できない点が記事を書く上での足かせになっている。
B紙 A紙はリベラル系だが、書く立場としてはどう?
A紙 正直、かなり苦しい(笑)。一方で保守系は、再生可能エネルギーを叩く方向に走りがち。原子力VS再エネという構図にはまると現実的な記事が書けなくなる。
C紙 GX(グリーントランスフォーメーション)基本計画で原発新増設をうたっても、実現できそうなのは1、2カ所だけ。「原発回帰」など象徴的なフレーズが独り歩きしがちだが、こうした実情もセットで伝える必要がある。特にエネルギーはいろいろな立場の人が、それぞれの理想を語っているから……。
B紙 産経も原発の活用を訴えるが、少し詳しい人なら「そうは言っても、資金面はどうするの」と思っている。表面的な記事を書くほど、現実との乖離が目立つ。
A紙「データセンターで電力需要増」と言われても、読者はピンと来ない。人口減の地方ならなおのことだ。遠い話のように思えて、とにかくエネルギーの記事は読者にウケない。
─再エネ規制改革タスクフォース(TF)資料へのロゴ混入問題で動きがあった。内閣府は6月3日に調査結果を公表。翌日には河野太郎デジタル相が同TFの廃止を明言した。
C紙 河野氏の私的な懇談会が公的な審議会並みの権限を持っていたわけだが、同じ神奈川県を地盤とする自民党の甘利明前幹事長がずいぶんと怒っている。6月4日の産経によると同日、「(エネルギー、情報通信の政策を)何の公的権限もオーソライズされない人が決め、関係省庁に指示を出すことはおよそ考えられない」、さらには「とんでもない大臣が来たら暴走する」とまで語ったとか。
B紙 裏ではもっと激しかったらしい。河野氏が地元の例会で自分が描かれたまんじゅうを配った。それを見た甘利氏は「そんなの食べたら、お腹壊すよ」とボソリ(笑)。
C紙 この2人は、いわば原子力と再エネのボス同士。ここまでバチバチにやり合うのは久しぶりだ。
YKKに似てきた「小石河」 蓮舫氏は「惜敗」がベスト?
C紙 9月の自民党総裁選への影響もある。「腕力」という武器を封じられた河野氏がどんな一手を打つのか。小泉純一郎元首相のように、よりポピュリスト的な手法に出る可能性もある。
A紙 かつて小泉元首相は「YKK」(山崎拓氏、加藤紘一氏、小泉氏)を「友情と打算の二重構造」と評したが、「小石河連合」(小泉進次郎氏、石破茂氏、河野氏)も同じ匂いがする。ただ河野氏は次の内閣では要職が予想されるので、今回はあまり動かないかも。
B紙 岸田文雄首相としては、国会への憲法改正原案の提出を狙っていた。いくら安倍派などが「裏金」問題への対応で「岸田憎し」といえど、党の悲願達成に向けて動き出した総裁を引きずり降ろすわけにはいかない。だが政治資金規正法改正案の審議への影響を考慮し、原案提出は見送りに。総裁選に向けた政局の季節がやってくる。
B紙 党が窮地に陥る中で総裁選に手を挙げる人はいるのだろうか。若手を中心に「岸田さんでは選挙に勝てない」という声は出るだろうが、「岸田さんに泥をかぶってもらいたい」という議員も多いはず。
C紙 ちなみに、9月には立憲民主党の代表選挙もある。泉健太代表を交代させたい勢力にとっては、7月7日の東京都知事選で蓮舫氏が「惜敗」するのが望ましい。勝利すれば「泉降ろし」の理由にならず、大敗なら党の勢いが失われてしまう。とはいえ、蓮舫氏は敗れたとしてもすぐに衆議院へ鞍替えるのだろうが。
─エネルギー政策では、河野氏も立民も期待できない。