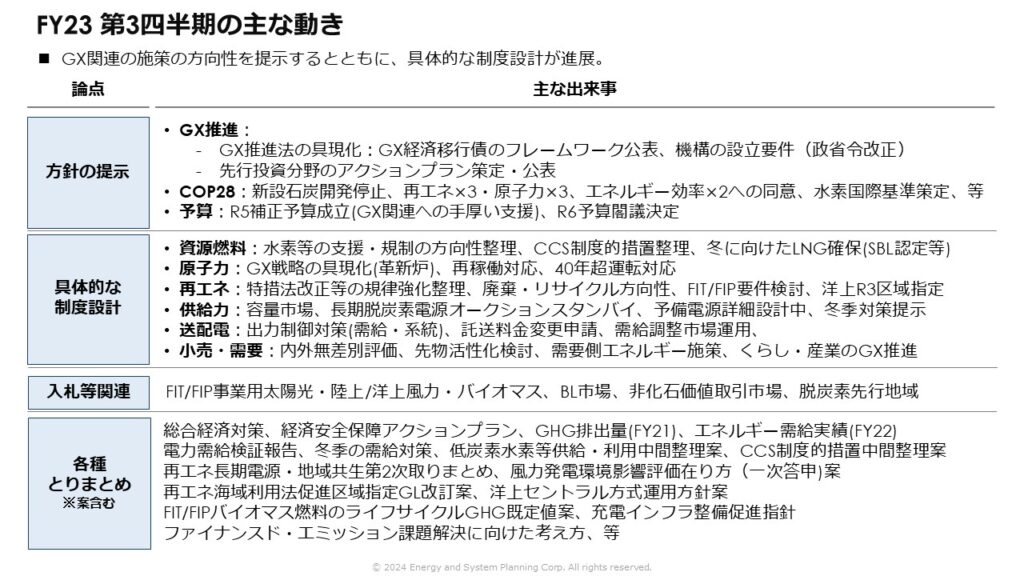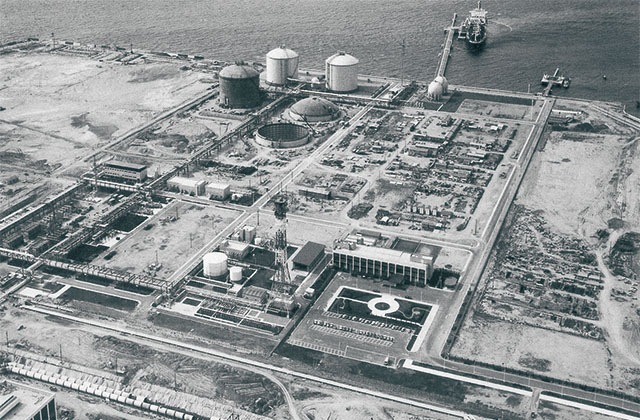【東京電力ホールディングス/世界で初めてペロブスカイト太陽電池が高層ビルで発電】
東京電力ホールディングスは、建設中の高層ビル「サウスタワー」(東京・内幸町)で積水化学工業が開発したフィルム型ペロブスカイト太陽電池(PSC)を設置する。従来の太陽電池は、耐荷重や風圧への対応、高額な更新コストなどの課題があり高層ビルなどでの設置が進んでいなかったが、次世代の太陽電池であるPSCは、「薄い」「軽い」「曲げられる」などの特徴を生かし、技術的・経済的な課題を解決できる見込みとなった。サウスタワーでの太陽電池の発電容量は定格で1000kW超を計画しており、実現すると世界初の「PSCによるメガソーラー発電機能を実装した高層ビル」となる予定だ。都心部で導入が限定的な太陽電池を飛躍的に拡大できるものと期待される。
【積水化学工業/ペロブスカイト太陽電池などの技術で社会課題の解決に寄与】
積水化学工業は2023年11月15日、中期経営計画「Dri-ve 2.0」の進捗と社会課題の解決に寄与するイノベーションについて発表した。ESG経営基盤強化を土台に、新事業領域の創出を目指す戦略的創造と着実な成長を目指す現有事業強化に取り組む。戦略的創造では、ペロブスカイト太陽電池の30cm幅でのロール・ツー・ロール製造プロセスを構築。発電効率15%と耐久性10年相当も達成した。25年の事業化を目指し、東京都の下水処理施設や大阪・関西万博などで開発・実証が進行中だ。今後、1m幅での製造プロセス確立や発電効率と耐久性のさらなる向上を目指す。COP28ではプレゼンを実施。エネルギー安全保障の観点からオールジャパンで推進していく方針だ。
【環境・省エネルギー計算センター/業界初のCASBEE―不動産セルフチェックシステムを提供】
建築物の省エネ計算やBELS・CASBEEの環境性能評価などを手掛ける環境・省エネルギー計算センターは「CASBEE―自己査定システム」を開発した。査定したい不動産の情報を入力すると、CASBEE―不動産の評価基準達成の可否や該当ランクを確認できる。CASBEE―不動産は既存の建築物が環境配慮をしているかどうか4段階で評価。投資家や金融機関、不動産会社など不動産マーケット関係者が参考にする指標だ。同センターの尾熨斗啓介代表取締役は「CASBEEの認証件数は年々増えている。査定前に取得可否やランクの確認をしたいとのリクエストも多く、今回のシステムを開発した。同システムの提供で、スムーズな認証取得に貢献していきたい」と語った。
【レゾナック/ホテルに低炭素水素の供給開始】
レゾナックは、生産過程のCO2排出量を最小限に抑えた「低炭素水素」を、川崎キングスカイフロント東急REIホテルに正式に供給開始した。日本で唯一、家庭ゴミから出る使用済みプラスチックを原料とした低炭素水素であり、商業施設での利用は国内初だ。生産は2015年、環境省の「地域連携・低炭素水素技術実証事業」での取り組みに始まり、18年から同ホテルに供給、22年に実証が終了していた。同社はこの水素生産方法で、循環型社会の構築に貢献する構えだ。
【IHI/大容量水素再循環装置 航空機用に開発】
IHIは、世界最高レベルの水素循環量を実現する大容量再循環装置となる、電動水素ターボブロアを開発し、実証運転に成功した。電動水素ターボブロアは、燃料電池発電時に未反応のまま排出される水蒸気を含む大量の水素を回収し、燃料極に再循環する装置。独自開発のガス軸受超高速モーターを採用することで、大容量化、小型化、軽量化を実現した。航空燃料電池向けに使用する目的で開発し、今後は大出力化が期待される燃料電池モビリティーにおいて、船舶や大型トラックなどの開発にも貢献する。
【LIXIL/窓の新事業戦略発表 エネルギー効率向上】
LIXILは窓・ドアブランド「TOSTEM」の100周年にあたり、窓の新事業戦略「GREEN WINDOW」を発表した。環境負荷を低減する地域に最適な窓と定義し展開する予定だ。窓の断熱性能を高めることで、冷暖房によるエネルギー効率が向上。CO2削減に大きく寄与する。また原材料の調達から製造、流通、使用、廃棄までのライフサイクル全体でのCO2削減を目指す。原材料としてリサイクル素材を使用し、長寿命化とリサイクル性を考慮した設計を行うなど、責任ある資源の使い方を推進していく方針だ。
【日本冷凍空調工業会/冷媒の最先端技術を集めた展示会開催】
日本冷凍空調工業会は2023年12月、HVAC&R JAPAN 2024の発表会を開いた。開催期間は2024年1月30日から2月2日までの4日間で、会場は東京ビッグサイト。12月11日に来場者受付を開始した。この展示会は、国内唯一の冷凍・空調・暖房機器産業の専門見本市として2年に一度開催されており、今年で43回目を迎える。東京大学公共政策大学院の有馬純教授の基調講演をはじめ、東京ガススマートエネルギーセンタ―(東京都江東区豊洲)の見学会などのイベントも併催。ZEBやBEMSといったエネルギーマネジメント技術やIoT・AIを活用した最新の省エネ製品、システムを展示する。国内外合わせて約200社が出展し、世界トップ水準の省エネ、冷媒技術が集結する。
【Looop/行動変容とピークシフトを促す料金プランが好調】
Looopは2022年12月1日から電力小売事業「Looopでんき」において、料金プラン「スマートタイムONE」を提供している。30分ごとに変わる日本卸売電力取引所(JPX)価格に連動したプランだ。太陽光による発電量が多く市場価値が下がる日中の電力使用を促し、需要が増えて価格が上がる夕方に使用を控えるといった、電気料金の変動に合わせた行動変容によるピークシフトを実現する。ユーザー数も順調に増加。同プランの導入により、再エネ電力の供給がより当たり前になることを目指す。
【大阪府ほか/府内の建物をZEB化 大学キャンパスから推進】
大阪府と大阪大学、ダイキン工業は、府内のZEB化推進に係る連携協定を締結した。大阪府は2023年7月に「今後、新築する府有建築物は、原則ZEB Readyを目指す」方針を決定している。大阪大は、箕面キャンパスでZEB Oriented棟を達成するなど、ZEB 化を推進している。ダイキンは、ZEBプランナーの実績でZEB 化に寄与していく。
【ENEOSグローブほか/CNLPガスの売買契約 国際団体認証で炭素減】
LPガス元売大手のENEOSグローブは、大丸エナウィン社にカーボンニュートラルLPガスを販売する。大丸社は、大阪など西日本を中心にLPガス販売、ミネラルウォーター、リフォーム事業などを手掛けている。エネグロは、国際NGO団体が認証したカーボンクレジットをオフセットすることで、実質的にCO2排出をゼロにする。
【商船三井・九州電力/石炭船「苓明」が運航 LNG燃料でSOX等削減】
商船三井と九州電力が建造した、LNGを主燃料とするパナマックス型石炭専用船が「苓明」と命名され、運航を開始した。商船三井が運航し、九州電力の苓北発電所向けに海外から石炭を輸送する。LNGは従来の船舶燃料油に比べて、CO2は約30%、SOXは約100%、NOXは約80%の排出削減が見込まれる。燃料は陸上のLNG出荷設備から直接供給するShore to Shipと、LNGバンカリング船によるShip to Shipでの供給も想定している。両社は、今後も安定した燃料輸送の継続と環境負荷低減の両立に取り組む。