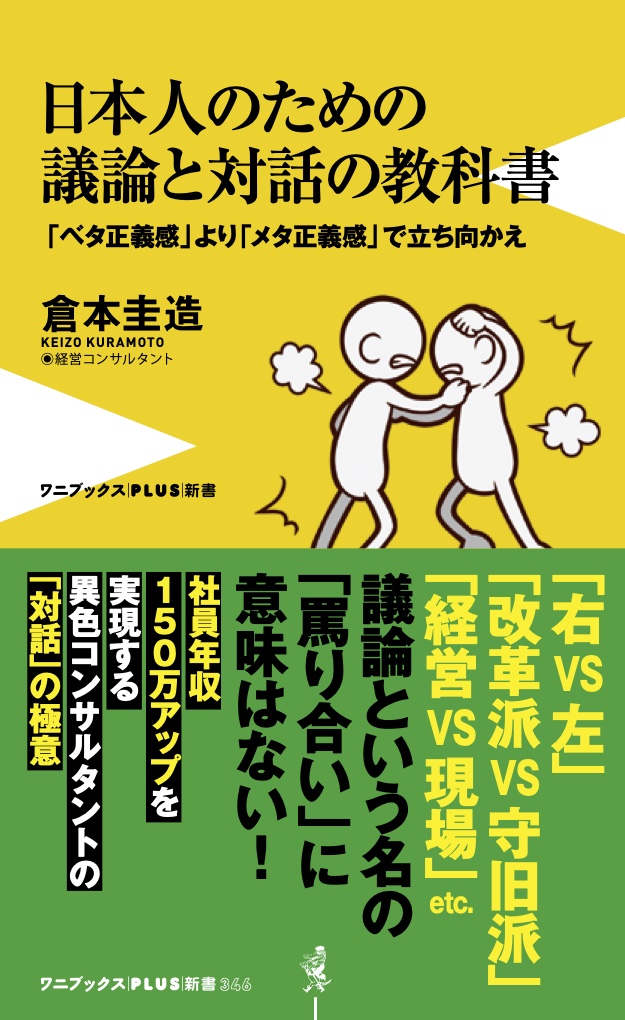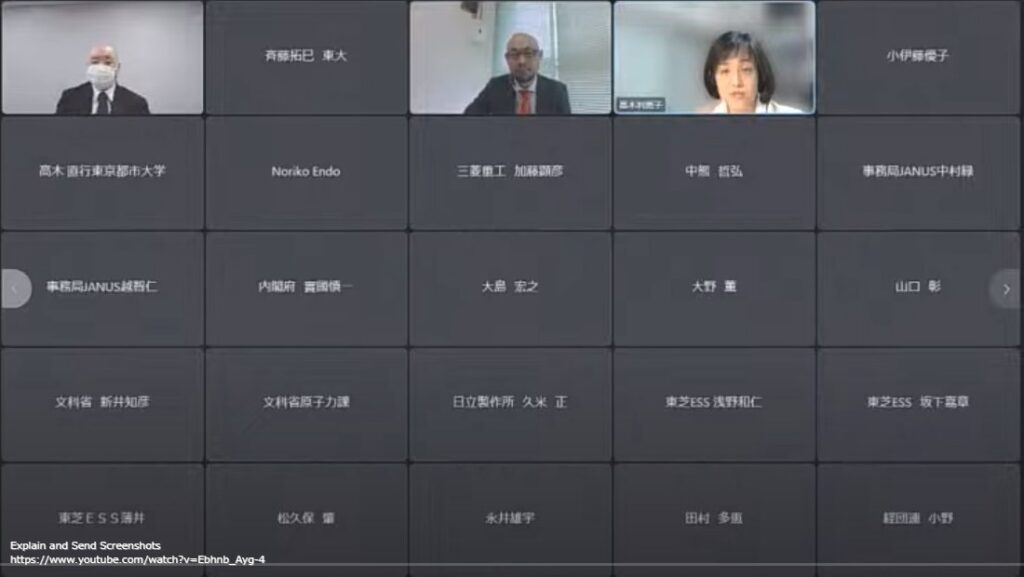エネルギー大手の日本瓦斯(ニチガス)が現在直面するエネルギー危機を乗り切り、来るべきカーボンニュートラル社会、DX(デジタルトランスフォーメーション)時代への対応を視野に、経営陣の刷新に踏み切った。5月2日付で、和田眞治社長が代表権のない取締役会長執行役員に退き、後任社長には柏谷邦彦・代表取締役専務執行役員コーポレート本部長が就任した。また、元東京電力出身の吉田恵一・専務執行役員エネルギー事業本部長が代表取締役に昇格。これにより、渡辺大乗・代表取締役専務執行役員を加えた3人が代表権を持つことになった。
和田会長と柏谷社長は6日、記者会見を行い、DXを機軸に地域社会のスマートエネルギー供給を担う新たなビジネス展開に向けた意気込みを表明するとともに、新体制下での経営方針に言及した。会見の具体的な内容は次の通り。
 会見する柏谷社長(左)と和田会長
会見する柏谷社長(左)と和田会長
柏谷 カーボンニュートラルや災害の激甚化、そしてコロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻等などによって、今までのように上流から下流まで一貫してエネルギーが安定的に流れてくるという前提が、当然のものではなくなった。大きく変化する経営環境の中でこれからの地域社会に最も必要なのは、再生可能エネルギーやEVの利用を前提としながら、災害時でもエネルギーを強靭に、あるいは自立的に供給できるようなレジリエントな分散型エネルギーシステムを構築していくことだと考えている。この課題に対して、当社グループでは従来のガスや電気を仕入れて販売するという事業モデルから脱却し、電気とガスをセットでお客さまに提供することを前提に、太陽光や蓄電池、EV、ハイブリッド給湯器など分散型エネルギーの設備を供給する。各家庭のスマートハウス化、そして大きなスケールではスマートシティー化に向けて、当社自身が地域社会に対し最適なエネルギーを供給できるようなエネルギーソリューション事業へと進化し、新たな挑戦を進めていくステージにある。
今、この局面においては私が適任と判断をされたと理解している。この会社にはいろんな特定の分野において私より優秀な人がたくさんいる。私の経験が不足している、あるいは知見が足りないところは、しっかりした現場のリーダーたちがいるので、その人たちと協力をして、さらに新しい発展、成長のために、前を向いて全力で疾走していく。和田会長は代表権を返上して、次のリーダーシップの体制に全面的にサポートする。取締役会には残るが、新しい代表取締役3人体制で思い切って前に行くようにというメッセージをいただいている。
和田会長「これ以上のタイミングはない決断」
和田 長年、社長職をどう引き継いでいくかということを考えてきた中で、状況、環境、それから人的リソースの体制も含めて、これ以上のタイミングはないということで決断した。柏谷から話がありましたけれども、日本瓦斯67年間の「成功体験との決別」という意味だ。LPガス業界では、プライベートカンパニーの創業家がずっと経営をやってこられるという体制が主流。それに伴ってトップがなかなか辞めないというケースがあって、和田がこのままずっといくんじゃないかと思う関係者が多かったようだが、老害といわれる前に辞めようというのはずっと考えていた。おそらく、このタイミングでは私が率いた時代の成功体験が新しい挑戦の足かせになるんだろうなと。代表権も返上しないと、また院政とかいわれてしまうので、代表権を返上して名実ともに新たな代表取締役3人体制に当社は移るということの表明だ。
5月号のエネルギーフォーラムで、さいたま市がエネルギー事業版のスマートシティーを目指して、第1歩が出ているという記事が出ていたが、私どもまさにそこへ向かって新たなソリューション事業を展開していく。エネルギー事業者がさまざまなシェアリングエコノミーによって地域社会に新たな貢献の形を目指していくところまできた。このタイミングでの引き継ぎのタイミングは、自分なりによかったなと、あとは静かに横からサポートしていこうと思っている。
――LPガスの需要は今後、どうなっていくと考えているか。
柏谷 脱炭素という観点では、化石燃料全体がこれからマーケットとしては縮小、減少するということは、ここは避けられないと考えている。ただ、この2050年にカーボンフリーになっていく社会の中で、LPガスが果たす役割は非常に大きい。地域分散型エネルギーには非常に適した事業形態で、LPガスの容器は標準家庭であれば2カ月ほどのエネルギーのストックになる。ここに、今後、蓄電池やEV、そして太陽光発電などが加わることで、LPガスのインフラとしての役割は重要だ。今後も都市ガスエリアの外部ではLPガスが主力のインフラになると考えている。
和田 結論をいえば、LPガスはなくならない。ただ、これからは地域社会の変化にわれわれ事業者サイドが飲み込まれる時代なので、業態変更しないと生き残れないと思っている。
メタバース、仮想空間で新しい経済圏が動くと言われているのに、今までと同じでいいわけがない。ある意味で言うとチャンス。この3年ぐらいで、業界はかなり動くと思う。そのキーポイントはやはりDXだ。いよいよ勝負どころにきたと思っている。
柏谷社長「東京電力との強固な提携で乗り切る」
ーー足元を見ると、とりわけ電力事業は非常に厳しい局面に立たされている。ここをどう乗り切っていくのか。過去の成功体験との決別といった話があったが、社名変更などを視野に入れているのか。
柏谷 短期的な電力の需給のひっ迫等に関しては、東京電力との強固な提携によって乗り切っていきたい。中長期に関しても、東京電力との提携を継続しながら、急速に普及するであろう蓄電池、最終的にはコミュニティーの中でエネルギーを融通し合えるようなエネルギーシステムの構築、特にデータ面からの構築というものを急いで進めていきたいと考えている。
和田 日本瓦斯の社名がどうなるのかだが、例えば富士フイルムはフイルムが主力事業ではなくなって富士フイルムっていう社名は残っている。ただ、私は日本瓦斯といえども、単独でこの先、生き残れるとは思っていないので、最終的には柏谷が決断することになるだろう。
ーー柏谷社長は自身の強みについて、どう考えているか、また和田会長はどうのような理由から次期社長に柏谷氏を指名したのか。
柏谷 私は日本の大学を卒業して、そのまま日本の会社に入ってサラリーマンをスタートしたわけではなくて、米国に留学して米国で、それこそニューヨークで世界中の人がいるグローバルファーム、コンサルファームで自分のキャリアを積み重ねてきた。振り返ってみると、当社の重要な分野で営業の現場の人たちだったり、あるいは保安の人たち、物流、ITといったそれぞれのチームの人たちと連携したり協力したからできたということがほとんど。自分にそんな大して誇れるほどの知識や強みや秀でたものがあるとは思わないが、一つ言えるのは環境の変化に向けて新しいチームを組成したり、新しい考え方をつなげて物事を実行していくことが、自分なりの役割を果たせる分野と考えています。
和田 日本瓦斯に足りないのはCFOだと。よく考えると日本企業の多くはCFOが足りない。だから、CFO的な仕事のできる人材をということで、当社に柏谷を連れてきた。これが今後10年の資本政策につながっていく。DXによって、やらなくてもいい仕事をやめて、効率化をして、地域社会に還元するということをできない限りは、集約化のされる側に回ると思う。柏谷のような外部の人たちが入って、今までの日本瓦斯の価値、そういうものに対してクエスチョンマークを付けてくれたということがわれわれの改革のスタート地点だった。そういう意味で言うと、私が大きなげきを飛ばさなくても新しいところに挑戦できる体制になった。
新体制に執行権限は全て移行
ーー会長職の復活ということで、二人の責任範囲とか役割分担を改めて教えてほしい。
柏谷 会長職はもともと設けていて、会長が空席だったということなので、ここに関して規定等の変更をしたわけではない。新しい体制での執行の責任、あるいは分担範囲については、基本的には新体制に執行の権限は全て移行する。ただ、新体制ではなかなか判断がつかなかったりすることに関しては、適宜、和田に相談する。和田とは情報の共有はするけれども、新しい体制で責任を持って経営を行っていく。そういう意味では、責任も役割も明確にわれわれの中では認識を共有しております。
和田 私に限らず、ニチガスは全体に情報共有をするという意味ではオープンな会社だ、それゆえにここまで改革が進んできたと思っている。会長職を見ながら仕事をするような引き継ぎだったら、やってない。今の日本企業を見ると、改革を標ぼうしながらアクセルのつもりでブレーキ踏んでるのは、ベテランの知見のある人たち。ブレーキ踏んでるから大きな事故にはならないが、1歩も前に進まないというのが、今の日本の企業社会だ。
ーー新時代への成長戦略におけるスマートシティー構想について、具体的に。
和田 われわれが準備してるのはコミュニティーガス、いわゆる簡易ガス団地の中で、エネルギー版スマートシティーをDXで統治して運用しようということだ。今、某地点では打ち合わせをしながら、もう地域配電の許可も取っている。われわれだけではできないので、連携先、ベンチャー、そういう所との関係も含めて、いろいろ通信も含めて協議を行っているところだ。
【お詫びと訂正】本文冒頭のリード文と2段落目の文の2か所におきまして、柏谷邦彦氏の姓の表記に誤りがありましたため、訂正させていただきました。関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫びいたします(編集部)。