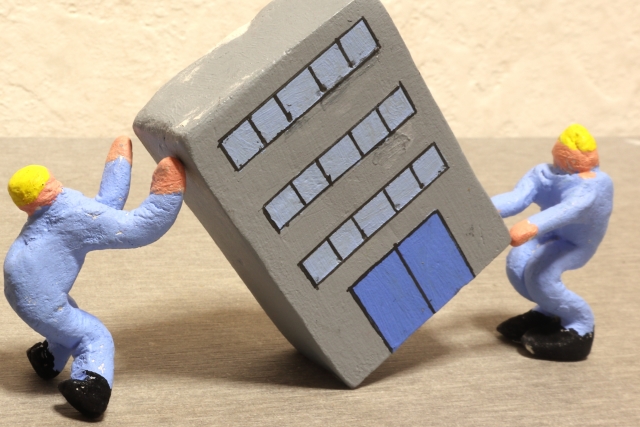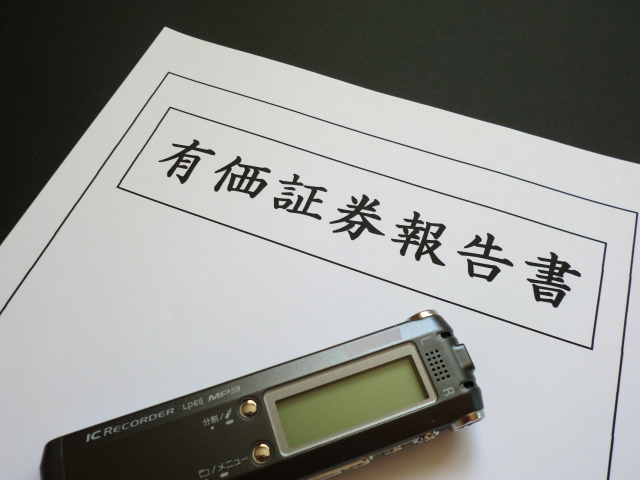1.地域新電力設立を妨害か 延岡市長が九電に抗議
地域新電力の設立を計画する宮崎県延岡市が、業界関係者の間で注目を集めている。九州電力が延岡市の取り組みを妨害するなどしたとして、読谷山洋司市長が九電に抗議を行うとともに、経産省などに対し九電の行為に関する調査を求めているためだ。
市長名の文書によると、九電は地元経済団体などに対し、「(新電力の)容量拠出金の負担が多額になるので赤字になる」と説明して回っていると指摘。新電力設立を阻止する意図だと推測しながら、「電力システム改革の大きな柱である小売り全面自由化を妨害する行為であり、かつ地方自治を侵害する行為」と痛烈に批判している。
事実とすれば、確かに問題になりそうだが、九電側は団体などから問い合わせがあり説明したこと自体は認めながらも、妨害の意図については真っ向から否定。また延岡市議のK氏(自民党)は、公約に掲げた新電力設立に前のめりな読谷山市長の姿勢に、「懸念があるのに、あいまいにしている」「疑心暗鬼」などと疑問を投げている。
延岡市では数年前から、九電が大阪ガスなど複数の都市ガス会社と共同で、旭化成が保有する石炭火力(3万4千kW)をLNG火力に設備更新する計画を推進。近隣にはLNG内航船の受け入れ基地も建設中だ。
「地域密着を標ぼうする大手電力会社にとっては、地域の自治体とは極力もめ事を起こさない方がいい。『金持ちけんかせず』で、地域新電力を応援するぐらいの気構えが必要だ。それは九電も十分理解しているはず」。大手エネルギー会社の幹部からは、こんな声も。経産省がこの件の調査に乗り出しているが、真相は果たして。
2.相次ぐ事実誤認報道 問われるS誌のモラル
全国的な需給ひっ迫による大停電をどうにか回避した1月の電力危機。電力会社のみならず、日ごろは熾烈な顧客争奪戦を繰り広げる都市ガス会社も、発電燃料のLNGを融通するなど一丸となってこの難局を乗り切った。
ところが、それに水を差すような記事が雑誌「S」の3月号に掲載され、エネルギー業界関係者の批判を招いている。問題となったのは、東京ガスを批判するミニニュースだ。電力不足の緊迫した最中に東ガスが電力販売のキャンペーンを展開していたことをやり玉に挙げるとともに、同社が東京電力よりも関西電力へのLNG融通を優先したことを報じている。

前者はともかく、後者に関しては「LNG融通で東ガスが東電より関電を優先した事実はない。ガセネタだろう」(大手エネルギー会社関係者)。発電燃料をかき集めていた当時の関電は、タンカーに残存するLNGも買い取っていたのだが、たまたまそれが東ガスの基地に荷揚げした後のトレーダーの船だったことがあった。S誌はそれを東ガスからの融通だと誤認し記事にしたとみられる。
かねて東ガスに批判的なS誌だが、同号に怒り心頭なのは東ガス関係者だけではない。これとは別の「卸電力取引所狂乱相場の全内幕」と題した記事の中で「停電危機でぼろもうけした輩たち」と名指しされた新電力の関係者だ。
記事によると、イーレックスなど新電力3社が、東電から卸供給を受けた電気を日本卸電力取引所に転売して大儲けしていたという。だが、取り沙汰された新電力関係者の一人は「そもそも今回の市場高騰では大儲けどころか赤字。明らかに事実誤認だ。迷惑極まりない」と憤る。
事実関係の裏取りをしないまま記事にしてしまう、S誌のモラルこそ問われている。
3.三村知事が国政進出? 共同利用案に影響も
核燃料サイクル施設が集中立地することから、電力業界にとって最重要地である青森県。業界が頭を抱える使用済み燃料中間貯蔵問題も絡んで、その青森県の政界動向を関係者が注目している。
三村申吾知事は2019年の知事選で5選を果たしたが、「さすがに6選には出ず、国政への復帰を目指すはずだ」(業界関係者)とみられる。県政に詳しい関係者が有力と考えているのが、来年知事を辞職し、夏の参議院選に出馬することだ。
「青森選挙区で改選するのは一人。来年改選するのは立憲民主党議員だが、その次になると自民党議員になる。知事選で自民・公明党の推薦を受けている三村知事が出るのなら、対抗馬が立民党になる来年だろう」(業界関係者)

関係者の関心は、誰が三村氏の後継知事になるかに向けられている。下馬評に上がっているのは、A市のO市長とM市のM市長。どちらも中央省庁の元キャリア官僚だが、「今のところO市長が有力視されている」(同)。
中間貯蔵施設の共同利用案に反発するM市長には、「とりあえず市長の職から離れてほしい」と考える関係者がいる。だが知事就任は難しく、衆院の3選挙区は自民党現職が占め、国政に送り出したくても「空席」なし。当分、業界はМ市長に向き合わざるを得ないもようだ。
4.再エネ団体Sに試練 体制を大幅縮小か
再エネ導入拡大をけん引してきた団体Sが、規模縮小の危機にさらされているといううわさが浮上している。
Sは東日本大震災を契機に、再エネ拡大と脱原発を目指して活発なロビー活動を展開。役員には設立者の実業家S氏を筆頭に、国内外の著名人が名を連ねる。団体は収益の大部分を寄付金に依存し、S氏も多額を寄付していると言われている。が、関係筋によれば、ここにきてS氏が団体とは一線を画す動きを見せているというのだ。
団体幹部に次年度以降のS氏の動向について問うと、「会長を辞めるような話は聞いていない。来年度以降も変わらず会長職を務める」と断言する。だが、ある再エネ業界関係者は「S氏は会長はやめないものの、いわゆる手切れ金の額まで提示したそうで団体関係者は大慌て。オフィスの移転を検討し始めたと聞いている」と打ち明ける。
最近のS氏は、自社グループの再エネ事業に対しても関心を失いつつあるとの話もある。震災から10年という節目で、いろいろ思うところがあったのだろうか。
5.安売り回避で協調? SS業者のメールリスト
新型コロナウイルスのまん延による価格下落から1年近くが経過し、原油先物市場の価格はコロナ禍以前の水準に戻りつつある。それに比例してガソリンスタンド(SS)の販売価格も3月8日の全国平均価格が146・1円となるなど上昇を続けている。
そもそも、WTI原油先物市場価格は昨年の夏から冬に掛けて40ドル台という低価格で推移していた。にもかかわらず、過去の原油安の時期と比べて割安感に乏しかったことから、「元売り再編で価格競争がひと段落し、安値攻勢を仕掛けていた業転問題もほぼ解消された。むしろ業界内ではここぞとばかりに、安売り回避で協調する動きが起きているのでは」と、談合疑惑の声が上がっている。
WTIが40~50ドル台で推移した16~17年当時、国内のガソリン価格は110円台という安値が続いた。対して昨年は5月から12月のWTIが30~50ドル台を付けていたものの、同時期のガソリン価格は最も安い時でも124・8円(5月11日集計分)にとどまっている。元売り2+1強体制の効果が表れているのは、明らかだ。
さらに、SS事情に詳しい関係者X氏はこんな内情を打ち明ける。「業界には『この地域のレギュラーガソリンは〇円』という情報を共有するメールリストがある。事業者はその情報を基に、阿吽の呼吸で価格を決めている」
実際、長距離ドライブの経験があるドライバーなら、地域ごとにSSの掲げる価格水準が異なることに気付いた人もいるだろう。「S県K市では軽油1ℓ116円だったのが、T県M市に移動すると同120円に相場が上がった。メールの話を聞いたら納得」(運送関係者)
全国的にSS数は激減していることから、「業者にしても、消耗戦は避けたいという事情がある」(X氏)。だが利用者にとっては、果たしてどうか。某離島では、地元住民と観光客で価格差を付けていたことを考えると、まだましかもしれないが。