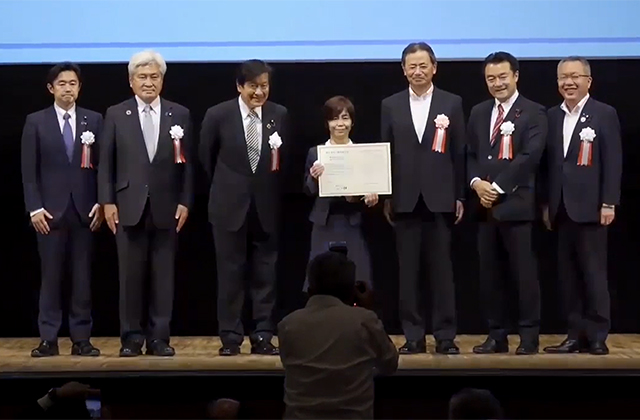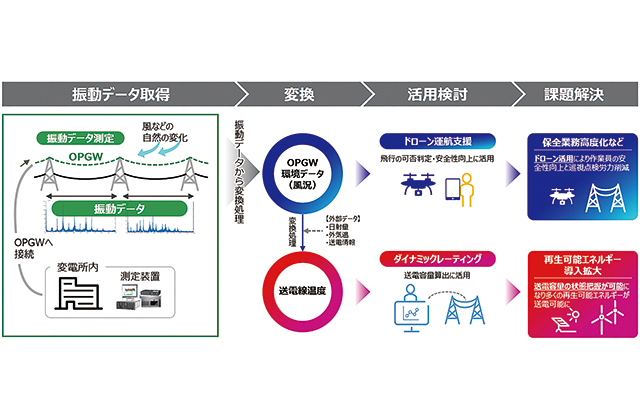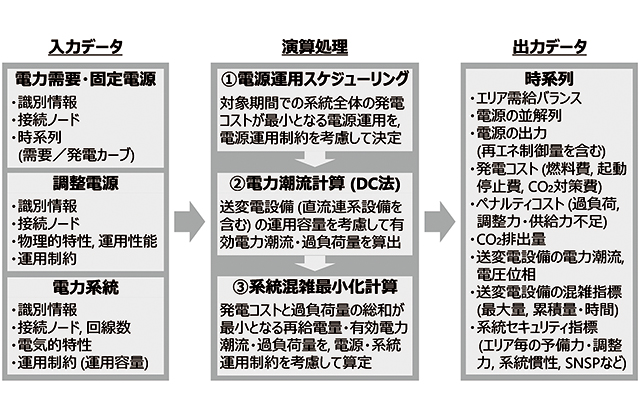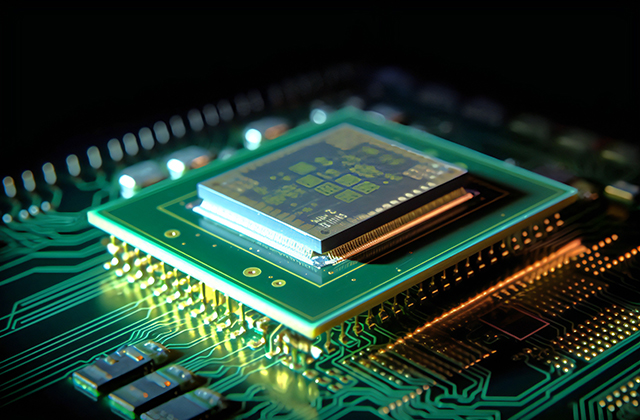【おやおやマスコミ】井川陽次郎/工房YOIKA代表
出羽守とは、「(『では』と『出羽』をかけて)『海外では』のように、他者の例を引き合いに出して語る人」(デジタル大辞泉)である。まさにこれだろう。
6月の国会で成立した「性的少数者(LGBT)への理解増進法」を巡る報道である。読売、産経以外は、5月に広島で開催されたG7サミット(主要7か国首脳会議)のころから成立まで、「日本は遅れている」と大騒ぎした。
5月22日朝日「広島サミット」は、「(20日に発表された)G7サミットの首脳コミュニケ(声明)には、ジェンダーに関する項目が設けられ、『あらゆる人々が性自認、性表現、性的指向に関係なく、暴力や差別を受けることなく生き生きとした人生を享受できる社会を実現する』と明記した」「ジェンダー平等をめぐっては、議長国である日本の遅れが国内外から指摘されている。日本はG7で唯一、国として同性カップルに法的な権利を与えず、LGBTに関する差別禁止規定もない」。
5月9日TBSもG7各国の差別禁止法の表を作り日本だけバツをつけた。他も似たりよったり。
読売6月18日社説「LGBT法成立、社会の混乱をどう防ぐのか」は真逆だ。「先進7か国(G7)で、LGBTに特化した法律を持つ国はない。LGBT法は、国際社会でも極めて特異な立法」と指摘し、「日本は最高法規で『法の下の平等』を定めている。LGBTに特化して差別禁止を定める理由は、見当たらない」と強く批判する。
出羽守たちの言説はどうも怪しい。衆議院法制局は5月、「G7でLGBTに特化した法律を持つ国はない」と自民党に説明。6月15日の参議院内閣委員会でも、外務省が有村治子議員(自民)の質問に同じ答弁をしている。
日本たたきの根拠は一体何だったのだろう。今後、LGBT報道は眉唾もの、と考えざるを得ない。
読売7月1日「OP技術で出典明示、『ネットの健全性高まる』」は、「台北で開かれた『世界ニュースメディア大会』で30日、読売新聞東京本社編集局長が講演。インターネット上の情報発信者を明示するデジタル技術『オリジネーター・プロファイル(OP)』が実用化されれば、『ネット空間の健全性は大いに高まる』と強調した」と書く。ネット記事や広告に発信者の信頼性を確認するための情報を電子的に付与する。
全国紙は全て参加しているという。期待したいが、何より重要なのは、記事の中身だろう。
朝日同日のコラム「石油危機から50年、『脱炭素』の戦略、定まらぬ軸足」は、日本企業が液化天然ガス(LNG)産出国との新規契約に消極的で、「既契約分の輸入が減り始める数年後には国内のガス供給に不安」と警告する。理由は、政府が電源の化石燃料比率を2030年度までに半減させる計画を定め、将来の需要が見込めなくなったためと解説する。
対策として推すのは再生可能エネルギーの普及。加えて化石燃料の開発投資も重要とする専門家の声を紹介する。記事からして軸足が定まらない。そもそも原子力発電に触れないのはなぜか。
トルコ公共放送TRTは6月9日、討論番組「フィンランドの電力価格がゼロ以下に」をユーチューブ配信した。フィンランドでは4月、オルキルオト原子力発電所3号機(出力160万kW)が本格稼働した。ダム水量も多かった。ウクライナ侵攻したロシアに昨年、電力供給を止められたが、原子力の実力を示した。あっ、出羽守……。
いかわ・ようじろう デジタルハリウッド大学大学院修了。元読売新聞論説委員。