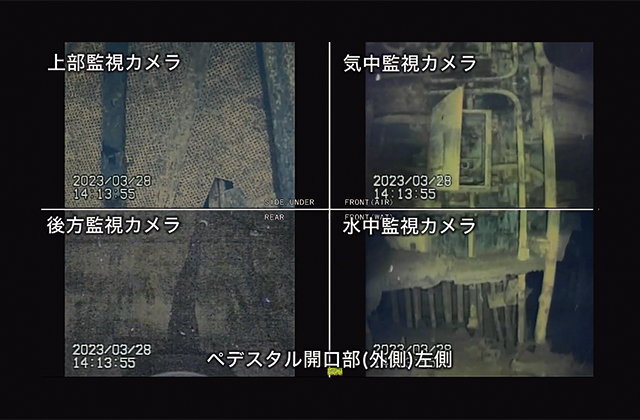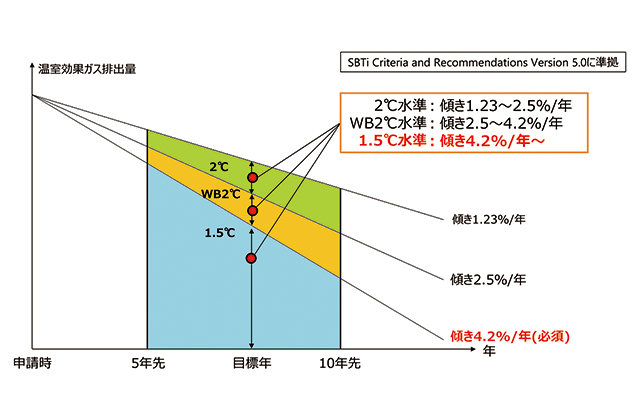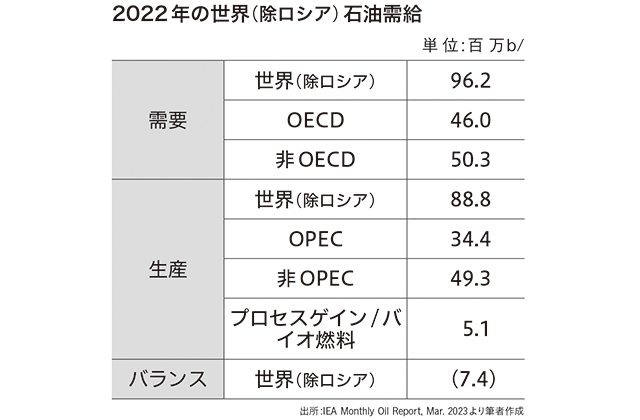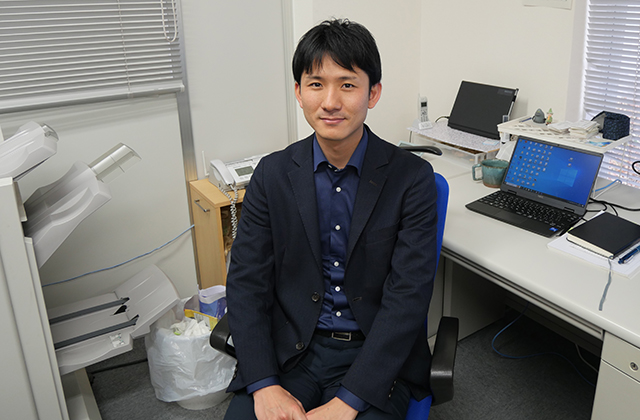テーマ:電力・ガス業界の人事と評価
電力業界の不祥事は、人事にも大きな影響を及ぼしている。潔くトップが辞任した会社があれば、辞任のタイミングを見計らったり、社長の首を守ろうとする会社も。騒動が過ぎ去った後の人事予想まで語り尽くした。
〈出席者〉 Aアナリスト Bエネルギー関係者 Cジャーナリスト
―まずは電力業界から。電気事業連合会は池辺和弘会長(九州電力社長)が続投。これで4年目に突入し、八木誠氏(当時、関西電力社長)に次ぐ在任期間に。候補には東北電力の樋口康二郎社長の名前も挙がっていた。
A 池辺さんの続投は、あくまで暫定的だ。中部電力と関電はカルテル、不正閲覧問題で引き受けられる状況ではない。一方で東北電にとっては、このタイミングで初めての会長職は荷が重すぎる。ただ池辺さんも一連の不祥事が一段落すれば退任する可能性もある。
C そんな状況でも、会長職へ触手を伸ばしたのが関電だ。カルテル問題は、関電自らがタネを撒いて刈り取ったようなもので業界内の評判は最悪だというのに。
B 一連の問題で逃げ切れたとしても、金品受領問題以降、経済産業省から連続して業務改善命令を食らう会社が電事連会長というのは、業界的に受け入れられない。カルテルの後で不正閲覧問題が明るみになり、ようやく会長職は無理だと悟ったようだ。
A 関電は他業種からの信頼も失った。一部の会社は安定供給を維持するために不正閲覧を行ったが、関電は営業に利用していたので極めて悪質。電事連会長などあり得ないのは明白なんだが……。業界の次男坊として自由奔放にやってきて、周囲の目など気にしない経営体質が表れている。
B 関電は昨年、森望社長の就任会見で、森本孝前社長の退任理由について「カルテルとは無関係」とした。退任理由をしつこく問われた森本さんは、質問した記者に「あなたの言っている意味が分からない」とまで口走った。森さんは今回の不祥事を巡って3月30日に記者会見し、岩根茂樹元社長や森本さんの関与に触れたが、改めて森本さんの退任理由は経営陣の若返りの趣旨だと言った。
ただ4月12日の社長会見では、森さんら幹部13人を減給などにする処分を発表、特別顧問の森本さんは結局辞任した。いま関電はとにかく森さんの首を守ることが至上命題になっている。一方で3年前、外部から招聘された榊原定征会長の今後も注目される。
A 森本さんは当時、営業担当の副社長でカルテルのレポートライン(指揮命令系統)にいたが、森さんはいない。しかし、森本さんがギリギリまで引責辞任という形を取らなかったことで、全ての責任が森さんに覆い被さってしまった格好だ。
C 金品受領問題以降、執行役員で残っているのは稲田浩二副社長だけ。もし森さんの首が飛べば、次は稲田さんか。
A いや、稲田さんもレポートラインにいるので、社外取締役が納得しないのではないか。取締役の中でカルテル問題と無関係なのは杉本康さんだけだが、年次を考えると難しい。関電は一気に執行役員クラスに若返りするかもしれない。

提供:朝日新聞社