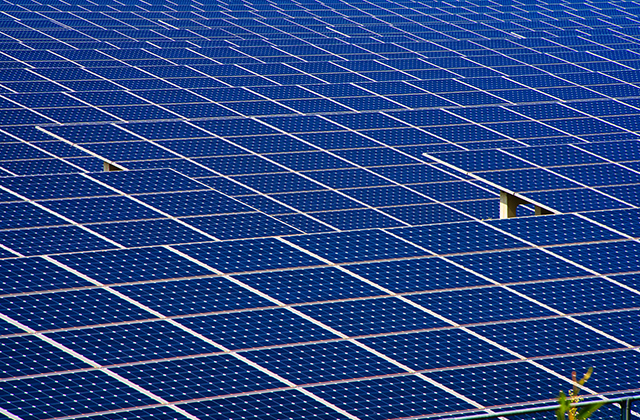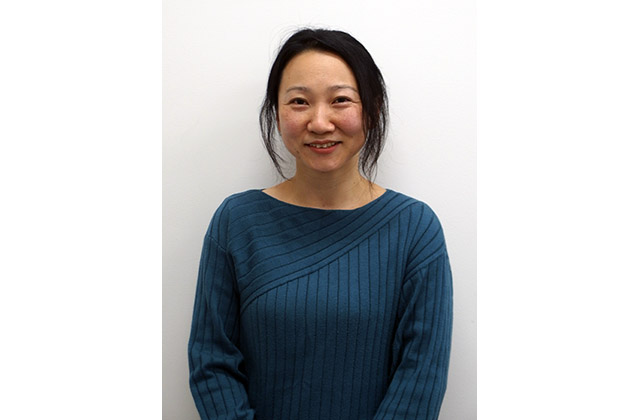テーマ:電力供給力対策
毎年のように繰り返される電力需給危機。資源エネルギー庁と電力業界は、これまでさまざまな対策を講じてきたが抜本的な解決策にはつながっていない。供給力をいかに確保するべきか。
〈出席者〉A発電事業関係者 B大手電関係者 C学識者
―今冬は、電力需給対策により厳寒時に必要とされる予備力をかろうじて確保しているようだが、毎年のように危機が繰り返されていることを踏まえると、安心はできない。
A もっと事前に準備していれば、ここまで費用をかけずに確保できるのではないか。設備容量(kW)も電力量(kW時)も不足しているのだから対策を打つのはいい。だが、kW時についてはウクライナ戦争のために燃料が高騰しているからなのでやむを得ないとはいえ、kWについては行き当たりばったりで非効率な印象が否めない。準備不足だと思う。
B 2013年の経済産業省の「電力システム改革専門委員会」の報告書には、セーフティーネットとして電力広域的運営推進機関入札が盛り込まれ、資源エネルギー庁関係者は「いいことを思い付いた」という感じだったし、容量市場が立ち上がるまではそれでつなぐのだろうと考えていた。いいことを思い付いたと自信を見せていたのだから、もっと早く発動してもよかったのではないか。
C 不足しているのだから、当たり前の対策を講じているだけのことだ。それにしても石油火力が残っていれば、需給状況は全く違っていただろうね。こうした事態を招いたのはここ10年の政策担当と学識者であって、今の電力基盤整備課は一生懸命だと思うけどね。
―東日本の予備率は、マイナス予想から対策を講じてなんとか4%台を確保した。
A 計画外停止は昔からあったことで、その頻度が上がっているわけではない。JEPX(日本卸電力取引所)へ半強制的に限界費用で玉出しをさせられ、容量市場の約定価格が2回目で大暴落するなど、老朽化した設備を直しながら維持していこうとしていた発電事業者は適正な水準の支払いが受けられないと判断し廃止に向かっている。そうした設備を急に運転再開しようとすると、どうしてもお金がかかってしまうし、ほかの電源よりも信頼度が落ちてしまうのは当たり前のことだ。計算上だけでつじつまを合わせようとするから、何かあるたびに騒ぐことになる。
C プロ野球の監督だって中継ぎのピッチャー5人に4回から8回まで登板させて、絶対に0点に抑える戦略なんて立てないでしょう。今発電側の対策で行われているのは、そういうことだ。原子力以外の電源は、1カ月運転すれば1割の確率で故障が起きるもの。そういうことを考えると、予備力が確保されていれば安心だというのは大間違いだ。
今年3月の福島県沖地震で損壊した新地発電所1号機が11月11日に冬を前に運転再開にこぎつけたけど、そのメンテナンス力だって石炭火力をいじめ続ける限り、いつまで維持できるか分からない。火力をばかにしていると大変なことになるよ。

小売り側の規律正常化 安定供給にプラス効果
―燃料不足によるkW時不足を回避するため、国による燃料在庫の監視が行われている。
C 発電事業者は、価格ヘッジもされず売る当てのない燃料を買うことはできないから、小売り事業者のヘッジを徹底させた意味は大きい。その分燃料を積みやすくなるし、発電事業者の燃料を積むことのリスクが縮小される。燃料の先買いができない小売り事業者は潰れてしまえと明確に言っているようなものだけど、もともとは、需要の上振れ分以上のシェアを新電力が取ったら停電するような仕組みだったわけで、供給側の対策ばかり注目されるが、小売り側の規律が正常化されれば自ずと燃料在庫は積み増しされ安定供給に相当のプラス効果が働く。そうすることで、監視さえ必要なくなるはずだ。
A 発電側からすれば、小売り事業者が需要を予測してそれに合わせて燃料を調達するのだから、そこがいい加減である限りどうすることもできない。監視すべきは、小売り側であって発電側ではないんじゃないかな。
―今冬実施される節電プログラムやデマンドレスポンス(DR)の効果はどうだろう。
C ユーザーに毎年節電するよう要請しても、いずれ効果はなくなる。そうならないために大事なのは、節電に対価を与えるか自動で節電する仕組みを定着させることだ。今回の取り組みは、そのプラットフォームを作ることが目的。多くの事業者が手を挙げ、SBパワーのようにプラットフォームを提供している会社もある。電力業界関係者は、DRをしたところで、しょせん数万kWにしかならないと言いがちだけど、長期で累積することが大事なんだよ。そういう意味で、明らかに電気の調達コストと価格が上がっている中で税金をばらまくようなことは、省エネとDRを邪魔することにほかならない。
A DRはやっぱり量的に大したことないということははっきりさせておきたい(笑)。だからやめろということではなく、DRは数時間しか持続しないのだから、それとは違う次元の予備力や調整力としての効果が火力にはあるということをきちんと認識する必要がある。節電するということはどこかで経済を痛めるということだよ。
B 経済活動の機会損失よりも高い値段で買い戻してくれるはずだから、経済を痛めないとすら考えている人が多い。
A そういいながら価格スパイクを抑え込むから経済は痛むし火力は退出せざるを得ない。