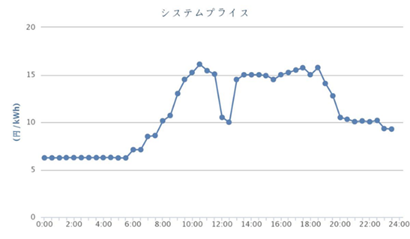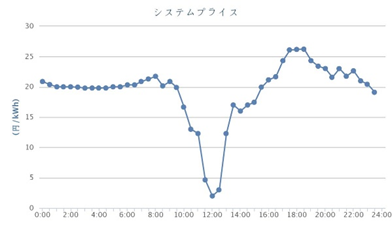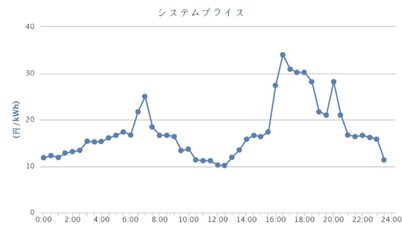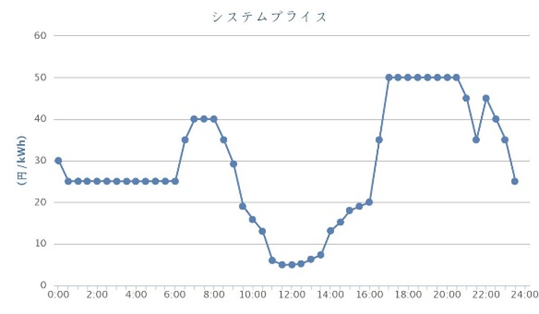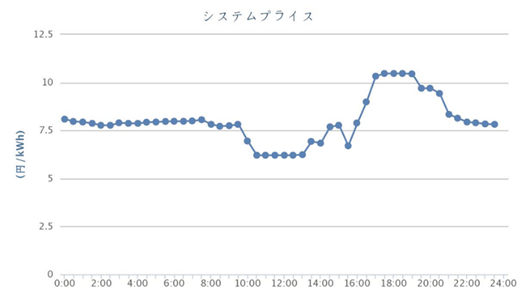【東京電力パワーグリッド】
脱炭素に向けた取り組みの波は電力系統のインフラ設備にも押し寄せている。
東電PGは業界に先駆けて環境にやさしい次世代型の変電設備を導入した。
カーボンニュートラルの実現に向けて、今、電力会社の送配電部門は大きく二つの、そして大変に難しい課題に向き合っている。一つは日々導入量が増えている再生可能エネルギーとの共存と、それに対する対応だ。「再エネ主力電源化に向けて何が必要か」。日夜、部門内では技術的かつ経済的な検討を続けている。制度設計の歩みと合わせながら、需給調整機能の大きな役割を担う「火力業界」とのやり取り、需給調整機能の精査……。また、それに伴い、インフラ設備の「保全」や「整備」についても新しい考え方が必要になってきている。従来は、秋や春など需給が緩和するタイミングを見計らって、人員を確保し設備保全やインフラを整備してきたが、再エネ大量導入時代は、そんな常識は通用しない。これらが難事の一つ目だ。
そして二つ目が、インフラ設備そのものにおけるカーボンニュートラルへの挑戦だ。「電力系統設備、とりわけ変電設備部門の環境対策に取り組む業界のリーディングカンパニーでありたいと考えています」。東京電力パワーグリッドで変電設備技術部門の実質トップである、工務部の塚尾茂之変電技術担当部長は、力強くこう話す。まず、塚尾さんが目を付けたのは、変電所の設備のひとつを構成する「開閉装置」だ。
日本初の環境型変電設備 自然由来ガスを利用
東京・府中駅から歩いて20分程度の静かな市街地に、東電PGが運用する6万6千Vクラスの変電所が存在する。変電所とは、その名が示す通り、電圧を調整するインフラだ。ここでは、高い電圧で送られてきた電気を低い電圧に落とし、実際の需要家に電気を送り届けるハブのような拠点だ。
敷地内には、設備を監視する機能を備えた無人の建屋のほか、経年化に伴って多少変色した、白や灰色を基調とした設備がいくつかたたずんでいる。設備を構成するのは、開閉装置(遮断器や断路器)、変圧器、避雷器などだ。
この府中変電所では、今秋から、経年化に伴った一部の設備のリプレース工事を進めている。その対象設備が開閉装置である「ガス絶縁開閉装置」、通称GISだ。そして、この設備こそが、東電PGが国内で初めて導入する、環境対応型次世代設備「AEROXIA(エアロクシア)」(東芝エネルギーシステムズと明電舎の共同開発)だ。
 東芝の川崎の工場で出荷を控える開閉設備
東芝の川崎の工場で出荷を控える開閉設備
ガス絶縁開閉装置と脱炭素―。両者に一体どのような相関関係があるのか。まずは、開閉設備の機能を簡単に説明しよう。この設備は、電気を流したり、あるいはその流れを瞬時に止める「遮断機能」や「絶縁機能」を持つ。落雷などで急激に電圧が高まったり、異常な電気が流れたりする時、瞬時に電力系統から切り離す必要がある。その際の「遮断」や「絶縁」は、
まさに電力インフラに不可欠である。そして、その遮断・絶縁に使っているガスがSF6(六フッ化硫黄)と呼ぶ、自然界には存在しない人工ガスだ。遮断や絶縁性能が優れていることから、設備全体を大変コンパクトに設計できる。1970年頃から、世界的に普及してきた。今回更新の対象設備として、78年に運用開始された府中変電所の初期型GISでも例外ではない。ところが、このガスは、地球温暖化係数(GWP)の値が2万5200と高いという欠点を抱えている。
「これまで、日本の電力会社は、このガスを漏らさないように運用してきました。年間の漏洩率は1%未満で、世界に誇れる運用でした。ところが、近年、世界的な脱炭素の流れの中で、SF6を代替するGWP値の低いガスの使用が求められてきました」。
そうした中、塚尾さんが主幹事となって、国内電力、学識者、メーカーとともに、次世代開閉機器の設計要件を議論してきた。塚尾さんらがユーザーとして志向したのは、人体に与える影響と安全性や環境適合性、代替ガスの供給性、SF6と同レベルの簡易なハンドリングな七つの要件だ。
技術駆使し省スペース設計 次なる課題は大型化
「容易な技術開発ではありませんでした」と塚尾さんは振り返る。設備設計をしたのは、あくまでもメーカーである東芝エネルギーシステムズと明電舎だが、東電PGは、公益的な設備を使用する立場である以上、使用者としての公益的な責任がある。公益事業者として、設備の安全性や環境適合性といった技術要件をしっかりと管理しステークホルダーに説明する責任があるわけだ。そんな使命感から漏れ出た塚尾さんの発言だ。
まず、塚尾さんを悩ませたのは、代替ガスの選定だ。代替ガスには、フッ素系ガスと自然由来ガスの2方式が存在している。前者のフッ素系ガスは、自然由来ガスほどではないが、SF6よりもGWP値が低く、絶縁性能も優れている。大型化への対応も比較的容易に可能だ。ただ、ガス自体や分解生成物の人体への健康面(毒性)での課題が解決し切れていないほか、ガスの供給面で不安を抱えている。
次に志向したのが自然由来ガスだ。GWPは1以下であることから、温暖化対策的には究極のガスだ。ただ、課題は主に絶縁性能だった。SF6ガスはその性能が優れていて、設備をコンパクトにできる。国土面積の狭い日本では、最適なソリューションだったが、自然由来ガスではその性能は約3分の1。単純計算で、設備サイズは約3倍になる。
そこを、ガスが収まる「タンク部」や電気が流れる「導体部」を設計改善した。使用した自然由来ガスは、窒素と酸素を混合したドライエア。遮断部に真空バルブを適用したり、実規模検証試験による最適な圧力設計などで、工夫した。そんな苦労が奏功し、リプレース前と比べても、省スペース設置が可能となり、今回、国内に先駆けて導入にこぎつけた。
次なる技術課題は、自然由来ガスによる「高電圧・大容量化」への挑戦だ。今回導入した府中では、変電所としては「小規模サイズ」。今後、27万5千~50万ボルトクラスへといった高電圧化が必須となる。その際どういった代替ガスを使い、どういった設計にして脱炭素を実現できるのか。安定供給を維持しながら、なおかつ託送コストも抑えないといけない。
高度成長期に大量整備されたインフラの更新時期が静かに訪れている中、複雑で多様な「難事」に東電PGは、今挑んでいる。