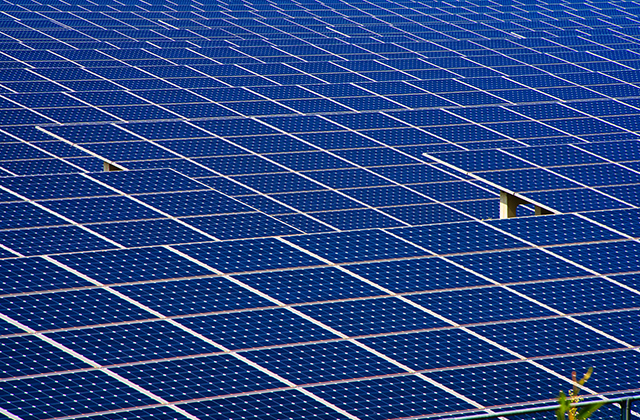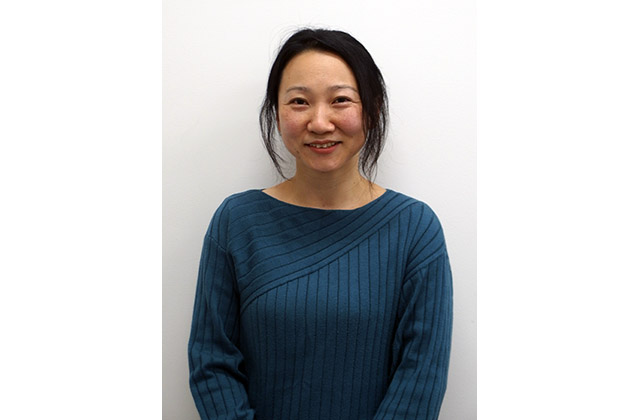民意を得た上関原発 安倍元首相の遺志も
中国電力が原発の立地計画を進める山口県上関町の町長選が10月24日行われ、原発推進派で前町議会議長の西哲夫(無所属新人)が、反対派の木村力(同)を破り、初当選した。原発を争点にした11年ぶりの選挙戦で、得票率7割という圧勝だ。
「原発を持ってくることで商業が発展して働く場所も確保でき、豊かな生活支援ができる」。西氏は民意が示されたとして、メディア取材などを通じ原発計画実現への意欲を見せている。
実は上関原発を巡っては、故安倍晋三元首相がかねて計画実現に向けて地道な政治活動を続けてきた。官邸事情に詳しい政府関係者A氏は昨年11月、本誌の取材の折にこんな話をしていた。
「安倍さんは、日本最後といわれる上関の計画をまだ諦めていない。首相退任後も自民党の最新型原子力リプレース推進議員連盟の顧問を率先して務めるなど、いわば推進論者だ。上関では新型炉の可能性もあるだろうし、それとは別に(高レベル廃棄物の)最終処分場建設に関する文献調査という話もある。最終処分場であれば、動いている炉より、はるかに安全だ。政府はクリーンエネルギーとして原子力を明確に位置付けて、その戦略を来夏の参院選までに打ち出すことが必要だ」
そんな安倍氏は去る7月8日、奈良市内で参院選の応援演説中に、山上徹也容疑者の手によって暗殺された。そうした経緯を背景にして行われた町長選の結果を、関係者は重く受け止める必要がある。安倍氏の遺志を受け継ぎつつ、民意を得た上関原発計画は脱炭素、電力需給、電力コストの課題解決に向け本格始動の時を迎えた格好だ。
住民恫喝に市議暴行 再エネ会社の正体
「いい加減にしろ!」
男性の老人が怒鳴り声のあと、人を殴る素振りを見せ、バンと机を叩く。そして「黙ってろ!」と怒鳴り、資料を見ようとした人の手を払い、腹を殴る。見ている女性は悲鳴を上げる―。
このような衝撃的な映像が「太陽光パネルの乱立から里山を守る北杜連絡会」のウェブサイトに3本掲載され、SNSで拡散された。
これらは今年5月と7月に、山梨県北杜市で行われた営農型太陽光発電の事業者代理人による住民説明会での映像だ。そこには映っていないが、7月の説明会では出席した北杜市議会議員がこの老人に腕をつかまれ、全治2週間のけがとの診断を受けた。市議は被害届を警察に出し、甲府区検察庁は10月17日に暴行罪で殴った老人を略式起訴した。11月15日時点で、裁判の結果は明らかになっていない。
太陽光を巡る問題は後を絶たない
報道では東京世田谷区にある会社の80歳の技術顧問が起訴されたという。参加した住民によると、この会社はN社で、映像では後ろに同社のF社長が映っている。映像で暴れている老人は同社のNという人物だ。新聞検索システムなどを使うと、この二人と同名の人物が、過去に水産物の産地偽装販売による詐欺罪などで逮捕されていた。
11月中旬にN社に問い合わせたが電話は留守電で、メールへの返信もなかった。ウェブサイトによるとN社は1993年に設立され、13年から営農型太陽光パネルの工事を開始し、山梨県などで事業を行っている。
太陽光発電を巡っては日本各地で乱開発による住民トラブルが発生し、北杜市でも反対運動が広がる。この異様な事件では、当事者の説明が求められる。さらに地域共生を軸に、太陽光事業者全体による自主規制と悪徳業者の排除が行わなければ、再エネや太陽光事業の未来はない。
ESGで人材争奪戦 大手信託Mに多士済々
ウクライナ侵攻が続く中にあって、ESG(環境・社会・統治)を巡る動きは世界規模で活気にあふれている。国内も例外ではない。大手信託銀行Mは、ESG関連の投融資を2030年度までの10年間で合わせて10兆円実施する計画だ。脱炭素の流れが加速して資金需要が増えており、昨年度の投融資は計画より3000億円程度上ぶれした。このことから計画を上積みした格好だ。
Mで同分野を担当するESGソリューション推進部は、世界銀行勤務などのキャリアを持つXをリーダーに据え、エネルギー業界はもとより、さまざまな分野で活躍する優秀な人材をかき集めているという。
中でも、証券会社でエネルギー関連事業の調査を担当し国の委員などを務めるY、流通大手IでESG戦略を推進してきたZは、業界で知れわたる人物でその移籍が注目された。
このほか、「石炭火力廃止、再生可能エネルギー100%」を主張する環境NGO団体の元日本代表を務めたAも在籍する。バラエティーに富んだ人材がESGの下、Mに集結している。
ESG部門で活発化する人材争奪戦
トーエネックが特損計上 FIT認定IDの行方は
静岡県函南町軽井沢地区で計画されるメガソーラー建設事業が、地元の反対などを受けて暗礁に乗り上げようとしている。
函南町は10月28日、再エネ条例の勧告を受けた事業者が「正当な理由なく当該勧告に従わないため」として、トーエネック、ブルーキャピタルマネジメント両社の社名を公表した。両社に対する勧告内容は次の通りだ。
〈(事業者の計画の届け出に対して)町は不同意を通知し、当該不同意の事業を継続する場合には、同条例第9条第3項の規定に基づき町長の同意を取得するよう指導を行いましたが、その後、事業地の地盤調査を実施するなど、当該事業を継続していることが確認されましたので、直ちに町長の同意を取得するよう勧告を行いました〉
町側の勧告を受けたトーエネックは同日、今年度上半期決算で特別損失を発表。具体的には、「当社が計画している再生可能エネルギー事業に係る固定資産(建設仮勘定)について、事業の見通しが不透明である」として、114・9億円の特別損失を計上した。関係者が言う。
「トーエネックとしては、函南町メガソーラーを特損扱いにしたことで事実上の撤退ということだろうが、問題はブルー社からT社を経由して購入したFIT認定IDの行方だ。本来、認定IDは取り消されるべきところだが、T社やブルー社が引き取る可能性も否定できない。ただ、町側が計画への不同意を掲げている以上、事業続行は極めて厳しい。一体どんな決着を見せるのか、注視している」
折しも昨年11月、トーエネックが、施工不良などが発覚した山梨県甲斐市菖蒲沢地区のメガソーラー事業をブルー社に譲渡する形で撤退し、長崎幸太郎知事らから批判を浴びた。函南で同様の手法を取れば、地元から反発を食らうのは想像に難くない。今後の展開が注目される。
今度は法相が辞任 国会空転への懸念
岸田政権で閣僚の辞任が相次いでいる。山際大志郎経済再生担当相に続き、今度は葉梨康弘法務相が辞任した。岸田派議員のパーティーでのあいさつで、「法相は死刑のはんこを押す時だけがトップニュースになる地味な役職」といった趣旨の発言をしたと報じられて、高まる批判を収めることができなかった。
葉梨氏は元警察官僚。茨城県の名門である。元政治家の義父と養子縁組みし、自身も政治の道に入った。実は経産省OBでガス関連団体の役員を務めたH氏と親戚関係にあるというのは、知る人ぞ知る話。法相を辞任した葉梨氏への地元の期待は高かったようだが、思わぬ失言で足をすくわれてしまった。
「新聞が1面トップであれだけ騒ぎ社説まで入れるほどの話題だったのか疑問だ。本来は囲み記事程度の内容では。野党も政策議論ではなく、岸田政権の閣僚の首を取ろうとする作戦に終始しているが、エネルギーや物価高騰、安全保障問題など本当に課題山積の中、予算に関する議論にこそ時間を割いてほしいと、むなしくなる」(エネルギー業界関係者)。国会の空転が続くことへの懸念も出ている。
また実際は葉梨氏の件の発言には続きがあり、「法務省は憲法を具現化する、理念を具現化する、そういう行政」だと語っていたという。今回もメディアの切り取り作戦勝ちというわけか。