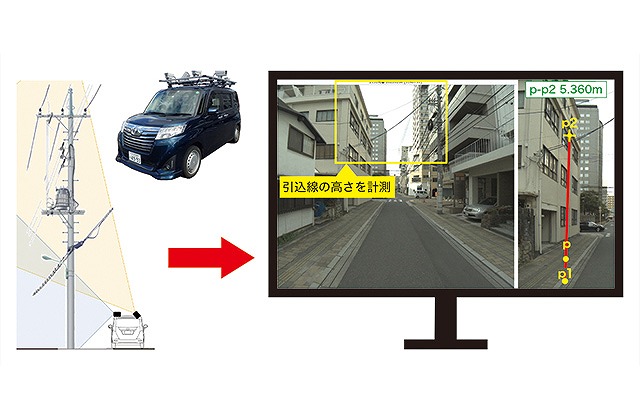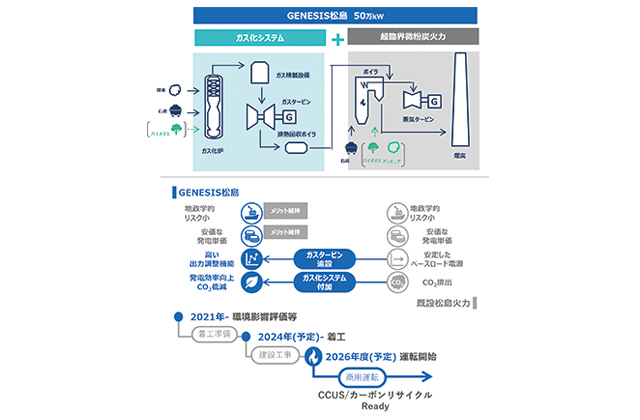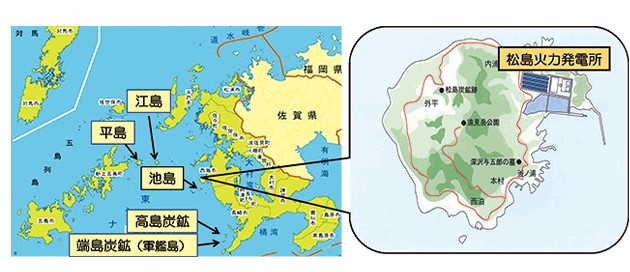飯倉 穣/エコノミスト
1,電力システム改革見直しの覚束無い中、暑い夏が過ぎる。酷暑の中、停電の懸念がよぎる。
近時電力需給に関わる記事が多い。「東電、料金3割上げ 来月、「電力難民」企業向け 中部電・関電も引上げ」(日経22年8月20日)、「首相指示 原発 新増設を検討 運転期間延長も」(朝日同25日)等々。
90年代、官は、電力の地域独占の問題(新規参入困難、再エネ不熱心、適正コスト不明・総括原価、電力会社の態度)の除去を狙い、電力システム改革を始めた。発送電を分離して独占が残る送電には公平な規制を導入する。発電と配電は自由市場とする。卸売のスポットマーケットを育成する。そして長期的な視点の設備投資市場の整備を目指した。
そして20数年、東日本大震災・福島第一原発事故ショック時の政権の思惑が、電力システム改革推進に走り、続く政権も踏襲した。16年小売全面自由化、20年発送電分離で官製電力自由化が完成した。改革キャッチフレーズは、自由競争市場で安定供給強化、市場競争・効率化で料金(価格)低下、電気を選べる時代だった。競争政策は、消費者重視を謳った。その消費者が、電力需給逼迫警報等で不安を煽られている。何故だ。
2,電力自由化は、様々な政治的・政策的・行政的・他産業不満配慮等の思惑で出発した。技術革新乏しき電力業で、自然独占・事業規制の論理を超える正しい経済論があったわけでない。
米国、EUの電力自由化をヒントに 公益事業(独禁法の適用除外)の扱いでなく米国要求消費者重視・競争政策の徹底(独禁法強化)を画策した。つまり新自由主義・市場重視の流れで電力需給を市場に委ね価格で調整することを良とした。
すべて市場が解決する。一般の商品同様需給逼迫なら価格高騰し需要減・供給増で需給均衡すると見た。停電は、品不足であり、電源は誰でも開発できる時代、供給力不足なら即時電源建設可能と装った。電源・小売りで新規参入・退出自由という競争促進が、電力の低廉安定供給に有効である。且つ効率化が進み料金も低下すると喧伝された。
3,現状をどう評価するか。競争政策の専門家は、発電・送配電・小売りという垂直的な取引関係を内部に持つ大手電力会社を分割することが社会厚生上望ましいか一概に言えない。垂直統合は、取引コスト低減、不慮の事故生起時の安定供給確保に寄与する。他方垂直統合は、独立系の発電・小売事業者の送配電アクセス困難、競争が鈍る可能性がある。需給調整市場の整備の姿、自然災害対応の議論も重要と指摘する(大橋弘「競争政策の経済学」21年4月)。競争重視・独禁法強化の論者も現実を前に判断先送りである。
日本を前に進める官僚・自由化論者は、電力自由化万歳であった。卸電力市場開設、長期的設備投資市場整備で、安定且つ低廉な電力供給可能と見た。最近ある自由化論者の発言が流れた(NHK6月13日「ある日電気が来なくなる!?」。「電力料金は安くなると楽観していたが・・」という発言であった。耳にしたとき、吉田茂首相の南原繁東大総長批判を思い出した。
4,現状の需給逼迫状態の打開を探る動きもある。「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会」は、22年度電力需給対策として、引き続き厳しいLNG燃料購入環境を踏まえ、点検中の発電所運転開始の確認、追加供給力(kW)の公募、燃料確保に向けたkWh公募を提示した(7月20日)。これは小手先対応である。需給逼迫は今後も継続すると示唆した。
又中期の視点から「卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の在り方に関する勉強会」は、現行制度の下で安定供給を図る対策を検討した。そして取りまとめを公表した(6月20日)。目指すべき姿として①電力の安定供給確保、②持続可能、効率的かつ公正な電力供給の実現を掲げ、日本全国で最適運用が可能な需給運用・市場システムを作ると述べる。これまでの電力システム改革(自由化)が機能してないことを明らかにした。問題は、目指す方向である。
経産省は、「あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会(以下作業部会という)」を立ち上げた(7月29日)。
作業部会は、需給運用上の不確実性が拡大する中で 日本全国で最適運用が可能な需給運用・市場システムを目指し、①中長期(数年~2か月前)的に確実な燃料確保の姿、短期(実需給1週間前)の安定供給の電源起動とメリットオーダーを検討する。②そして卸電力市場の先物取引拡大で燃料確保に先見性を付加するという。機能しない卸電力市場の欠点に継ぎ接ぎを試みる。そして欧米市場を参考に、先物に金融資本の活用を期待する。投資金融は、投資的性格でなく投機的性格が強い。果たして安定供給に寄与するだろうか。また先物市場で需要見通しを明確にする試みは、効果不明の思い込みで、対外的な購買力強化にならないであろう。
電力システム改革の本質を問う問題、安定供給と料金安定対策としてどのような体制が適当か、つまり競争政策(自由競争市場)か産業政策(安定供給義務と公益事業的扱い)か等の問題提起を回避している。
5,繰り言となるが、国内の電力需給安定と合理的な価格形成を図るためには、次を考慮する必要がある。電磁気学に従えば、電力産業は、電場を提供している産業である。需要家は、スイッチ一つで電場の利用を行う。電場の提供とは、電力会社が、需要家のつなぐコンセントに、常時電場(電流としての電子)を、発送配電というサーキット内で需要を見越し維持することである。
自由化で発送配電を分離すると、第一に発電事業者は、電場販売で在庫ゼロを合理的と考え、発電は利潤最大化を目指し、需要を少なめに見積もる傾向となる。第二に発電部門と送電部門は、契約関係で言えば、不完備契約となる。そこでは情報不十分で、投資は必要水準より少なくなる。第三に電力産業は、自然条件や需要の視点を含めて、不確実性が大きい。投資リスクが高いので、投資を躊躇する。また需要家に必要なベース電源の共有・負担が必要である。((南部鶴彦「電磁気学と経済分析の接合の試み」(公益事業研究72巻第1号20年9月)等の指摘)。
また対外的にエネルギー確保の方策を熟慮する必要がある。日本が持てるのは、国民(需要家)負担の計画的な購買力だけである。それを分散すれば、購買力は低下する。また一定の計画がなければ、調達量を確定できないであろう。この意味でも、電力業は、産業政策的管理が適当である。過去30年間の消費者重視・競争促進・市場任せの競争政策は、功を奏していない。再考が必要である。
6,日々電力需給逼迫問題がマスコミを賑わせ,大本営本部発表は、国民を困惑させている。ある高名な政治ジャーナリストは岸田文雄政権の課題(難題と難局)として、11項目を挙げた。コロナ感染危機、安保防衛力整備、物価高騰対策、エネルギー・電力ひっ迫、10増10減区割り法案、人口減少社会、新しい資本主義、150兆円GX投資、日銀総裁人事、憲法改正問題、外交・安全保障である。その中に電力需給逼迫を挙げた。優先課題として産業政策で今後の電力システムを見直すことを期待したい。
【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。