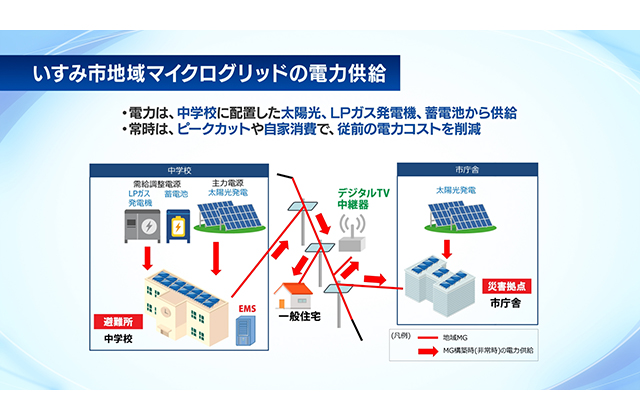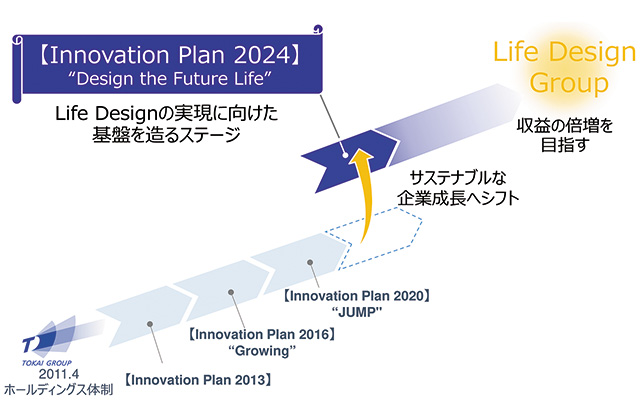【識者の視点】杉山大志 /キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
10月31日から英国グラスゴーで温暖化防止国際会議・COP26が開催される。 交渉は膠着状態で事実上何の成果もなさそうだが、中国だけは最大の利益を得ることになりそうだ。
今春に米国が開催した気候サミットでは、米国バイデン政権、ドイツ・メルケル政権、フランス・マクロン政権、英国ジョンソン政権、それに日本の菅政権と脱炭素に熱心な政権がたまたま出そろい、G7(先進7カ国)諸国は軒並み「2030年にCO2半減、50年にはゼロ」を宣言した。ただし、中国をはじめ新興国はそのような宣言をしなかった。今度のCOP26では、G7が新興国に同様の宣言を求める構図になっているが、新興国が応じる気配はない。
まあ、G7も言っているだけで実行不可能であるのみならず、欧州では既に無理な再生可能エネルギー依存の政策がたたって、エネルギー価格の高騰が生活費の圧迫やインフレを引き起こしつつあり、政治問題化している。早晩、G7の無謀な目標は問題視され、見直しが入るだろう。そんな中で新興国が経済成長の足かせになるような宣言をすることはばかげている。G7の圧力には説得力も政治力も無く、新興国が譲ることはなさそうだ。よって事実上は何の成果も無い会議になりそうなのだ。
欧米が一変して中国賞賛 石炭火力輸出支援停止のワケ
ところがここで、中国が救い船を出した。習近平国家主席は9月、「海外の石炭火力発電事業への資金提供を止める」と発表した。
この方針で中国は大いに感謝された。COP26の議長であるアロク・シャルマ氏は「習主席が海外での新規石炭プロジェクトの建設を中止すると約束したことを歓迎する。これは私が中国を訪問した際に議論した重要なテーマだった」と述べた。米国のジョン・ケリー気候変動対策特使も「素晴らしい貢献だ」と言い、最近すっかり嫌われ者の中国に最大級の賛辞が送られたわけだ。
だが習氏は実質的にはまだ何も譲歩していない。まず、具体的に「いつ」資金提供を止めるのか言及していない。中国が着手した7000万kW(19年時点)もの石炭火力プロジェクトを止めるとは、一言も言っていないのだ。これは、日本の全石炭火力4800万kWをはるかに超える水準だ。
また「どの」資金提供を止めるかも言っていない。公的なものだけなのか、民間を含めるのか。プロジェクトファイナンスだけを対象にするのか否か、など、実質的に何を止めるのかは不明だ。
その一方、中国国内では現在、世界の石炭消費量の半分を燃やしており、今後ますます増える。日本の20倍以上の10億kWの石炭火力発電所があり、毎年、日本の全石炭火力発電設備容量に匹敵する大量の発電所が建設されている。
それにもかかわらず、欧米の政権はここのところ、温暖化問題に限らず中国に好意的で、中国の体制を非難しない。なぜだろうか。
「中国はCOP26という機会をフル活用しているのだ」と主張する英国貴族院議員のマット・リドレー氏は、次のように指摘する。
「グラスゴーでの協力を中国に求めるために、英国と米国はどのような譲歩をしたのか? それは有益な譲歩なのか?」
「習近平の今般の発表の数週間前に、バイデン政権が、ウイルスが武漢の実験室起源かどうかは『分からない』とした報告書を発表したのは偶然だったのだろうか?」
「米国のバイデン大統領、ハリス副大統領、ケリー特使は、最近の人権に関するスピーチで、中国について言及することを慎重に避けている。なぜか?」
「香港で自由が弾圧されているのに、英国が黙っているのは偶然だろうか?」
「内容不明な『海外石炭事業の停止』宣言によって、事実上何の成果も無いであろう『国連気候会議』が『成功』したと演出してみせることで、中国は数々の譲歩を引き出したのではないか?」
「私は、明白に宥和政策があったと言っているわけではない。だが中国のリップサービスを頼みの綱にしてしまっている英米が、このタイミングにおいて、ほかの案件で中国を厳しく批判できるとは思えない。中国はもちろんこの機会を最大限利用する。こんなゲームをすることは有益なのだろうか」
「いま中国は、かつての英国のお株を奪って『分割統治』を仕掛けている。つまり米国と豪州には敵対する一方で、英国には愛嬌を振りまいている」
「中国共産党の機関紙『環球時報』は先月、米国は『不安定で支配的』であるが、英国は『協力的で従順だ』と書いている」――。
「超限戦」を仕掛ける中国はCOPも利用するのか
COPは「超限戦」の道具 G7との駆け引きはいかに
中国はこの美味しい構図を継続させようとするだろう。もしCOP26で「グラスゴーアクションプラン」が合意され「継続的に中国と協議する」などとなったら、今後何年間も同じような譲歩を続けることになるのだろうか。人権は、パンデミック対策は、どうなるのか。G7は見事中国の術中にはまってしまうのだろうか。
いま中国は、人権、領土、貿易、技術などを巡って、国際的に孤立気味である。そこで、これらの重要な外交問題についてG7を分裂させ、譲歩させるために、気候変動への協力を装っている。
「超限戦」という言葉がある。中国の軍人たちが1999年に発表した概念だ。いまや戦争に平時と戦時の区別なく、技術に軍事と民事の区別なく、武器にリアルとバーチャルの区別は無い。あらゆる境界を越えて、国家は常に自らを強め敵を弱める。恒常的な戦争状態にあるという考え方だ。
超限戦が目指すのは、習氏が掲げる「中国の夢」である中華民族の偉大な復興の実現だ。気候変動はその最も便利な道具だ。
ちなみにCOP26の正式な交渉議題は国際的な排出権取引のルールなどだが、全ての国が数値目標を持つ今、国際的な排出権取引が大々的に活用できるようになる可能性はほぼゼロだ。他にも議題はいくつかあるが、どれも細かくてあまり重要ではない。重要なのは中国などが正式な交渉議題と別に何を宣言するかと、その広範な外交関係への影響である。中国が仕掛ける超限戦としてのCOP26で、G7がどう対処するのか。大きな構図にこそ注目しよう。
すぎやま・たいし 1991年東京大学理学部卒。93年同大学院工学研究科物理工学修了後、電力中央研究所入所。電中研上席研究員などを経て、2017年キヤノングローバル戦略研究所入所。19年から現職。