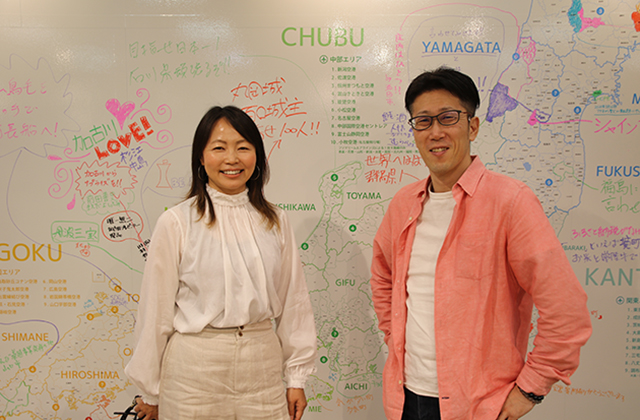【福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.5】石川迪夫/原子力デコミッショニング研究会 最高顧問
1979年3月、米TMI(スリーマイルアイランド)発電所で炉心が溶融する事故が起きた。 炉心溶融は原子炉の圧力上昇に気付き、注水した途端に発生している。
前号の溶融炉心図に続いて、今回はTMI事故の説明に入る。
事故は1979年3月28日午前4時に起きた。発端はトラブル発生による原子炉の停止後に、開いた安全弁が閉じなかった故障に始まる。それに気付いた運転員が弁の元栓を閉じたのが約2時間後だ。蒸気の流失は止まったが、その時点で原子炉の水位は半減していたが、運転員はそれに気付かなかった。このぼんやりが、トラブルを大事故に拡大させた。
元栓が閉じたので、行き場のなくなった崩壊熱は、原子炉の温度・圧力を上昇させる。圧力上昇に気付いた運転員は圧力を下げようとして、停止していた一次冷却ポンプを動かして水を入れた。この途端に、炉心溶融が起きた。トラブルから3時間後のことだ。
原子炉圧力は下がるどころか急上昇した。それも2分間に5・5Mpという、無茶苦茶な上昇だ。運転員は慌てて安全弁の元栓を開いて減圧を試みたが、圧力は下がらない。なぜなら、炉心熔融が起きるような巨大な発熱が炉内で誕生していたからだ。
同時に、一次冷却配管の放射線指示が急上昇している。燃料破損が起きた事は明かだ。発電所に緊急事態宣言が発令された。
午後3時間15分、ポンプを止めたところ原子炉圧力は少し低下した。だがその間に、安全弁からの蒸気を水に戻すレットダウン・タンクが、2度にわたり破壊した。10時間後には、格納容器の内部で水素爆発が起きた。
注水で圧力が急上昇 前代未聞の不可解な事故
以上がTMI事故の概要だ。圧力を低下させるために原子炉に水を入れたら、圧力が急上昇して燃料棒が溶け、発電所の放射線が上昇した。前代未聞の不可解な事故だ。
原子炉内部の損傷は、前報のスケッチ図の通りだ。炉心は熔融し、その上に燃料デブリが堆積している。だが、炉心の外周にある燃料棒や制御棒案内管は、炉心溶融などどこ吹く風とばかりに元の状態で残っている。以上がわれわれの知る、世界で最初の炉心溶融の実体だ。
ところが、原子炉の外は大荒れで、大嵐の跡のさながら全面的な破壊だ。2度にわたるレットダウン・タンクの破壊、10時間後の格納容器内部での水素爆発、記録にはないがその他にもいろいろあったろう。
タンクの破壊には諸説あるが、最初の破裂は水素の大量流入による過圧破壊、二度目の破壊は水素爆発と、僕は考えている。
水素の大量発生は、原子炉の場合、高温のジルカロイと水の酸化反応しか考えられない。蒸気発生器の二次側にたまっていた復水が、冷却材ポンプの作動によって一挙に原子炉に送られ、高温のジルカロイと反応して大量の水素ガスを発生させたのが、原子炉圧力急上昇の原因だ。
さらに考えれば、ジルカロイ・水反応は大きな発熱反応であるから、この熱で炉心溶融が起きたとの説が出るのも当然だ。
レットダウン・タンクが破壊すると、原子炉で発生した水素ガスは、安全弁を通って格納容器へ直行し、中の空気と混じって爆発性ガスと化す。このガスが10時間後に、何らかの衝撃によって爆発した。TMIで見た格納容器内部の写真では、エレベータ付近に破壊が集中していたという。爆発は一度だけだったらしい。制御室の運転員は、この爆発音をダンパーの閉じる音と聞き違えている。運転員の証言は信頼がおけないのだ。
その後のTMIの経過は、原子炉冷却水に混入した水素ガスを約1月かけて除去し、4月末に事故終結宣言の発布に至った。NRCデントン部長の采配である
TMIの格納容器への入構は、今日なお特別許可が必要という。炉心熔融を起こした水素ガスは放射能を伴っているため、格納容器内部の汚染が非常に高いからだ。
話を廃炉に移す。事故後約15年たった90年代中頃、TMIは遠隔操作機械を使って熔融炉心の約98%を取り出した。これで廃炉が始まるかと思ったのだが、邪魔が入った。溶融燃料の運搬先で反対運動が起きたからだ。
予定の運搬先は、ニューメキシコ州の南、メキシコ国境近くにあるWIPP(Waste Isolation Pilot Plant)という名の核廃棄物の隔離埋設試験施設だ。原爆の開発・製造でできた放射性廃棄物を処分する目的で作った、地下約600m深さにある岩塩層の施設だ。
反対運動は、同じニューメキシ州の北部にある有名別荘地、サンタフェで起きた。WIPPから300㎞も北に離れているが、反対運動は成功し、運搬は休止となった。取り出された溶融炉心は、今、アイダホ州にある国立研究場(旧NRTS)の仮置き場で保管中という。
依然高い放射能線量 進まない廃炉工事
その後、TMIの廃炉工事は進んでいない。残余の溶融炉心と格納容器内部に付着した放射能の線量が高く作業に適さないとの理由だが、その通りであろう。
熔融炉心が出す放射能による汚染には毒性の強いプルトニウムが混入しているので、除染工事の方法や、工事費用の見積りが難しいのであろう。
その先輩が再処理工場だ。使用済みの燃料からウランやプルトニウムを回収した後の廃棄物には、天然には存在しなかった放射性物質が含まれる。これらの体内への取り込みを防ぐために工場は各種の防護設備を備えているが、廃棄物がこぼれたりするとその除染作業は大変だ。
炉心溶融が起きた炉の廃炉工事は、再処理工場に似ている。汚染全体にプルトニウムそのほかの放射能の付着があり、除染費用のめどが付かないのだ。
お金の話が出たついでに、事故炉の廃炉費用について述べる。TMIの溶融炉心取り出し費用はざっと1000億円だった。チェルノブイリで新設した石棺全体を覆う建造物の費用が1700億円だ。
福島第一発電所の廃炉予算は、事故直後に東京電力が計上したのは約2兆円だったが、16年12月に経済産業省が発表した原子力損害賠償・廃炉等支援機構の試算は8兆円に跳ね上がっている。その理由は不明確だが、額は諸外国と較べて数倍高い。
いしかわ・みちお 東京大学工学部卒。1957年日本原子力研究所入所。北海道大学教授、日本原子力技術協会(当時)理事長・最高顧問などを歴任。
・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.1 https://energy-forum.co.jp/online-content/4693/
・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.2 https://energy-forum.co.jp/online-content/4999/
・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.3 https://energy-forum.co.jp/online-content/5381/
・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.4 https://energy-forum.co.jp/online-content/5693/