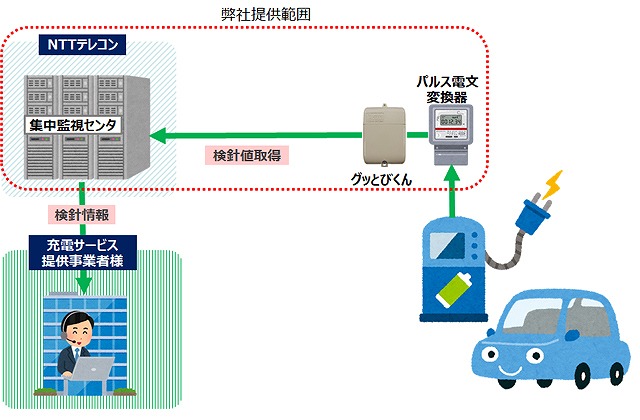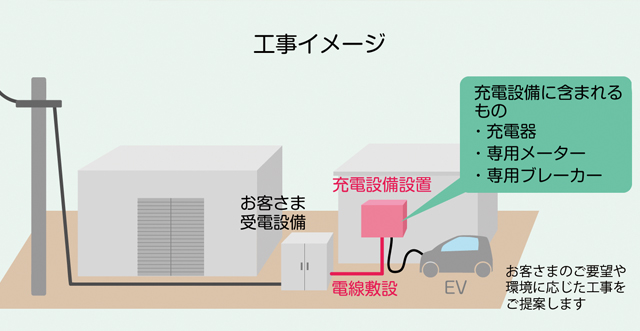【論点】米国の中東政策/須藤 繁 帝京平成大学客員教授
トランプ前米大統領はパレスチナ和平プロセスを無視、イランとの核合意離脱など中東外交で「負の遺産」を残した。
新大統領は政策の再構築に乗り出すが、域内の勢力均衡は大きく変化しておりイランとの関係修復は困難が伴いそうだ。
米国トランプ前大統領は、第二次世界大戦以後、歴代の大統領が世界を導くために採用した外交理念の全てと決別したといわれる。その理念とは、大きくはリアリズム(パワーバランスを維持して影響力を行使)とリベラリズム(国際協調の推進により国際秩序を実現)に収斂するが、トランプ政権は経済的利益に焦点を当てるだけで外交政策の理念をほぼ完全に無視した。
そのトランプ政権は、いくつかの「負の遺産」というべきものを遺した。環境政策ではパリ協定からの離脱が挙げられる。
外交活動の相手は責任ある政府・国家であり、感情のある国民である。トランプ政権の外交政策の負の遺産には、米軍基地の撤退、貿易合意からの離脱があり、中東政策の誤りが挙げられる。
パレスチナとの仲介を放棄 イランへの対抗路線構築
中東和平に関しては、米国はパレスチナの仲介者の役割を果たしてきたが、トランプ政権はその枠組みを完全に放棄し、和平プロセスの一切を無視した。パレスチナ人は弱体で当事者たりえないとし、イランと対抗するため、スンニ派アラブ諸国をイスラエルと協力させる路線を構築しようとした。
在イスラエル米国大使館をエルサレムに移転し、パレスチナ難民への資金拠出を停止し、イスラエルによるゴラン高原編入を認めた。さらに、西岸地区の一部併合の道筋を描き出したのもトランプ政権の4年間で行われたことである。
イランの核協議は、オバマ政権下の2015年7月14日に最終合意された。核合意はイランに対し制裁解除と原油輸出の再開を保証し、テロ支援につながる外貨を確保させるものであり、イスラエル、サウジアラビアを筆頭にアラブ諸国は大きく反発した。中でもサウジは合意の翌日、核合意への対応としてイランが支援するイエメン・フーシ派への攻撃をエスカレートし、拠点を奪還している。
米国は18年5月イラン核合意に関しては一方的に離脱し、制裁措置を強化した。イランは核合意で定められた限界を超える行動を取り、イラク、シリア、イエメン情勢に介入することで、中東のパワーバランスを変化させた。
トランプ政権の4年間で起きたことは、イスラエルと湾岸アラブ諸国の連携強化であった。中でもトランプ大統領が初めて外遊先として選んだサウジは、米国製先端兵器を大量に導入し、反イランで連携することを通じてイスラエルと良好な関係を構築した。
その見返りというべきか、トランプ大統領は記者殺害への関与が疑われたムハンマド皇太子を擁護し、イエメン内戦に対する同国の軍事介入を全面的に支持した。
一方、イスラエル、UAE、バーレーンは20年9月15日、米ホワイトハウスで国交を正常化させる合意文書に署名した。これらの動きは米国の反イラン包囲網の拡大を意味し、安全保障の分野で中東地政学の枠組みは大きく変化した。
こうした米国の対応に対し、イランは軍事力の強化で対抗、19年秋までに無人機(ドローン)および巡航ミサイル攻撃でサウジの石油関連施設を攻撃できるまでに戦闘能力を整備した。
また米国の離脱後、イランは核合意を破る核兵器開発に着手し、本年1月には短期間で核兵器に必要な90%レベルに引き上げられる20%レベルへの核濃縮を始めた。これらは地域内のパワーバランスの均衡を求めてのものである。
バイデン政権にとっては核合意への復帰が対イラン政策の軸になるが、大統領はEUを仲介させる条件でイランとの対話を用意することを表明している。米国は本年6月のイラン大統領選挙で保守強硬派の勝利を阻止したい考えであり、その点では対イラン経済制裁を解除してビジネス関係を再開したいEU諸国と思惑が一致する。
バイデン大統領がイラン核合意への復帰の可能性を示唆する一方で、イスラエルによるパレスチナ地域の入植活動やサウジにおける人権侵害を問題視していることも重要である。
 バイデン政権のイラン政策は核合意への復帰が軸になる
バイデン政権のイラン政策は核合意への復帰が軸になる
バイデン政権が抱える難題 中国ファクターと核合意
それでは、こうした基本構造の中で、バイデン政権は今後どのようなイラン政策を取るのか。具体的な方向はまだ確定しないものの、二つの出来事を踏まえ、事態の推移を注視したい。
その第一は中国ファクターである。3月27日、イランのザリーフ外相が中東歴訪の一環でテヘランを訪問した中国の王毅外相とイラン・中国包括的協力協定に署名した。協定は16年1月に発出した包括的戦略パートナーシップ共同宣言に基づくもので、経済や文化などの分野で今後25年間にわたって両国関係を発展させる。
協定は、イランに中国からの軍事・政治面での後ろ盾と原油輸出を通じた外貨獲得という経済的利益をもたらす。協定が20年6月の閣議で承認されていたにもかかわらず、署名が先延ばしされた理由には、米国大統領選挙の結果に配慮したことが考えられる。イランは、米国からの制裁を無効化する手段として、今回、中国への接近という保険的措置を講じた。
第二は、4月6日にイラン核合意関係国がウィーンで開催した合同委員会が二つの専門部会の設置を決めたことだ。専門部会は、イランによる核合意の順守と米国による対イラン制裁解除に向けた措置を分担して議論する。米国とイランは、欧州を介してようやく間接協議を実施できるようになった。
専門部会の設置により、プレーヤー全員がステージに登場しつつあることは歓迎される。他方、地域の軍事バランスが18年当時とは大きく変わり、イラン側がこれを是正するには弾道ミサイルの開発に取り組まざるを得ない事情を抱えた以上、核合意への立ち戻りを楽観視することはできない。
 すどう・しげる 1973年中央大学法学部卒。石油連盟、三菱総合研究所、
すどう・しげる 1973年中央大学法学部卒。石油連盟、三菱総合研究所、
国際開発センターを経て2011年帝京平成大学教授。21年から現職。専門は石油産業論。