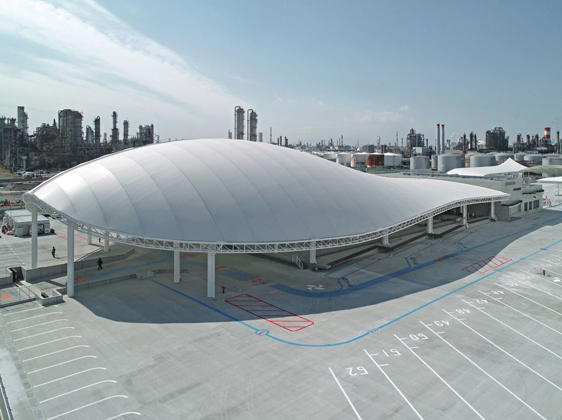【論説室の窓】竹川正記/毎日新聞論説委員
10年前の東日本大震災・福島第一原発事故で日本はエネルギー政策の転換を迫られた。 だが、政府はこの間、問題先送りを続けてきた揚げ句、「脱炭素化」を一足飛びに進めようとしている。
「十年ひと昔」というが、2011年3月11日以降の福島第一原発危機の記憶は今も鮮明だ。1、3、4号機が連続して水素爆発を起こし、一時はメルトダウン(炉心溶融)による放射性物質拡散の深刻な影響が東日本全域に及ぶことも想定された。欧州の大使館員や外資系企業の社員らは相次いで東京を離れた。同盟関係にある米国大使館はとどまったが、追随していれば、東京はパニックに陥っていたかもしれない。
財務省幹部が当時「国民に仕える身として逃げるわけにはいかない。家族にも東京に残るように言い渡した」と語った姿が今も印象に残る。私も正直、同じような思いだった。避難を迫られた福島の人々と比べようもないが、原子炉の冷温停止が確認されるまで東京でも緊迫感が続いた。
電力不足で石炭火力依存 問題先送りを続けた政府
深刻な電力不足に見舞われた首都圏では3月14日以降、約2週間にわたり断続的に計画停電が実施された。電力不足からの脱却が当面の最優先課題となり、原料が安価な石炭を中心に火力発電が急ピッチで増強された。
当時はシェールガス革命が本格化しておらず、LNGの輸入コストは割高だった。バブル崩壊以降の長期的な経済低迷による税収減少と累次の景気対策に伴う歳出膨張で国の財政状況は既に主要国で最悪の水準だった。財務省内では「LNG輸入が急増すれば、慢性的な経常赤字に陥り、国債暴落など財政危機の引き金になりかねない」と懸念する声もあった。
一方で、LNGに比べて発電時のCO2排出量が多い石炭火力への依存は、地球温暖化対策に逆行するジレンマが指摘されていた。
「安全神話」が崩壊した原発の位置付けを含めてエネルギー戦略をどう見直し、電力の安定供給と温暖化対策の両立を目指すかは、大震災直後から日本が突き付けられた最大の課題だった。
旧民主党政権は12年に「革新的エネルギー・環境戦略」を発表し、「30年代に原発稼働ゼロ」を掲げた。代替電源として再生可能エネルギーの普及を急ぐとし、太陽光発電などの固定価格買い取り制度(FIT)を導入した。買い取り価格を高く設定したため、設備導入が比較的容易な太陽光発電は確かに伸びた。だが、海外で再エネの主力となっている風力発電導入は進まなかった。日本の大手電機メーカーが軒並み風車製造から撤退したのもそんな事情からだ。
再エネにとって、日本は欧米などに比べて気候や地理的条件が悪い。基幹電源化を目指すなら、蓄電池開発や送電網の増強など包括的な推進策が必要だった。しかし、旧民主党政権のエネルギー政策はそんなスケール感が乏しく、脱原発・脱炭素依存に全くの力不足だったと言わざるを得ない。
13年末に自民党の安倍晋三政権(当時)に交代して以降、水面下で原発回帰の道が探られた。原発はカーボンフリー電源で、再エネと異なり発電量が天候に左右されない。安倍政権下で策定されたエネルギー基本計画は原発を「重要なベースロード電源」と明記。30年度の電源構成目標の原発比率は20~22%とした。
しかし、国民の不興を買うことを恐れてか、肝心の再稼働の判断は原子力規制委員会と地元自治体に丸投げした。地元住民の不安解消に欠かせない避難計画策定にも積極的に関与しなかった。原発の位置付けはあいまいなままで、国民の不信は払拭されなかった。
この結果、大震災後に再稼働した原発は9基に止まり、18年度の原発比率はわずか6%。エネ基の目標は「絵に描いた餅」となっている。再エネ比率は17%と大震災前から倍増したが、発電の不安定さは解決されていない。
にわか仕立ての脱炭素化 原発の位置付け定まらず
原発の再稼働停滞の穴埋めと再エネの調整電源を引き続き担う火力発電の割合は7割超と高止まりし、日本は世界的な脱炭素化の潮流に大きく出遅れた。専門家は政府の無策ぶりをエネルギー版「失われた10年」と批判する。
菅義偉政権は昨年10月、50年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル(CN)」を宣言したが、にわか仕立ては明らかだ。経済産業省はCNに向けてグリーン成長戦略を策定したが、技術革新への期待感を総花的に網羅した「作文」の域を出ず、実効性が疑われている。原発に関する記述は「可能な限り依存度を下げつつも最大限活用」と矛盾に満ちている。
カーボンニュートラル宣言はにわか仕立てが否めない
関係筋によると、政府や経産省は「まずは野心的なCN目標をぶち上げて、世論の脱炭素化ムードを醸成することが重要」と考えているという。その上で再エネ活用にはコストや技術面で限界があることを国民に徐々に浸透させ、その延長線上で原発のリプレースや新増設方針を打ち出すシナリオを描いているとされる。
だが、福島原発事故の影響は今も続いている。避難者がいまだに数万人に上り、廃炉作業は何十年続くか分からない。そんな状況下で「脱炭素化」を隠れみのにするような原発復権論が国民に受け入れられるとは到底思えない。
CN目標達成への道筋づくりは菅首相や経産省が喧伝するようなバラ色の絵図にはならない。日本にとってオイルショック以上の厳しい試練となるだろう。電源の脱炭素化を進めるには、産業構造や生活スタイルの抜本的な転換も必要だからだ。世論調査では、原発への不信や不安が大きい一方、「即時廃止」を求める意見は少数派にとどまっている。日本のエネルギーの現状を直視した国民の冷静な認識が背景にあるのだろう。
そうならば、政府がまずやるべきはこの10年間のエネルギー無策を真摯に反省することだ。その上で、国民と幅広く対話しながら原発の位置付けも含めたCN目標実現の道筋を探ることだろう。有識者会合のお墨付きを得て新たなエネ基や電源構成目標を決めても再び「絵に描いた餅」になるだけだ。国民の理解なしにエネルギー政策の見直しは進まない。3・11が遺した貴重な教訓だ。