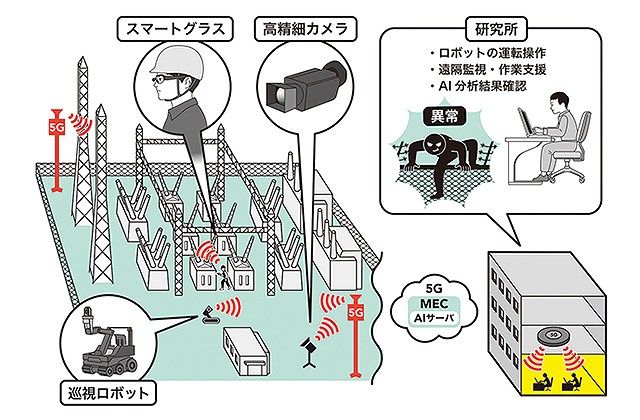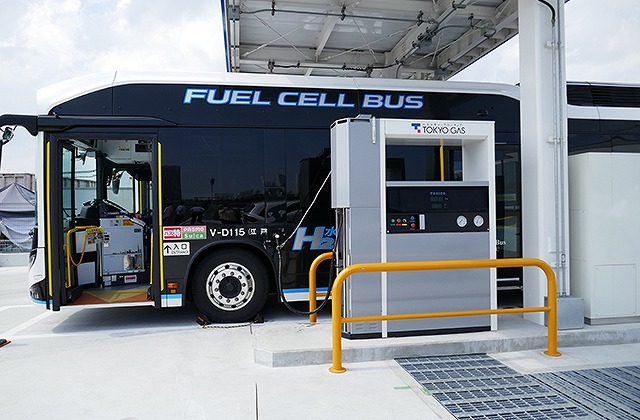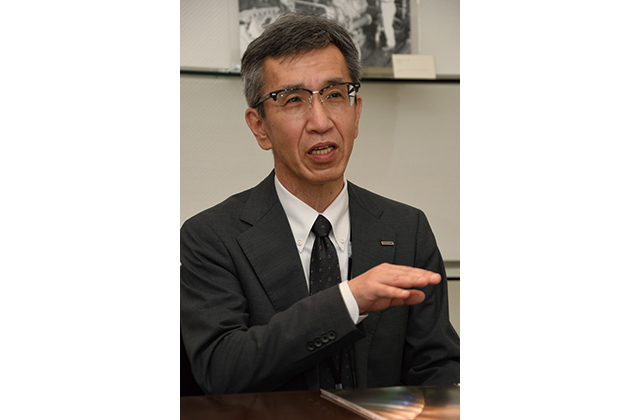【識者の視点】松田世理奈/阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁護士
大手電力を含む4社への公取委立ち入りは、業界の枠を超えて社会に対して大きな衝撃を与えた。
今後の展開を踏まえ、事業者には激化する競争に対する新たな備えが必要となる。
報道各社は4月13日、「中部電・関電に公取委立ち入り」「大手電力カルテルの疑い」などと大々的に報道した。
公正取引委員会が、電力販売に関するカルテル(不当な取引制限)の疑いで、中部電力、中部電力ミライズ、関西電力、中国電力の計4社に立入検査を行ったというのだ。また、公取委は同日に、中部電力、中部電力ミライズ、東邦ガスの計3社について、別の被疑事実により立ち入ったとも報じられている。
報道によれば、中部電力、中部電力ミライズ、関西電力、中国電力の4社は2018年ごろから、中部、関西、中国の各エリアの「特別高圧と高圧の電力販売」に関し、顧客獲得競争を制限するようなカルテルを結んでいた疑いがある。
また、中部電力、中部電力ミライズ、東邦ガスの3社は、同じく18年ごろから、中部エリアの「商店や家庭向けの低圧電力や都市ガスの料金」について、値下げ競争をせずに価格を維持することを目的としたカルテルを結んでいた疑いがある。
いずれも、独占禁止法で禁じられているカルテルが結ばれていた疑いがあるという点で共通している。
カルテルとは、競争事業者同士が市場の独占を目的として、販売価格や販売地域などに関して、互いに競争を制限するような示し合わせを行っていたことをいう。そのような行為があった場合には、独禁法違反として、事業者に対し行政処分などが下されることになる。
当事者申告で発覚か 結果次第で多額の課徴金
どうしてこのタイミングで今回の事件の調査が行われることになったのか。
公取委は、事件調査の具体的な内容に関して、正式な行政処分を下すまで一切対外的に発表しない。また、事件調査の端緒については、正式な行政処分を下した後でも公表せず、秘密を保持している。そのため、今回の事件について、公取委が立入検査を行った契機や、その判断材料が何であったのかという点については、正確なところは不明である。
他方で、一般論として、カルテルのように通常は当事者同士にしか知られない行為については、リニエンシー、つまり当事者による自主的な公取委への申告により発覚することが多い。今回の事件についても、関係者によるリニエンシーにより発覚したのではないかとみる向きが多い。
なお、事業者が立入検査などの正式調査が始まる前に最も早くリニエンシーを行うと、その事業者は公取委の行政処分を免れることができる。
今後は、公取委による関係者の取調べなど、事件の調査が当面続くことになる。調査期間は、最近の例を平均すると1年半程度になると思われるが、事案の複雑さや事業者の協力度合いによって前後し、1年程度で終わる場合や、2年近くかかる場合もある。
調査の結果、公取委がカルテルの事実を認定すれば、事業者に対し「排除措置命令」と「課徴金納付命令」という2種類の行政処分が下される。カルテルの場合に課される課徴金は、基本的に違反行為の対象となった取引の売上額の10%となる。しかし、事業者が違反行為を認めて申告し、公取委の調査に協力することで減算されることがある。
仮に報道された疑いが事実であると認められ課徴金納付命令が下されるとすれば、特に販売金額の高い「特別高圧および高圧の電力販売」が対象となっている事件について、その課徴金が多額に上ることが予想される。