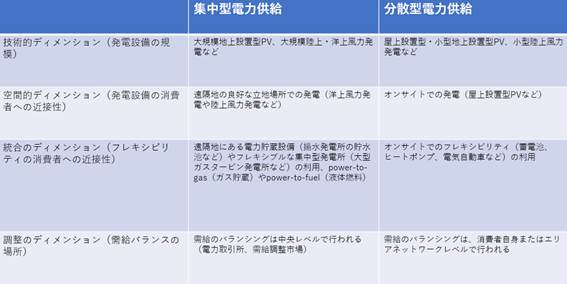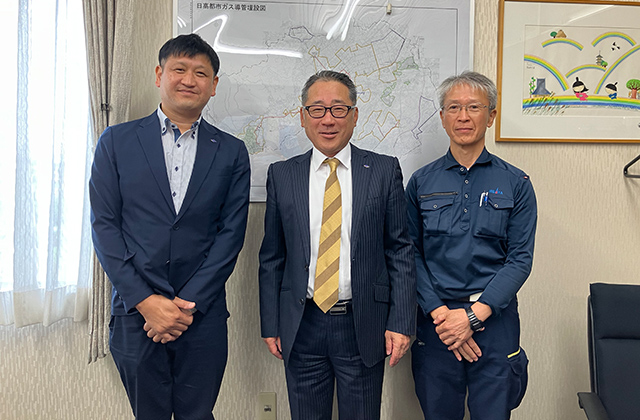飯倉 穣/エコノミスト
1、持続的成長願望ながら
トランプ関税協議、米高騰・備蓄米放出や物価対策に話題が集中する下で、選挙対策の野党の消費税引下げ発言や与党の慎重姿勢が交錯した。今年も経済運営と改革の基本方針(以下基本方針という)の公表があった(25年6月13日)。新しい資本主義の実現を掲げ、賃上げこそが成長戦略の要と述べた。
報道もあった。「骨太方針 減税より賃上げ 閣議決定 選挙前野党と一線」(朝日同14日)。「骨太方針 減税より賃上げ 実質1%上昇 方策乏しく」(日経同)。
基本方針は、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を掲げる。手法は、物価上昇を上回る賃上げ要請である。適切な価格転嫁や生産性向上、経営基盤強化となる事業承継・M&Aを後押しなど、賃上げの環境整備に施策を総動員という。その姿勢は、徒労に終わることを厭わないようである。現状認識の錯覚は、果たして効を奏するか。今回の基本方針の掲げる成長戦略と経済運営を考える。
2、現在の物価上昇要因を直視せず、目玉は賃上げ
「賃上げこそが成長戦略の要」と強調する。持続的・安定的な物価上昇の下、1%程度の実質賃金上昇の定着で、生産性を向上させる。つまり賃上げ、消費(需要)増、投資増、生産性上昇、賃上げ増の経路を狙う。現実の物価上昇要因と経済成長の状況から、飛躍していないか。
24年の経済成長率は、実質0.2%、名目3.1%(23年夫々1.4%、5.5%)だった。輸入物価が落ち着き、企業物価上昇もやや安定(24年前年比2.3%)の後、25年Q1に4.2%、4月4.0%と上昇している。この傾向は何を示しているか。現在の物価上昇は、輸入インフレの後、物価見合い賃上げや企業収益の状況から見て、企業の価格引上げ(含む便乗値上げ)が原因と推量される。円安要因というよりコストプッシュ型インフレである。それが消費者物価上昇(コア前年同月比4月3.0%)も牽引している。このような物価上昇は、需要を減少させ、実質経済の縮小をもたらす。
基本方針は、もう一つ願望を述べている。「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加である。投資目標で、2030年度135兆円、2040年度200兆円を見込む(24年名目105兆円、実質92兆円)。この実現のため賃金や金融所得・資産の増加を資金の流れでつくるという。つまり家計の現預金が投資に向かい、官民一体で国内投資を加速し、企業価値向上を目論む。その具体化で、従来からGXの推進、DXの推進、フロンティアの開拓、先端科学技術の推進、スタートアップへの支援、海外活力の取り込み、資産運用立国の実現を例示している。かけ声は、素晴らしいが実際はどうか。近時の民間企業設備投資(24年実質1.3%増)の現実から、浮き上がって見える。政府の取組みは、所詮将来のこと故なのであろう。
3、それは実現可能か
途中経過の資料の中には、経産省の打ち上げ花火もあった。積極的な政策強化を前提に、潮目の変化と同様の国内投資拡大(官民目標2040年200兆円)を継続すれば、賃上げは春季労使交渉5%相当の名目3%が継続し、名目GDPは約1000兆円(新機軸ケース、名目975兆円、実質750兆円)に達するという(5月26日)。その後内閣も乗る事態になった(総理発言6月9日)。原案で、直ちに数字の意味が、呑み込めなかった。果たして実現性はどうだろうか。
物価を上回る賃上げ期待は、繰言だが、逆転の発想というより成長現象の見誤りである。過去の成長の結果、得られた数値(雇用・資本ストック)を数式化したソローモデルを思い出す。左辺は成長率、右辺は労働力、資本、TFP(全要素生産性)である。その式を見て、投入資本や労働投入すれば成長可能と計算する。あるいはGDP恒等式を見て、財政出動や減税で消費を喚起すれば成長軌道に乗せることが可能という。この種の経済論の継続に危惧するばかりである。これらの成長期待論は、これまでの経済推移を見れば、一目瞭然である。誤りだった。
経済成長とは何か。一般の理解では、技術革新・企業化あれば、設備投資増、雇用増、製品単価低下、賃金上昇の現象を垣間見ることが出来る。マクロ的には、実質経済成長率上昇、企業物価安定、消費者物価やや上昇の姿となる。つまり民間企業行動と設備投資の中身(独立投資)にすべて帰着する。現実直視が第一である。