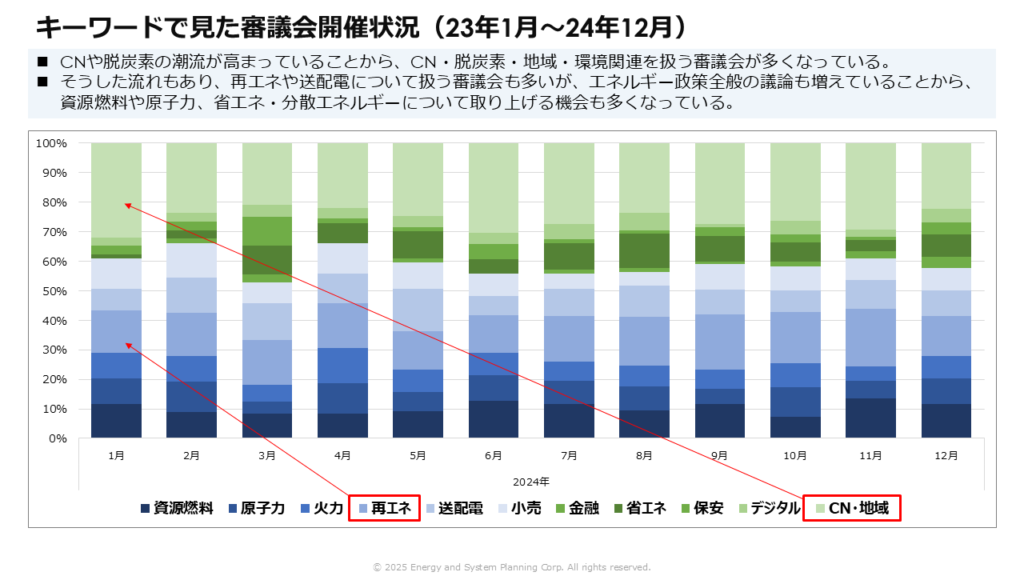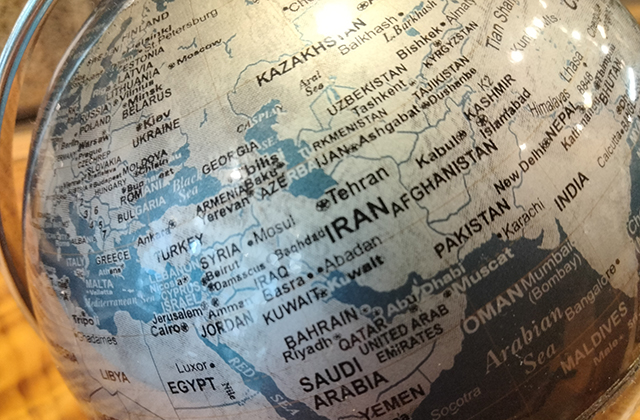トリガー条項の問題点/原発再稼働時の地元同意
Q 今、話題のトリガー条項には、どのような制度上の問題があるのでしょうか。
A トリガー条項は、ガソリン価格の高騰から国民生活を守るために設定された緊急避難的な政策です。トリガー条項は小売物価統計の全国平均価格が1ℓ当たり160円を3カ月連続で超えた場合に、特例規定(暫定税率)を停止し、130円を3カ月連続で下回った時に解除するものです。しかし2011年4月に東日本大震災の復興財源確保のための特例法によって凍結されて以降、発動されたことはありません。
トリガーには対象油種がガソリンと軽油に限られ、灯油、重油、ジェット燃料などが対象外であること、地方揮発油税分の減収(1㎘当たり5200円)による財源問題などがあります。
この制度の最大の問題は発動価格を固定していることです。例えば消費税一つとってみても160円が設定された時は5%でしたが、現在では10%になっています。エネルギー価格や物価の上昇の中で、事実上基準は押し下げられています。
もしトリガーをスタンバイ政策として機能させようとするならば発動価格は物価にスライドさせるなど、いつでも発動できる仕組みを作る必要があります。しかも小売価格はガソリンスタンドで最も高く売られている価格(フリー価格)が基準となっており、競争による効果を組み込んでいません。エネルギー価格の高騰対策を減税や補助金にのみ頼っていることは不自然で、取引慣行や価格表示を含めた公正な競争を前提とする仕組みに変えていく必要があります。
トリガーにはさまざまな議論がありますが、ガソリン税にさらに消費税をかける二重課税を正当化する人はいません。まずここから制度設計を見直していくべきと考えています。
回答者:小嶌正稔 /桃山学院大学経営学部教授
Q 原子力発電所を再稼働する場合、地元の同意は必要とされるのでしょうか。
A 原子力事業者が原子力発電所を再稼働させるか否かを判断するに当たっては、安全性の確保について、原子力規制委員会によって原子炉等規制法に定める基準に適合すると認められることを要するとされていますが、法令上、それ以外に国の判断、または意思決定は要件とされるものではありません。
一方で、従前から、立地自治体(道県および市町村)は住民の安全を確保するため、トラブル時の通報連絡体制の確立などを定めた「原子力安全協定」(正式名称や一部の内容は自治体によって相違があります)を事業者と締結しています。この協定では、「施設変更時の事前協議と了解」条項を設けているなど、再稼働のために規制基準に適合するように施設の変更工事を行った事業者は、立地自治体に対し、事前に協議ないし了解(同意)を得ることが、契約上の義務となっています。
なお、わが国で初めて締結された「原子力安全協定」は、1969年に福島県と東京電力との間で結ばれたものです。それ以降、他の立地自治体でも原子力事業者と同協定を結ぶことが慣例となりました。現在では、全ての立地自治体が締結しています。
また、福島第一原発事故後は、緊急防護措置を準備する区域(UPZ)などの防災対象範囲の拡大もあり、立地自治体以外の周辺自治体も、事業者と協定を結ぶ例が増えています。ただし、その協定の内容は、「事前協議・了解」の項目が無い場合が多いのが実状ですが、地域によっては、「事前協議・了解」を協定の内容に含める場合や、事業者が周辺自治体に再稼働について事前説明を行うなど事実上、事前了解を得ている場合もあります。
回答者:小林 勝/TMI総合法律事務所参与