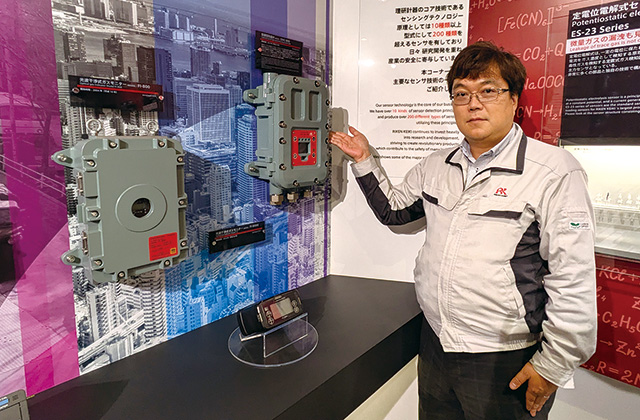エネルギー業界的には不安の中での船出だ。10月下旬の衆院選を受けた特別国会が11月11日召集され、石破茂首相(自民党総裁)が衆参両院で第103代首相に指名。皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て、第2次石破内閣が発足した。
しかし、衆院で少数与党となり、第2次石破内閣は政策面や国会対応で野党の主張への配慮が避けて通れない。しかも、衆院予算委員長に就いたのは、立憲民主党の安住淳・前国会対策委員長。来年夏の参院選を見据え、国会での与野党の攻防が激しさを増しそうだ。

「岸田(文雄)前政権時代にかじを切った原子力推進路線が引き続き堅持されるのか。石破首相の姿勢や官邸スタッフの陣容、原子力理解派議員の軒並み落選などを見る限り、政治主導の勢いが急減速しそうな気がしてならない」。大手電力会社の幹部は、こう懸念を隠さない。
石破氏は最初の首相就任直後こそ、10月4日の衆参両院本会議における所信表明の中で、「安全を大前提とした原子力発電の利活用」に触れたものの、日本経済新聞が12日に報じたインタビューでは「(エネルギー基本計画について)原発比率の低減があり得る」と語り、電力関係者を驚かせた。そして11月11日の国会召集後の会見では、エネルギー・原子力問題への言及が全くなかったことも特筆される。
官邸主導期待できず 鍵握る国民民主と維新
岸田前首相が2022年10月3日の臨時国会の所信表明の中で、「ロシアの暴挙が引き起こしたエネルギー危機を踏まえ、原子力発電の問題に正面から取り組む。そのために十数基の原発の再稼働、次世代革新炉の開発・建設などについて、年末に向け、専門家による議論の加速を指示した」と力説したのとは大違いだ。
その言葉通り、昨年5月の通常国会では原発の「60年超」運転に道を開くGX脱炭素電源法が成立。8月には、関係者の多くが難しいと考えていた、福島第一原発から出る処理水の海洋放出を実現させた。
「岸田政権では、政務秘書官の嶋田隆氏が中心になって原子力政策をリードしてきた。彼が官邸から抜けた影響は大きい。しかも石破氏はそもそもエネ政策に関心がない。これまでのような官邸主導体制はもう期待できないだろう」(永田町関係者)
こうした状況に追い打ちを掛けるのが、エネ政策に造詣の深い議員の相次ぐ落選だ。重鎮の甘利明氏をはじめ、原子力正常化に精力を注いできた鈴木淳司氏、党の電力安定供給推進議員連盟事務局長の高木毅氏、同事務局次長の細田健一氏―。
「政治的には、原子力推進に黄信号が灯った格好になった」(自民党関係者)。再稼働、新増設、中間貯蔵、再処理、最終処分など課題は山積みだ。幸い、国民民主党、日本維新の会は原子力推進を公約に掲げている。どうする! 石破首相。