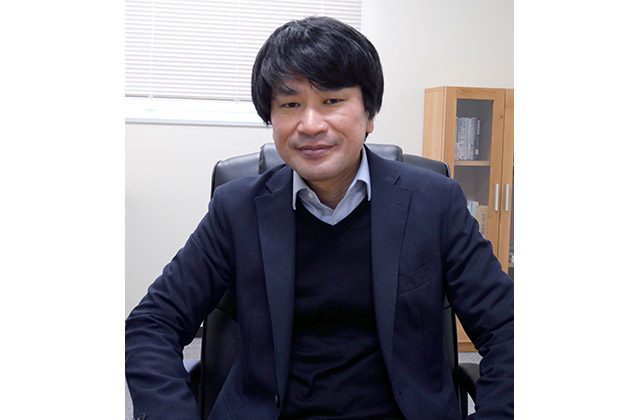VPPを進める上で社会貢献や再エネ利用の最大化などの意義を掲げる。
需要側リソースをいかに獲得するのか。現状や展望について東京ガスに話を聞いた。
【インタビュー】松本幹雄/東京ガスカスタマー&ビジネスソリューションカンパニーソリューション共創部部長

―東京ガスは総合エネルギー企業としてガスや電気の販売を手掛けています。そうした中、法人向けの新しいソリューションとして、VPP事業に本格的に取り組み始めました。
松本 東京ガスグループとして2023年2月に中期経営計画「Compass Transformation 23-25」を発表し、三つの主要戦略を掲げました。一つ目がエネルギー安定供給と脱炭素化の両立、二つ目がソリューションの本格展開、三つ目が変化に強いしなやかな企業体質の実現です。
当社はLNGバリューチェーン上のさまざまな強みを生かして電力事業を手掛けてきましたが、その中からVPPやデマンドレスポンス(DR)を切り出し、20年4月から私どものソリューション共創部が本格展開するソリューションの一つとして事業化をしました。現在、VPPリソースの拡大に向けて動いています。
新たな価値に気付く 丁寧に説明し理解得る
―VPPを進める意義は何ですか。
松本 大きく四つあります。一つは、社会的な貢献という視点です。例えば電力の需給がひっ迫した時にVPPは電力需要を抑える取り組みになります。従来は火力発電所などの発電側で担っていたことを需要側で対応することであり、発電コストを押し上げることなく、安定供給に資することは、社会的に意味があり、大きく貢献できると考えています。
二つ目が再生可能エネルギー利用を最大化することです。再エネ導入量が増えるほど、電力系統の需給バランスが崩れやすくなります。この需給バランスを調整するVPPの意義は高いと考えています。また現状では、「優先給電」という制度があります。これにより、火力発電などの発電側の調整力の限界値を超えた場合、再エネの余剰分は抑制されることになっています。これはもったいない。なので、再エネ余剰分の局面では電力需要の増加を促すのもVPPの取り組みの一つです。結果的に再エネを有効活用し脱炭素につながります。
三つ目がお客さま目線に立った取り組みということです。われわれの部署ではお客さまへのソリューション事業を展開しています。VPPはお客さまにとって対価を得られる仕組みでメリットがあります。そうしたインセンティブを提供することがソリューション事業の一つの狙いです。
四つ目が、改正省エネ法への対応です。昨年、省エネ法が改正され、お客さまにはDRの実施実績について報告義務が課せられました。国の施策に対応する上でも、こうした取り組みを進めることは重要だと考えています。