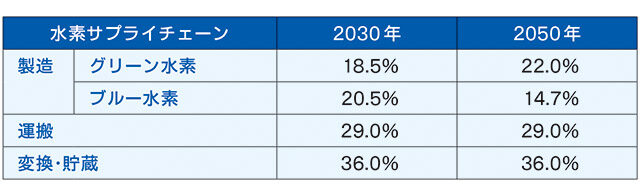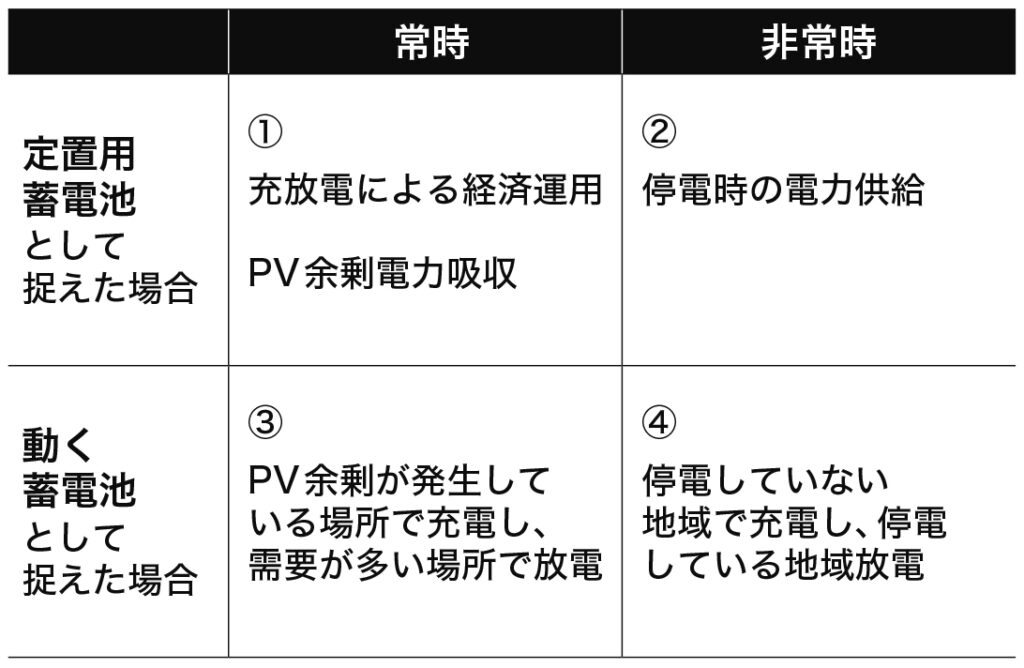東日本を中心にして全国に点在するBWR7地点の現状はどうなっているのか。
再稼働に向けて先行する3地点のほか、対策工事・安全審査中4地点の「現在地」を紹介する。
現存の原子力発電には大きく分けて、原子炉の中で発生させた蒸気を直接タービンに送り発電するBWR(沸騰水型)と、蒸気発生器で高温高圧の水から発生させた蒸気をタービンに送り発電するPWR(加圧水型)の2方式がある。東日本大震災で事故を起こした福島第一原子力発電所と同じ炉系のBWRは、新規制基準に基づく適合性審査の遅れなどから長期停止を余儀なくされてきたが、ようやく今年、稼働ゼロの状況に終止符が打たれようとしている。
東北電力 女川/被災プラント「再出発」へ
再稼働への道のりが終盤に近付くサイトの一つが、東北電力女川原子力発電所2号機だ。震災後、緊急的な安全対策工事を実施。そして新規制基準施行後、2013年12月に女川2号機の適合性審査を申請し、約9年半かけ、原子炉設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可と一連の許認可を取得した。安全対策では地震・津波への備えが非常に重要との考えから、基準地震動を580ガルから1000ガルに引き上げるとともに、想定津波の高さを23・1mと評価した。
工事の特徴は、ほかのプラントでも前例がない、圧力抑制室内の耐震補強工事だ。効率的に現場作業が進むよう、実機模型を製作し工事着手前に技術習得訓練などを行い、着工から約1年6カ月で完了。また、国内サイトでトップクラスの高さの防潮堤(海抜29m、総延長約800m)は、「鋼管式鉛直壁」と「セメント改良土による堤防」で、1000ガルにも耐えられる構造体としている。
 9月ごろの再稼働が見込まれる女川
9月ごろの再稼働が見込まれる女川
提供:朝日新聞
なお、火災防護対策工事の遅れの影響で、安全対策工事完了は今年2月から6月に、そして再稼働は9月ごろを目指すとしている。同社は、女川2号の運転再開を単なる再稼働ではなく「再出発」と位置付ける。「発電所をゼロから立ち上げた先人の姿に学び、地域との絆を強め、福島事故を教訓に新たに生まれ変わる」との決意を込めている。
中国電力 島根/8月再稼働へ工事佳境
昨年8月、原子力規制委員会から工事計画認可申請に対する認可を受け、9月に「使用前確認申請」を行った中国電力島根2号機。今年8月の再稼働、9月営業運転開始という具体的な工程を初めて示したことで、手続きはいよいよ最終段階に入った。
5月の完了を見据え安全対策工事が急ピッチで進むが、懸念されるのがテロに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)を巡る審査の難航だ。原子力規制庁は昨年10月の審査会合で、特重施設設置位置付近の地質・地層構造の評価に当たり、同社が対象から外していた断層と、新たに確認されたシーム(薄い粘土層)について、追加で基礎データを整理するよう求めた。特重施設には発電所本体の工事計画認可から5年以内という設置期限があり、島根2号機の場合、28年8月までに完成しなければ規制委から運転停止命令が出される可能性がある。再稼働スケジュールを揺るがすものではないが、その後の継続的な運転に支障が生じかねない状況だ。
この特重施設の対応に区切りが付き次第、同3号機の本体施設に関わる審査対応が本格化する。政府がカーボンニュートラル社会へ原子力の活用を標榜する中、東日本大震災後、初の新規稼働を実現するためにも、慎重かつ迅速な対応が求められている。
東京電力 柏崎刈羽/新潟県知事の判断が鍵
東京電力柏崎刈羽原子力発電所6、7号機は17年12月、新規制基準の適合性審査に合格した。同月、原子力規制委員会は安全性の最優先など「七つの約束」の順守を条件に、東京電力に原子力事業者としての「適格性」を認定。また規制委は20年10月、7号機の設計・工事計画、保安規定の変更を認可した。
しかし一方で20年9月、核物質防護に関して、他人のIDカードを使用した中央制御室への不正入室が発覚。21年3月には原子力規制庁が、侵入検知設備が損傷していながら復旧に長期間を要し、実効性のある代替措置も講じられていなかったことを指摘。規制委は同月、東京電力に事実上の運転停止命令(核燃料の移動禁止措置)を発出し、核物質防護に関わる追加検査などを行っていた。昨年12月に運転禁止命令を解除、東京電力の「適格性」を再判断した。
 柏崎市で行われた冬季避難訓練
柏崎市で行われた冬季避難訓練
提供:朝日新聞
再稼働に向けては、地元同意が得られておらず、広域避難計画も未策定だ。地元同意については新潟県の花角英世知事が「県民の信を問う」構えを見せる。
広域避難計画の策定については、除雪時の人員確保や避難道路の整備拡充、鉄道網の活用など実効性の向上が求められているが、昨年12月に国が大雪時対応の全体像を提示するなど策定に向けて前進している。
日本原電 東海第二/「避難計画」がハードルに
日本原子力発電東海第二発電所は18年9月、新規制基準の適合性審査に合格した。10月には規制委が設計・工事計画を認可、11月には運転期間の延長を認めた。現在、今年9月の完了を目指して安全性向上対策工事を実施しているが、防潮堤の基礎で一部不備が見つかり、その原因分析や対策を進めている。
広域避難計画は未策定の自治体があるが、立地する東海村が昨年末に避難計画を公表し、隣接する日立市も年度内に公表する方針を示すなど地域防災の動きが加速している。
しかし、原子力発電所の半径30㎞圏内(UPZ)に含まれる14市町村の人口は約92万人と全国最多。避難計画の実効性向上が課題となっている。茨城県は昨年11月、日本原電の協力を得て、30㎞周辺まで避難・一時移転が生じるような仮想的条件での拡散シミュレーションを公表した。今後、茨城県はこの結果も踏まえて、広域避難計画の実効性向上を図っていくとみられる。
21年3月には、水戸地裁が避難計画の未作成などを理由に運転差し止めを認容する判決を出しており、現在、東京高裁で控訴審が行われている。