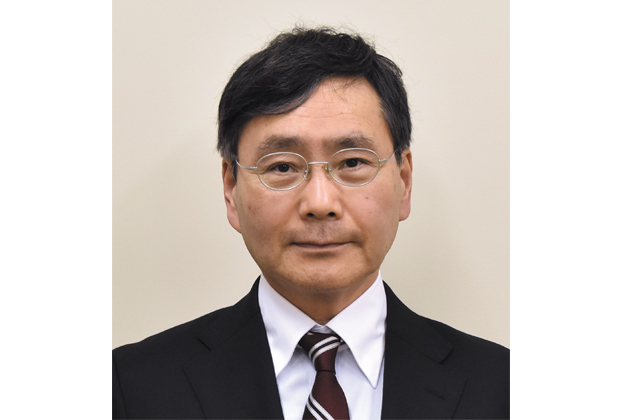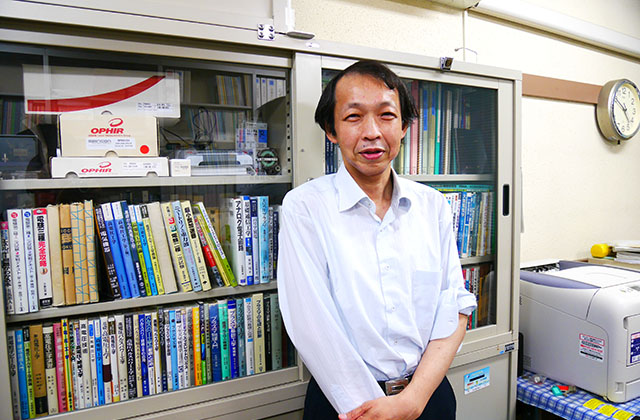EVの普及が進展する一方で、合成燃料の実用化も視野に入ってきた。
充電インフラとSS、それぞれの事業者に脱炭素時代への取り組みを聞いた。
【インタビュー①】丸田 理/CHAdeMO協議会 事務局長
充電インフラ整備は極めて順調 料金適正化や信頼性向上が課題に
―日本のEV市場をどう見ていますか。
丸田 国内市場は昨年、日産が軽EVサクラを発売し、海外勢も中国のBYDや韓国のヒョンデなどが相次いで進出しました。市場の成長は加速するでしょう。
今後、EVは都市部や地方問わず満遍なく普及するとみています。特に地方の場合はサービスステーション(SS)の数が減り、隣町まで車を走らせなければ給油できない地域も存在します。こうした点で、自宅で充電できるEVには圧倒的な優位性があります。サクラの売り上げも好調ですが、軽EVの車種が増えれば普及は一段と進むでしょう。一方、大都市圏ではテスラを筆頭に海外メーカーのEVも普及すると思われます。

―ほかにEVの強みは?
丸田 災害時のレジリエンス機能です。2018年の胆振東部地震では北海道電力管内でブラックアウトが発生しましたが、Ⅴ2H(ビークル・トゥ・ホーム)によって数日間の電力を供給できた事例があります。また11年の東日本大震災ではガソリンの供給不安が発生し、SSに長蛇の列ができましたが、日産のリーフや三菱のアイ・ミーブなどのEVが被災地に送られ、復興活動で活躍した実績もあります。
―国内充電インフラの整備の現状を教えてください。
丸田 極めて順調に進んでいます。日本はこれまで、空白地帯が生まれないよう、全国規模で面的な整備を進めてきました。高速道路では数十㎞おきに、一般道ではほぼ全てのカーディーラーが充電器を設置しています。SSよりも充電器を探す方が簡単な地域もあるほどで、諸外国と比べても面的なカバー率や設備の可用性は高いレベルにあります。
―課題はありますか。
丸田 料金体系の適正化が課題の一つです。現在、急速充電の料金体系は充電時間に応じた時間制課金が主流ですが、車や充電器の性能でサービスに格差が生じています。そこで22年に計量法に関する規制緩和が行われ、充電器の計量機能を取引に使えるようになりました。ただ急速充電器の出力は10~150kWとさまざまで、車載電池の性能によっても充電可能な出力が変わります。今後は各事業者が利用実態に応じて時間制課金と従量制課金を併用するなど、柔軟な料金設定が求められています。
―CHAdeMO(チャデモ)協議会としての課題は?
丸田 欧州と北米は法的な規制でCCSという充電規格の採用を義務化している国・地域が多く、チャデモ対応の車種が増えることは考えにくいです。当然、日本メーカーも欧州・北米向けにはCCS対応車種を製造しており、チャデモの欧州や北米への浸透は厳しい状況にあります。
―今後はどのような取り組みを展開しますか。
丸田 アジアを中心にEV市場の拡大を見込む地域では、チャデモの強みを生かせると考えています。例えば、Ⅴ2Hなど双方向の給電機能を製品として実現できている規格は世界でチャデモだけです。電力系統機能が弱い新興国などでは、V2Hが系統の安定に寄与する可能性も秘めており、積極的にアピールします。
国内で最優先に取り組むのは、信頼性の維持です。現在、EVの車種が増えたことで不具合の件数が増えています。中でも、海外メーカーは自国の製造拠点でチャデモの精密なテストを行うことが困難なケースもあります。そこで11月に三重県でマッチングテストセンターの運用を開始し、車両の市場投入前にテストを行える環境を整備します。海外では充電器の故障や稼働率の低さが問題となっていることもあり、信頼性という点で日本がロールモデルとなることは、チャデモの海外普及という点でも重要だと考えています。