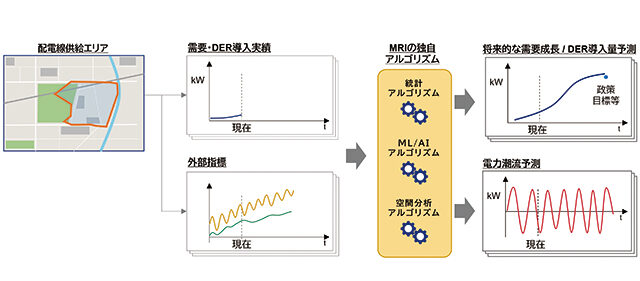原子力発電所の建設を禁止しているオーストラリアで、原発導入の気運が高まっている。
最大野党の保守連合(自由党・国民党)は、2025年に予定される総選挙の公約に原発導入を掲げる見通しだ。
「労働党は、地方部への再生可能エネルギー導入と送電網の開発を性急に進める誤った判断をしている」。自由党きってのエネルギー政策通で、原発推進派のテッド・オブライエン下院議員は8月、原発に反対するアルバニージー現政権のエネルギー政策を痛烈に批判する傍ら、立地地域の住民の意見に配慮しながら原発導入を進めていく必要性を強調した。
野心的な脱炭素政策を掲げる豪州は、火力発電所の閉鎖計画でエネルギー不足が顕在している。エネルギー問題の解消、産業転換による雇用の確保、気候変動対策という三つの背景から、最大の争点に浮かび上がる可能性が出てきた。
自由党が次期総選挙をにらみ、原発の導入推進を声高に訴え出したのは、1年前にさかのぼる。ピーター・ダットン党首が政党間協議の場で「エネルギーの安全保障に寄与し、電力価格を下げる手段として、次世代の原子力技術の可能性を模索する」と明言したのだ。保守連合は原発推進を次期総選挙の公約とする方向だ。原発導入に反対する現政権のエネルギー政策との違いを鮮明にすることで、政権奪取の足掛かりをつくる狙いが透けて見える。
豪州では1990年代に制定された「環境保護・生物多様性保全法(EPBC法)」と、「放射線防護・原子力安全法」の二つの連邦法に原発開発を禁止する条項が盛り込まれている。世界最大のウラン埋蔵国であるにもかかわらず、原発の建設、稼働ができないのはこのためだ。
現実的な選択肢で俎上に 電力の危機的状況が後押し
ただ自由党など保守勢力は2000年代から原発の可能性について模索していた。モリソン前政権内でも、二つの法律から原発活用を禁止する条項を削除することを、総選挙の公約にしようと目論んでいた経緯がある。
今回、保守連合が再び原発導入の議論を活発化させてきたのは、保守勢力の悲願を現実のものにしたいという表れだ。
だが原発導入の議論は単なる政争の具として浮上しただけではない。豪州のエネルギーの在り方を問いかける現実的な選択肢として俎上に載せられたのだ。急激な脱炭素化による深刻な電力不足が顕在化したことが、大きく影響した格好だ。
豪州のエネルギー市場の管理などを担うエネルギー市場オペレーター(AEMO)は8月下旬、23年12月~24年2月ごろの夏季にかけて電力需給がひっ迫する可能性があると警告した。一部の州では停電リスクがあるとも指摘。気候変動の影響が顕著になる今後10年間について、一部の州を除き全国的に供給不足に陥る可能性があるというのだ。
現政権は脱炭素化を急速に進める政策を前面に打ち出し、30年には再エネ発電量を現在の約40%から82%に引き上げるという途方もない目標を掲げている。
このため、やり玉に挙がる石炭火力発電所などは早期閉鎖を余儀なくされており、すでにいくつかの火力が停止している。再エネ導入は急ピッチで進められているものの、新規投資が遅れており、火力の閉鎖分を補えるほどではない。気候変動の影響で高まっている需要に対して、有効な策が打てない状況といえよう。
 自国産ウラン資源を活用する狙いも(豪州北部のウラン鉱山)
自国産ウラン資源を活用する狙いも(豪州北部のウラン鉱山)
こうした電力の危機的状況が、原発導入の議論を後押ししていることは否めない。前出のオブライエン下院議員の政権批判も電力不足問題の延長線上にある。火力のように温室効果ガスを排出しない、自然条件で変動する再エネとは違い設備稼働率が安定的な原発こそが、脱炭素化と電力不足を両立できるというわけだ。
こうした状況が理解されているのか、世論も原発導入には好意的だ。豪州の経済紙オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューが7月に実施した読者調査によると、回答者の58%が化石燃料を廃止するための解決策として、小型モジュール炉(SMR)を使った原発の導入を望んでいると答えた。また資源業界団体の最近の調査でも、原発導入について賛成が45%に上ったという。
経済界も前向きだ。現地メディアは、経済団体のオーストラリア産業グループとオーストラリア・ビジネス・カウンシル、オーストラリア労組が22年8月、上院委員会で原発を電源構成から除外しないよう求めたと報じた。
オーストラリアの建設・林野・鉱山・エネルギー労組は、老朽化した石炭火力の代わりに、SMR建設を提案した。これにより、10年間で810人の直接雇用と建設時に1600人の雇用が創出されると説明。産業転換による雇用問題の解決にもつながると主張している。
政権側は火消しに躍起 日本のビジネス機会に?
このような原発推進の動きに対し、政権側は火消しに躍起だ。現地メディアの報道などによると、クリス・ボーエン気候変動・エネルギー相は、コストが極めて高いことや、建設に時間がかかり、多大な放射性廃棄物が出るなどの理由から原発導入に反対している。
他の政権幹部は「野党の原子力に対する新たな恋心は、最も安価なエネルギーである自然エネルギーにイデオロギー的に反対しているだけだ。根拠がある信頼できるエネルギー政策を(自らが)持っていないという事実から目をそらそうとしているにすぎない」と、野党側を厳しく批判した。
ただ与党労働党が賛成する豪米英の安全保障枠組み「AUKUS(オーカス)」による原子力潜水艦の導入が、豪州内での原発を含めた原子力の技術研究や開発に道を開くきっかけになるのではないかとの指摘もある。
豪州では25年の総選挙に向けて、原発導入の是非を巡る議論はさらに盛り上がることだろう。エネルギー政策の失策が原因で政権交代が起こるようなことがあれば、原発の導入が現実味を帯びてくる。日本のエネルギー関連企業にとっても新たなビジネスチャンスが到来するかもしれず、動向から目が離せない。