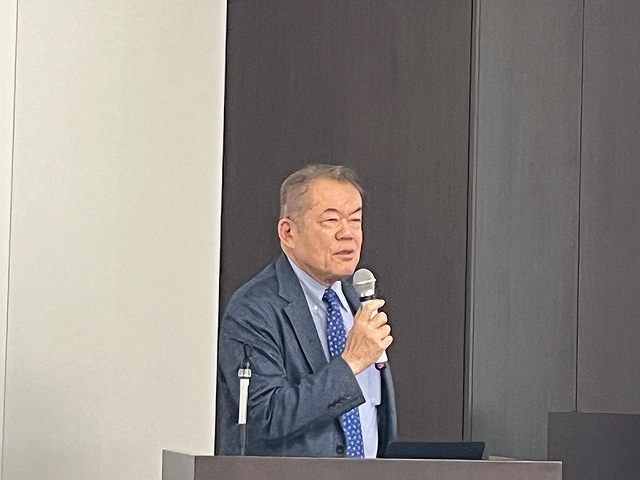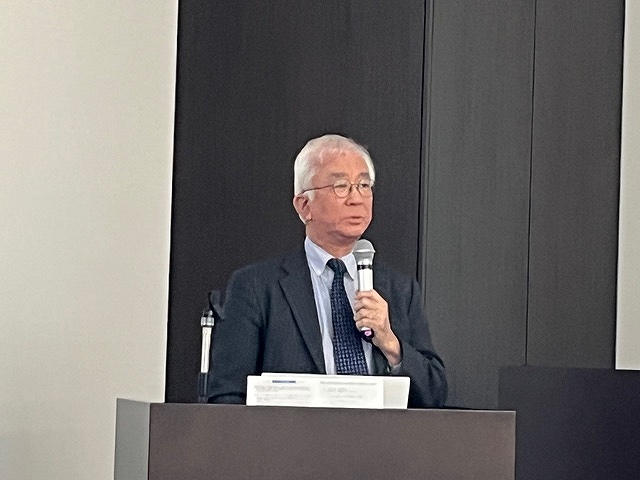政府公募では行き過ぎた価格重視により競争環境が歪んだ結果、事業継続が危ぶまれる事態に陥った。R2・3への緊急避難的措置、そしてR1再公募とR4以降のルール見直しが進むが、事態は好転するのか。
洋上風力産業が正念場を迎えている。近年の世界的なインフレに伴うコスト増のうねりが、日本でも猛威を振るう。さらに需要側でも変化が。数年前の世界的なエネルギー価格高騰局面では再生可能エネルギーの電気を高くても確保したいとの雰囲気があったが、今は市場が緩み、そうした空気が薄れている。
一部報道は、一般海域での洋上風力を巡る政府公募ラウンド1(R1)に続く「撤退ドミノ」の可能性を指摘する。政府公募はR3までの約450万kWが決定済みだ。特に、第三次保証金の支払い期限が年末(秋田県八峰・能代はその3カ月後)に迫るR2各社の動向が注目される。まだどの海域も最終投資決定(FID)に至っていない。
政府は撤退ドミノをなんとしても防ごうと、資源エネルギー庁と国土交通省の合同会議でR2・3の事業完遂に向けた支援策などを検討中だ。これまでに示されている事業期間の延長や価格調整スキームなどに加え、さらなる措置が俎上に載る。最も注目されるのが長期脱炭素電源オークション適用の行方であり、この詳細は後半で触れる。
R1継続模索も断念 地域では混乱広がる
三菱商事に改めて撤退理由を聞くと、入札当時の物価・為替水準などを踏まえて「事業性が見込める価格で応札した」ものの「公募時のリスク想定を大きく上回る事業環境の変化が生じた」とコメント。あらゆる手段を精査したが「開発の継続は困難」と結論付けた。コスト面は、入札時に見込んだ金額と比較し、「建設費用は2倍以上」に。収入面では、政府がそれまでに示した措置を考慮してもコスト増をカバーできる価格水準での売電は困難と判断した。
撤退が決まった地域では混乱が広がる。千葉県銚子市の場合、2月に三菱商事がゼロベースで事業性再評価に着手してから半年間具体的な説明はなく、市に撤退の知らせが届いたのは発表当日の午前中だった。市洋上風力推進室の八角貴志室長は「住民や漁業関係者の反発は少なく、順調に進んでいただけに衝撃だった」と振り返る。
銚子はR1で最も早く運転を開始する計画だった。市と漁業協同組合、商工会議所がメンテナンス会社を共同設立したが、人材育成の取り組みが宙に浮き、視察による宿泊・飲食業などへの波及効果が失われつつある。
秋田県由利本荘市では、本荘港をO&M(運転・保守管理)拠点として活用する構想を進め、地元企業が水上ドローン事業に参画するなど、準備を進めていた矢先の知らせだった。海底地盤調査で想定より軟弱であることが判明し、計画見直しの動きはあったものの、やはり撤退は想定外だったという。
R2以降の地域の関係者にとっても、撤退が続くことは由々しき事態だ。三菱商事が説明するような環境変化は個社に限った話ではなく、他地点の状況はどうなのか。