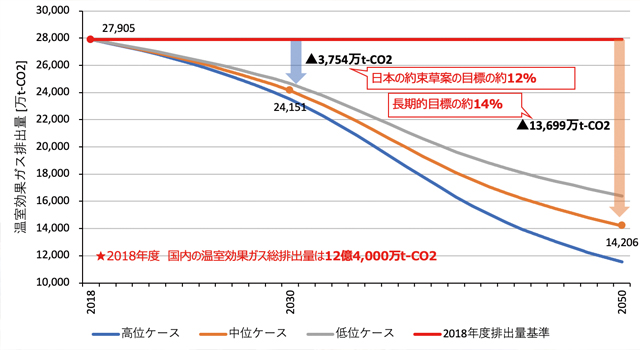静岡県では、大都市圏に近い立地環境などから多彩な産業が発達している。
こうしたことを背景に、エネルギー政策と経済活性化との両立が必須だ。
企業同士、または産学官の「連携」による新ビジネス創出への動きが始まっている。
大消費地に近く、東海道の主要幹線が東西に横断する恵まれた立地環境のもと、静岡県には多彩な産業が集積している。東部は首都圏からのアクセスの良さや地下水が豊富なことから製紙・化学工業が発達。一方、西部は自動車や二輪車などを中心とする工業地域を形成している。第二次産業の割合が44%と全国の27%に比べて高く、2018年の製造品出荷額は全国4位と上位に位置する。

電動車100%への対応 事業転換が課題に
このように、製造業が盛んな土地柄のため、県はエネルギー政策と両輪で産業振興を進めている。17年に「ふじのくにエネルギー総合戦略」を策定し、①創エネ、②省エネとともに、③経済活性化を盛り込んだ3本柱を設定。豊かな自然環境を生かした再生可能エネルギーを中心に分散型エネルギーシステムの導入拡大とともに、地域企業によるエネルギー関連産業への参入促進を目指している。
「地域エネルギーの地産地消に重点を置き、かつ技術開発を進めることで地域経済の振興につなげていく狙いがあります」。経済産業部産業革新局エネルギー政策課の川田剛宏課長はこう話す。
静岡県は日照時間が長く、国内有数の山岳地帯を持つことから、太陽光発電や小水力、バイオマスはいずれも全国上位の導入量を誇る。中でも太陽光発電は、18年度末時点で導入容量が約193万kWに上り、東日本大震災の翌年、12年末時点の約28万kWから急増した。
これにより、地産エネルギー導入率やエネルギー自立化率は20年度までの目標値を前倒しで達成。さらに、②省エネでは、くらし・環境部との連携により、クールビズなどの行動様式の変革に取り組み、エネルギー消費効率でも前倒しでの目標達成を実現した。
こうしたことから、数値目標の見直し、また県の新ビジョンを盛り込んだ新たな総合計画の期間との整合性を図る上で、エネルギー総合戦略の期間を21年度に延長。上方修正した新たな目標達成に向けた施策を推進している。
喫緊の課題が、「脱炭素社会の実現」を視野に入れたエネルギー政策の展開だ。県内には軽自動車大手・スズキの工場が立地するほか、トヨタ自動車と取引のある部品メーカーが多い。製造品出荷額のうち、自動車関連が約26%を占め、都道府県別では、愛知県に次いで第2位となる主力産業だ。
こうした中、政府がとりまとめた「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、遅くとも30年代半ばまでに、乗用車の新車販売を電動車100%にする方針が示された。川田課長は「ここ数年、ガソリン車からハイブリッド車への移行に向けた産業の変化が課題でしたが、電動化はさらに早急な対応に迫られます」と危機感をあらわにする。
既存のエンジン技術とは異なり、電気自動車はモーター技術が必要になる。そのため、関連企業ではこうした新技術への対応に向けた事業の転換が求められる。
県では今後、次世代自動車関連の産業振興を進める方針だ。その一つ、次世代自動車センター浜松では関連企業の固有技術を活用した次世代自動車の部品製造により、新たなビジネス展開に向けた開発・設計から製造・販売まで、ワンストップでの支援を行っている。
連携を積極的に推進 革新的な技術開発へ
さらに、今後、従来のビジネスモデルからの転換や革新的な技術開発を急速に進めていく上で、企業同士、もしくは大学や自治体と連携を進める動きが始まっている。
県では、再エネや地産地消、小規模分散型エネといったテーマごとに企業や大学、金融など他業種が参加するグループを作っている。例えば、創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会では144の企業・団体を集め、勉強会や講演会で情報共有を行うなど、技術開発に向けた企業間連携をコーディネートする形で支援する体制を整えている。
一方、静岡市は、内閣府に選定された「SDGs(持続可能な開発目標)未来都市」の取り組みの一環として、SDGs宣言事業を実施。SDGsに取り組む企業・団体から宣言書を集め、企業間連携につなげていく構えだ。参画企業・団体は20年11月末時点で207に上り、エネルギー関連では中部電力や静岡ガス、鈴与商事などが名を連ねる。

市ではこれまで関連イベントの開催や広報誌による特集記事の掲載などにより、まずはSDGsの認知度向上を図ってきた。この活動が奏功し、現在の認知度は50%を目標とする中、46・5%を達成。そこで、次なる展開として、SDGsに参画した事業者同士のマッチング支援を行い、新規事業の創出につなげていく。メリットは多種多様な業種が参画している点だ。市企画局企画課の稲葉博隆課長は「各社の強みを持ち寄り、弱みは補完する連携体制により、ビジネスが成り立つ取り組みにしていきたいです」と意気込む。
こうした自治体の取り組みがある中、県内ではさまざまなエネルギー事業が進んでいる。次ページ以降、各社の取り組みを紹介する。